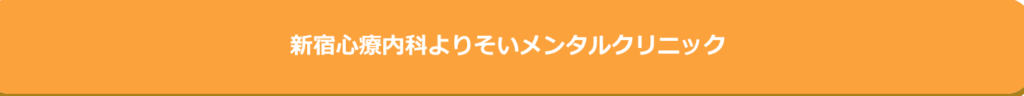
ストレスやパワハラによって心身に不調を感じ、「もう会社に行けない」「休みたい」と考えている方もいるかもしれません。体調を崩しながら無理して働き続けることは、さらなる悪化を招く可能性があります。
時には、心と体を立て直すために「休職」という選択肢が必要になることもあります。しかし、休職を考え始めても、どうすればいいのか分からない、お金はどうなるのか、その後のキャリアはどうなるのか、といった多くの不安がつきまとうでしょう。
この記事では、ストレスやパワハラを原因とする休職について、その可能性から具体的な手続き、期間、休職中の経済的な補償、そして休職後の選択肢まで、知っておくべき情報を詳しく解説します。一人で悩まず、この記事を参考に、ご自身の状況を整理し、適切な一歩を踏み出すためのヒントを見つけてください。
ストレスやパワハラでの休職はできるのか?

ストレスやパワハラは、時に心身に深刻な影響を及ぼし、就労が困難な状態に追い込むことがあります。このような状況に陥った場合、「休職」は可能なのか、と疑問に思う方もいるでしょう。結論から言えば、精神的な不調やパワハラが原因で働くことが難しくなった場合、休職は可能です。ただし、いくつかの条件や手続きが必要になります。
精神的な不調で休職するケース
ストレスが原因で精神的な不調をきたした場合、医師から「休養が必要である」と診断されれば、休職を検討することができます。
具体的な診断名としては、
- 適応障害
- うつ病
- 不安障害
- 睡眠障害
などがあります。
これらの病気は、仕事上のストレスや人間関係などが引き金となって発症することが多く、治療のためには原因から一時的に離れることが有効とされています。医師は、患者の症状や状態を診察し、休職の必要性や期間を判断します。この医師の診断が、会社に休職を申請する上での重要な根拠となります。
企業の多くには「休職制度」が設けられています。これは、従業員が病気やケガなどで長期にわたり働くことが困難になった場合に、一定期間の休養を認め、その後の復職を前提とする制度です。精神的な不調による休職も、この制度の対象となるのが一般的です。厚生労働省のウェブサイトでは、職場におけるメンタルヘルス対策の推進について基本的な方針や具体的な実施方法を示しており、その中で休職・復職支援についても触れられています。
ただし、休職制度は法律で定められた義務ではなく、企業ごとにその有無や内容は異なります。就業規則に休職制度の規定があるか、どのような条件で利用できるかを確認することが重要です。
パワハラが原因の休職は可能
パワハラ(パワーハラスメント)は、職場におけるいじめや嫌がらせの一種であり、働く人々の心身の健康を著しく害する行為です。パワハラによって精神的な苦痛を受け、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症し、働くことが困難になった場合も、休職は可能です。
パワハラは、単なるストレス源というだけでなく、企業の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)にも関わる問題です。企業には、従業員が安全かつ健康に働けるように配慮する義務があり、パワハラを防止し、発生した場合には適切に対応する責任があります。厚生労働省が発行するパワハラ防止法対応ガイドブックでは、事業者向けの具体的な予防策や相談窓口設置の義務、事後対応などが解説されています。
パワハラが原因で体調を崩し休職する場合も、精神的な不調の場合と同様に、まずは医療機関を受診し、医師の診断を受けることがスタート地点となります。医師から休養が必要であると診断されれば、診断書を会社に提出して休職を申請します。
さらに、パワハラが原因で精神疾患を発症した場合は、労災(労働災害)と認定される可能性があります。労災認定されると、治療費や休業期間中の所得補償などが労災保険から給付されるため、経済的な負担を軽減できます。ただし、パワハラによる精神疾患の労災認定には、厳しい基準が設けられています。パワハラの内容、頻度、期間、業務との関連性などが詳細に調査されます。労災申請については後ほど詳しく解説します。
パワahparaによる休職は、単に体調を回復させるためだけでなく、パワハラという不当な行為から身を守るためにも必要な場合があります。休職期間中に、パワハラ問題の解決に向けた話し合いを進めたり、外部の専門機関に相談したりすることも検討できます。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

休職する際の手続きの流れ

ストレスやパワハラが原因で休職を決意した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。一般的には、以下の流れで進めます。会社の規定によって詳細な手順は異なる場合があるため、就業規則を確認するか、人事担当者に問い合わせるのが確実です。
医師の診断を受ける
まず最初に行うべきことは、医療機関を受診し、医師の診断を受けることです。精神的な不調の場合は心療内科や精神科を、体調不良全般についてはかかりつけ医や一般の内科を受診しても良いでしょう。
診察時には、現在の症状(不眠、食欲不振、気分の落ち込み、動悸、頭痛など)を正直に伝え、仕事上のどのようなストレスや出来事(パワハラの内容など)が原因と考えられるかを具体的に説明しましょう。
医師は、これらの情報と診察の結果に基づいて、病名(または診断名)を診断し、休養が必要かどうか、必要であればどのくらいの期間休むべきかを判断します。
休職するためには、通常、会社に医師の診断書を提出する必要があります。診察の際に医師に「休職が必要であること」「具体的な病名(または診断名)」「必要な休養期間」を診断書に記載してもらえるよう依頼しましょう。診断書は、会社の書式がある場合や、医師の書式で良い場合がありますので、事前に会社に確認しておくとスムーズです。診断書の発行には費用がかかるのが一般的です。
中央労働災害防止協会や日本精神衛生学会などが提供する資料も、休職判断の基準や産業医面談などについて参考にすることができます。
医師に現在の状況を正確に伝えることが、適切な診断と必要な休養期間の判断につながります。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることが大切です。
診断書を会社に提出
医師から診断書を受け取ったら、速やかに会社に提出します。提出先は、通常は直属の上司か人事部になります。会社の規定やこれまでの経緯によって適切な提出先が異なる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
診断書を提出する際には、現在の体調が優れないため休職を検討している旨を伝え、休職制度の利用について相談したいと申し出ます。診断書は、客観的な証拠として休職の必要性を会社に示す重要な書類です。
診断書を提出するタイミングも重要です。症状が重く、すぐにでも休養が必要な場合は、診断書を提出し、即日あるいは数日内の休職を希望する旨を伝えることも可能です。ただし、会社の承認や引き継ぎなども考慮する必要があるため、可能であれば、ある程度の猶予をもって相談するのが望ましいでしょう。緊急性が高い場合は、電話などで口頭で先に状況を伝え、後から診断書を提出するなどの対応が必要になることもあります。
パワハラが原因で休職する場合、加害者が直属の上司であることもあります。その場合は、人事部や会社の相談窓口など、加害者を経由しないルートで診断書を提出し、相談するようにしましょう。
診断書は、休職開始の根拠となるだけでなく、休職期間中や復職時の手続きにおいても必要となる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。
会社との話し合い・休職申請
診断書を提出した後、会社側と休職についての話し合いが行われます。話し合いの相手は、人事担当者や直属の上司(パワハラが原因でない場合)、またはその両方になることが多いです。
この話し合いでは、主に以下の点について確認が行われます。
- 休職開始日と期間: 医師の診断書に基づき、いつから休職を開始し、いつまで休職するかを決定します。会社の休職規定で定められた期間の上限がある場合もあります。
- 休職中の連絡方法: 会社からの連絡の要否、連絡手段(電話、メールなど)、頻度について取り決めます。病状によっては、休職期間中は会社からの連絡を一切受けたくない旨を伝えることも可能です。
- 休職中の給与・手当: 休職期間中の給与の支払いについては、会社の規定によりますが、多くの場合は無給となります。健康保険からの傷病手当金の申請や、パワハラによる労災認定の可能性などについて説明を受ける場合もあります。
- 社会保険料の取り扱い: 休職期間中も社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は原則として発生します。支払い方法について会社と取り決めます(給与天引きができない場合の振込方法など)。
- 復職の条件・手続き: 休職期間満了後の復職に向けた手続きや、復職可否の判断基準(医師の診断、産業医面談など)について説明を受けます。
- 引き継ぎ: 業務の引き継ぎが必要な場合は、体調と相談しながら可能な範囲で行います。緊急性が高い場合は、引き継ぎが難しい場合もあります。
これらの話し合いの後、会社所定の「休職願」や「休職申請書」を提出するのが一般的です。申請書には、休職理由、休職期間、医師の診断などを記載します。提出された申請書に基づき、会社が正式に休職を承認することで、休職が開始されます。
話し合いの中で不明な点や不安な点があれば、遠慮せずに質問しましょう。特に、お金のことや復職・退職に関することは、今後の生活に大きく関わるため、しっかりと確認することが重要です。パワハラが原因の場合は、安心して休養できるよう、加害者との接触がないように会社に配慮を求めることも必要です。
ストレス・パワハラ休職の期間はどれくらい?

ストレスやパワハラによる休職期間は、個々の病状や会社の休職制度によって異なります。一般的な目安はありますが、画一的に決まるものではありません。
一般的な休職期間の目安
多くの企業の休職制度では、休職期間に上限が設けられています。この上限は、勤務年数によって異なる場合や、一律で定められている場合があります。例えば、勤続3年未満は〇ヶ月、3年以上は〇ヶ月、といった規定や、一律で1年や2年まで、といった規定が見られます。
実際の休職期間は、医師が必要と判断した期間に基づき、会社の休職規定の範囲内で決定されます。精神的な不調の場合、回復には個人差がありますが、一般的には数ヶ月から半年、長ければ1年以上の休養が必要となるケースもあります。
医師は、診断書に必要な休養期間を記載しますが、これはあくまで現時点での目安です。病状の回復具合によって、期間が短縮されたり、延長されたりする可能性があります。
初めて休職する場合、まずは比較的短期間(例えば3ヶ月や半年)で休職を開始し、その後の病状を見ながら期間を検討していくというケースも少なくありません。
期間延長や短縮の可能性
休職期間中に病状が回復し、医師が早期の復職が可能であると判断した場合、会社の承認を得て休職期間を短縮して復職することができます。
一方で、休職期間満了時までに病状が十分に回復しない場合、医師が引き続き休養が必要であると診断すれば、会社の休職規定の範囲内で期間を延長できる可能性があります。休職期間の延長には、再度医師の診断書が必要になるのが一般的です。会社の休職規定で定められた最長期間を超えての休職は、通常は認められません。最長期間を超えても復職できない場合は、休職期間満了による退職となるケースが多いです。
休職期間の延長や短縮の可能性については、会社の休職規定に定められていますので、事前に確認しておくことが重要です。また、期間の変更が必要になった場合は、速やかに会社に相談し、医師とも連携を取りながら手続きを進めましょう。
病状の回復には波があることも理解し、焦らず、医師の指示に従って療養に専念することが、結果的に早期回復につながります。
休職中のお金(給料・手当・補償)

休職期間中、多くの企業では給与の支払いはありません。しかし、生活費や治療費の心配なく療養に専念できるよう、いくつかの公的な制度による経済的な補償があります。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガのために働くことができず、会社から十分な給与が支払われない場合に支給される手当です。ストレスやパワハラによる精神的な不調で休職した場合も、この傷病手当金の対象となります。
傷病手当金を受給するための主な条件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガであること: ストレスやパワハラによる精神疾患は、通常、業務外の病気とみなされます。(ただし、パワハラが原因で労災認定された場合は、後述する労災保険からの給付が優先されます)
- 療養のために労務不能であること: 医師が「働くことができない」と診断している状態であること。
- 連続する3日間を含む4日以上仕事を休んだこと: 待期期間として、最初に仕事を休んだ日から連続して3日間休む必要があります。この3日間は傷病手当金の支給対象となりません。4日目以降から支給対象となります。
- 休業した期間について給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ないこと: 会社から給与が支払われている場合は、その給与額と傷病手当金の差額が支給されるか、給与が傷病手当金より多い場合は支給されません。
支給額:
傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として「支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」の30分の1に相当する額の3分の2です。
(標準報酬月額の平均額 ÷ 30日)× 2/3
支給期間:
同一の病気やケガについて、支給開始日から最長で1年6ヶ月です。途中で一時的に復職しても、再び同じ病気で休んだ場合は、以前の支給期間と通算されます。
申請方法:
傷病手当金は、ご自身が加入している健康保険組合(または協会けんぽ)に申請します。申請には、医師の意見書、会社の事業主の証明書、ご自身の申請書などが必要になります。申請書は、健康保険組合のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。通常、休業期間をまとめて申請しますが、継続して休む場合は1ヶ月ごとなどに区切って申請することも可能です。
傷病手当金の申請手続きには少し時間がかかる場合があるため、早めに準備を進めることが大切です。詳細は、加入している健康保険組合に確認してください。
パワハラによる労災認定
パワハラが原因で精神疾患を発症し、休職せざるを得なくなった場合、労働災害(労災)と認定される可能性があります。労災認定されると、労災保険から治療費や休業期間中の補償が受けられます。
労災認定の基準:
パワハラによる精神疾患が労災と認定されるには、厚生労働省が定めた認定基準を満たす必要があります。主なポイントは以下の通りです。厚生労働省の資料「精神障害の労災認定」では、詳細な技術的基準や心理的負荷の評価方法などが解説されています。
- 対象となる精神障害を発病していること: うつ病、適応障害、PTSDなどが対象となります。
- 業務による強い心理的負荷があること: パワハラの内容、頻度、継続期間などから、業務による心理的負荷が「強」であると認められる必要があります。具体的には、人格や尊厳を傷つけるような言動、過大な要求、過小な要求、人間関係からの切り離しなどが、継続的・反復的に行われた場合などが該当し得ます。
- 業務以外の原因(個体側要因)により発病したものではないこと: パワハラ以外の個人的な問題(家庭内の問題、既存の精神疾患など)が原因でない、または業務による心理的負荷がそれらを上回るほど強いと判断される必要があります。
申請方法と流れ:
労災申請は、所轄の労働基準監督署に行います。「療養補償給付たる療養の費用請求書」や「休業補償給付支給請求書」などの書類を作成し、提出します。申請書には、事業主の証明が必要な欄がありますが、パワハラが原因で会社に証明を拒否される場合は、その旨を労働基準監督署に伝え、事業主の証明が得られない理由書を添えて提出します。
申請後、労働基準監督署が調査を行います。調査では、本人や会社の関係者からの聞き取り、医師への照会、タイムカードや業務日報などの資料確認などが行われます。この調査に基づいて、労災認定されるかどうかが判断されます。労災認定の判断には時間がかかる場合が多いです。
給付内容:
労災認定された場合、以下の給付などが受けられます。
- 療養補償給付: 治療費や薬代などが全額支給されます。
- 休業補償給付: 休業4日目から、給付基礎日額(原則として、事故発生日または診断日以前3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割った1日あたりの賃金額)の80%(休業補償給付60% + 休業特別支給金20%)が支給されます。
傷病手当金との関係:
傷病手当金と労災保険の休業補償給付は、同時に全額を受け取ることはできません。労災保険からの給付が優先され、労災保険から休業補償給付が支給される期間は、健康保険からの傷病手当金は支給されません。ただし、労災保険からの給付が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給される場合があります。
パワハラによる労災申請は複雑な手続きを伴うため、労働基準監督署や労働組合、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
会社からの休業補償
休職期間中の給与については、多くの企業の就業規則で「無給」と定められています。法律上、病気休業中の従業員に対して給与を支払う義務は、原則として会社にはありません(労働基準法に基づく休業手当の支払いは、会社の都合による休業の場合に適用されます)。
ただし、企業の福利厚生として、休業期間中に一定割合の給与を支給する規定がある場合や、見舞金などが支給される場合もあります。これは会社の任意によるものなので、必ず支給されるわけではありません。ご自身の会社の就業規則や賃金規程を確認するか、人事担当者に問い合わせてみましょう。
パワハラが原因の場合、企業が安全配慮義務違反を認め、損害賠償の一部として休業中の賃金を補償する合意に至る可能性もありますが、これは個別の交渉や裁判によるものであり、自動的に支払われるものではありません。
休職期間中は収入が大きく減る、あるいはゼロになる可能性が高いため、傷病手当金や労災保険などの公的制度をしっかりと活用することが経済的な不安を軽減し、療養に専念するためにも非常に重要です。経済的な補償について、主な制度を以下の表にまとめました。
| 制度名 | 対象となる休業 | 支給元 | 支給額(概算) | 支給期間 | 申請先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 業務外の病気・ケガ | 健康保険 | 標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3 | 最長1年6ヶ月 | 加入健康保険組合/協会けんぽ |
| 休業補償給付 | 業務上の病気・ケガ(労災) | 労災保険 | 給付基礎日額の80% | 原則として治癒または症状固定まで | 所轄労働基準監督署 |
| 会社からの休業補償 | 会社の規定による | 会社 | 会社の規定による(無給が多い) | 会社の規定による | – |
休職後の進路:復職か退職か

休職期間が終わりに近づくと、復職するか、あるいは退職するか、という大きな選択を迫られることになります。これは、ご自身の病状の回復具合、会社の状況、そして今後のキャリアプランなどを総合的に考慮して判断する必要があります。
復職に向けた準備と注意点
休職期間中に病状が回復し、「また働きたい」と思えるようになったら、復職に向けて準備を進めます。
- 医師の復職可能診断: まずは主治医に相談し、復職が可能であるかどうかの判断を仰ぎます。医師から「復職可能」という診断書をもらうことが、復職に向けた第一歩となります。日本精神衛生学会なども、休職者の支援フローの中で医学的休職基準や職場復帰のプロセスを示しています。
- 会社との面談: 会社に復職したい意向を伝え、面談を行います。この面談では、現在の病状、復職に対する意欲、復職後の働き方(短時間勤務や業務内容の変更など)について話し合います。診断書を提出し、医師の意見を伝えます。
- 産業医面談: 多くの会社では、休職からの復職にあたって、産業医との面談が必須となります。産業医は、医学的な見地から従業員の健康状態や職場環境を評価し、復職の可否や復職後の就業上の配慮(残業を制限する、部署異動など)について会社に意見を述べます。正直に現在の体調や不安な点を伝えましょう。中央労働災害防止協会のガイドなども参考に、産業医面談に臨むと良いでしょう。
- 試し出勤制度: 会社によっては、本格的な復職の前に「試し出勤」を認めている場合があります。これは、短時間勤務から始めたり、リハビリとして軽作業を行ったりして、職場への適応fähigkeitを確認する期間です。いきなりフルタイムで働くのが不安な場合に有効なステップです。
- 復職後のフォローアップ: 復職できたとしても、すぐに元の調子に戻れるとは限りません。会社と連携し、定期的に体調について話し合ったり、必要に応じて業務量の調整をしてもらったりするなど、無理のないペースで働くことが大切です。産業医や人事担当者との面談を継続的に設定してもらうことも有効です。厚生労働省も、職場におけるメンタルヘルス対策として、こうした復職支援の重要性を指摘しています。
復職を急ぎすぎると、再び体調を崩してしまい、再休職や退職につながるリスクがあります。医師や会社の産業医とよく相談し、慎重に進めることが重要です。体調が完全に回復していないと感じる場合は、正直に伝え、復職時期や働き方について調整してもらいましょう。
パワハラ環境からの部署異動
パワハラが原因で休職した場合、元の部署に戻ることに強い抵抗を感じる、あるいは同じ環境では再び体調を崩してしまうのではないか、という不安があるのは当然です。
復職を検討する際に、パワハラ加害者から離れるために部署異動を会社に要望することは可能です。企業には、従業員が安全に働ける職場環境を提供する安全配慮義務がありますので、正当な理由に基づいた部署異動の要望には応じる責任があります。厚生労働省のパワハラ防止法対応ガイドブックでも、相談者への事後対応の一つとして配置転換などが挙げられています。
会社との面談の際に、パワハラの具体的な内容や、元の部署に戻ることの困難さ、部署異動を希望する旨を明確に伝えましょう。診断書に「元の部署での勤務は困難であり、配置転換が望ましい」といった医師の意見を記載してもらうことも、要望を通す上での助けになります。
ただし、会社の組織体制や人員配置の状況によっては、希望通りの部署異動が難しい場合もあります。会社とよく話し合い、代替案(加害者との接触を避けるための措置など)も含めて検討する必要があります。もし会社が適切な対応を取らない場合は、外部の相談機関に助けを求めることも検討しましょう。
休職期間満了での退職
会社の休職規定で定められた最長期間を満了しても、病状が十分に回復せず、医師が復職は困難であると判断した場合、その時点で自動的に退職となるのが一般的です。これは「自然退職」と呼ばれ、従業員側から退職を申し出るのではなく、会社の規定に基づいて雇用契約が終了する形となります。
休職期間満了による退職は、懲戒解雇のような不利益な解雇とは異なります。しかし、ご自身の意図しない形で離職することになるため、今後の生活設計に大きく影響します。
休職期間が満了に近づくにつれて、会社から今後の進路について確認の連絡が入るでしょう。医師の診断を踏まえ、復職が難しい場合は、休職期間満了での退職となることを受け入れざるを得ません。
退職が決まったら、会社から離職票を受け取り、失業給付の手続きなどを行います。また、次の仕事を探す、療養を続けるなど、今後の計画を立てる必要があります。経済的な不安がある場合は、失業給付以外にも利用できる公的な制度(生活保護など)についても情報収集しておきましょう。
メンタル不調で自然退職は可能か
「自然退職」という言葉は、広義には自己都合退職を含む場合もありますが、一般的には前述のように休職期間満了による退職を指すことが多いです。
メンタル不調を理由に、ご自身の意思で会社を辞めることは可能です。これは「自己都合退職」となります。休職期間を設けずに、あるいは休職期間中に、自ら会社に退職届を提出して退職します。
自己都合退職の場合、会社の就業規則に定められた退職手続き(通常は退職希望日の〇ヶ月前までに退職届を提出するなど)に従う必要があります。また、休職期間満了による自然退職とは異なり、会社の規定に基づくものではないため、休職制度の利用の有無に関わらず選択できます。
ただし、メンタル不調が原因で働くことが難しい状態であれば、まずは休職して療養に専念し、その後の回復状況を見て復職か退職かを判断する方が、経済的な面(傷病手当金など)やキャリアの選択肢を広げる上で有利な場合があります。安易に自己都合退職を選択する前に、まずは医師や会社の担当者に相談し、休職制度の利用を検討してみることをおすすめします。
休職中に会社をクビになるケース
休職中に会社から一方的に解雇されるのではないか、と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言えば、原則として、病気療養のための休職中に会社が従業員を解雇することは、労働契約法上、正当な理由がない限り認められません。
企業が従業員を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる必要があります(労働契約法第16条)。病気療養のための休職は、これに該当しません。むしろ、企業の休職制度は、従業員の療養機会を保障し、その後の復職を支援するためのものです。
ただし、例外的に以下のようなケースでは、雇用契約が終了する可能性があります。
- 休職期間満了による自動退職: 前述の通り、会社の休職規定で定められた最長期間を満了しても復職できない場合、自動的に退職となるケースは多いです。これは解雇ではなく、規定に基づく雇用契約の終了です。
- 休職制度がない会社の場合: ごく小規模な企業などで、就業規則に休職制度の規定がない場合があります。この場合、長期の病気休業が続くことで、労働契約上の債務不履行(労働力の提供ができない状態)とみなされ、普通解雇の対象となるリスクがゼロではありません。しかし、それでも解雇が有効と判断されるには厳しい要件(長期にわたり回復の見込みがないなど)があります。
- 休職原因と異なる問題: 病気療養とは全く関係のない、重大な服務規律違反などがあった場合は、病気休職中であっても懲戒解雇の対象となる可能性はあります。ただし、病気を理由とした解雇とは異なります。
- 就業規則違反: 休職中の過ごし方に関する規定(例えば、許可なく他の仕事をする、療養に専念しないなど)に明らかに違反した場合も、会社の規定によっては雇用契約の見直しや懲戒の対象となり得ます。
原則として、病気療養による休職は、会社の休職制度に基づき守られるべき権利です。不当な解雇の恐れがある場合は、労働組合や弁護士、労働基準監督署に相談しましょう。まずは、ご自身の会社の就業規則で休職制度がどのように定められているかをしっかりと確認することが重要です。
ストレス・パワハラ休職の相談先

ストレスやパワハラによる体調不良、そして休職という大きな出来事は、一人で抱え込むにはあまりにも重い問題です。適切なサポートを得るために、様々な相談先があります。
会社内の相談窓口
まずは、会社内に相談できる窓口があるか確認してみましょう。
- 人事部: 休職制度や手続きについて説明を受けられます。また、パワハラに関する相談窓口を兼ねている場合もあります。
- 産業医: 従業員の健康管理を専門とする医師です。体調について医学的なアドバイスを受けられるほか、復職の可否や職場環境について会社に意見を述べてもらうことも可能です。パワハラによる精神的な負担についても相談できます。中央労働災害防止協会のガイドなど、産業医の役割や相談の活用方法について参考になる情報もあります。
- 社内相談窓口(ハラスメント相談窓口): パワハラを含むハラスメントに関する相談を受け付ける窓口です。専門の担当者(社内・社外の場合あり)が対応し、問題解決に向けたサポートを行います。
ただし、パワハラが原因で休職する場合、加害者が上司や人事部の人間であるなど、会社内の人間関係が相談を難しくしているケースも少なくありません。会社内の窓口に相談することがためらわれる場合は、次に挙げる外部の専門機関を利用することを検討しましょう。
外部の専門機関
会社に相談しにくい場合や、より専門的なアドバイスが必要な場合は、外部の相談機関を利用しましょう。
| 相談先 | 主な相談内容 | 特徴・その他 |
|---|---|---|
| 労働組合 | 労働条件、解雇、ハラスメント、不当労働行為など | 労働者の権利を守る立場から会社との交渉をサポート。個人加盟できる労働組合も。 |
| 弁護士 | 法的問題全般(パワハラによる損害賠償請求、労災申請のサポート、不当解雇など) | 法律に基づいた専門的なアドバイスと手続きを代行。費用がかかる場合がある。 |
| 総合労働相談コーナー | 労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど労働問題全般 | 厚生労働省が運営。予約不要、無料で相談可。専門家(社会保険労務士など)が対応。 |
| 労働基準監督署 | 労働基準法違反(賃金不払い、不当な労働時間など)、労災申請 | 労働基準法違反の取り締まりや労災認定手続きを行う機関。 |
| 精神保健福祉センター | 精神的な健康に関する相談、医療機関の紹介など | 都道府県・政令指定都市に設置。専門家(精神保健福祉士など)が対応。無料相談可。 |
| よりそいホットライン | 様々な困難を抱える人からの相談全般 | NPOが運営。24時間、匿名で相談可。電話番号:0120-279-338(無料) |
| みんなの人権110番 | いじめ、ハラスメント、差別など人権問題全般 | 法務省が運営。電話番号:0570-003-110(全国共通ナビダイヤル) |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 精神的な健康に関する相談 | 都道府県・政令指定都市が運営。電話番号:0570-064-556(全国共通ナビダイヤル) |
これらの相談先は、それぞれ得意とする分野や役割が異なります。ご自身の状況に応じて、適切な相談先を選びましょう。いくつかの機関に相談することで、より多角的なアドバイスやサポートを得られることもあります。
特にパワハラが原因の場合は、まず会社のハラスメント相談窓口か、外部の労働組合や弁護士、総合労働相談コーナーに相談することをおすすめします。精神的な不調に関しては、医療機関での治療と並行して、精神保健福祉センターやかかりつけ医の紹介する相談機関を利用すると良いでしょう。
ストレス・パワハラ休職は必要な選択肢

ストレスやパワハラによって心身が疲弊し、働くことが困難になった場合、休職は決して逃げではありません。むしろ、心と体を回復させ、今後のより良いキャリアや生活を送るために必要な、そして勇気ある選択です。
休職を検討する際は、まず医療機関を受診し、医師の診断を受けることが重要です。診断書を会社に提出し、会社の休職制度に基づいて正式な手続きを進めます。休職期間中は、健康保険からの傷病手当金や、パワハラが原因で労災認定された場合の労災保険からの給付など、経済的な補償制度を活用できます。これらの制度を適切に利用するためにも、必要な手続きを把握し、不明な点は各機関に問い合わせることが大切です。
休職期間の長さは、病状の回復具合や会社の規定によって異なりますが、焦らず、医師の指示に従って療養に専念することが、その後の復職や新たな道に進むための基盤となります。休職期間の終盤には、復職か退職かという進路選択を迫られます。復職を希望する場合は、医師や産業医と連携しながら慎重に準備を進め、必要に応じて会社に働き方や配置についての配慮を求めましょう。パワハラが原因の場合は、元の部署に戻るのが困難なことを伝え、部署異動などを検討することも重要です。回復が思わしくない場合は、休職期間満了による退職となる可能性も考慮に入れ、今後の生活設計を立てる必要があります。
ストレスやパワハラの問題は、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが何よりも大切です。会社内の相談窓口、労働組合、弁護士、労働基準監督署、精神保健福祉センターなど、様々な相談先があります。それぞれの専門家から適切なアドバイスやサポートを得ることで、問題を解決し、安心して療養に専念できる環境を整えることができます。
この記事が、ストレスやパワハラによる休職を考えている方にとって、現状を整理し、具体的な行動を起こすための一助となれば幸いです。ご自身の心と体を第一に考え、適切なステップを踏んでいきましょう。
免責事項:
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の個人に対する医学的アドバイスや法的アドバイスを行うものではありません。個々の状況については、必ず医師、弁護士、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。制度の内容は変更される場合がありますので、最新の情報は関係省庁や加入している健康保険組合にご確認ください。
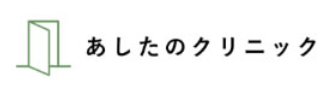

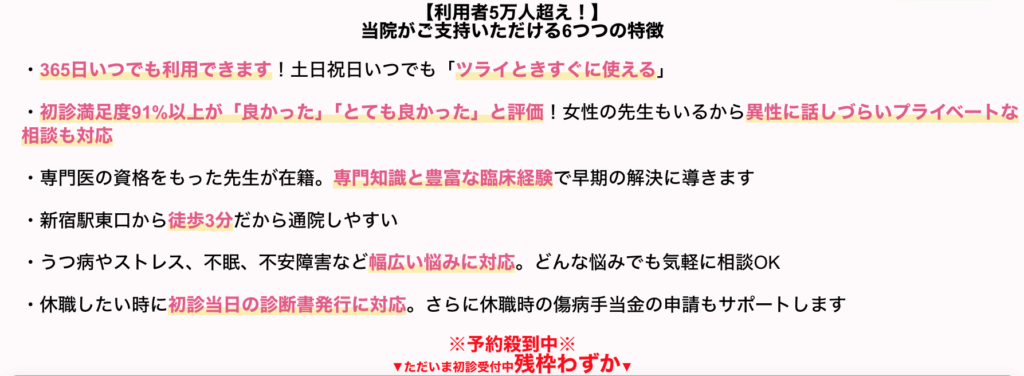



コメント