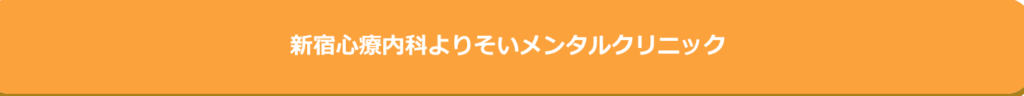
ストレスによる心身の不調が続き、「もしかしたら病院で相談した方がいいのかな」「休むために診断書が必要なのかな」と不安を感じている方もいるかもしれません。ストレスが原因で仕事や日常生活に支障が出ている場合、診断書が状況を改善するための一歩となることがあります。
この記事では、ストレスによる診断書の発行について、その必要性や取得方法、費用、そして取得後の手続きや注意点まで、あなたが抱えるかもしれない疑問に網羅的に答えます。どこで診断書をもらえるのか、即日発行は可能なのか、休職や退職にはどう影響するのかなど、具体的な情報を詳しく解説していきます。
もし今、ストレスによる不調に悩んでいるなら、ぜひこの記事を読んで、診断書に関する疑問を解消し、適切な行動を取るための参考にしてください。
過度なストレスで診断書はなぜ必要?役割と提出を求められるケース

ストレスで診断書が必要となる主な理由は、自身の病状や状況を、会社や学校、あるいは公的機関に対して証明し、理解や配慮を求めるためです。特に、外見からは分かりにくい精神的な不調の場合、診断書は非常に重要な役割を果たします。
具体的にどのような場合に提出を求められるのか、その役割とともに見ていきましょう。
会社に病状や必要な配慮を伝えるため
ストレスによる不調で、仕事に集中できない、ミスが増える、体調が優れないといった状況が続くと、業務への影響は避けられません。そのような場合、会社に対して自身の状態を正確に伝え、必要な配慮を求めるために診断書が役立ちます。
例えば、以下のようなケースで診断書を提出することで、会社側もあなたの状況を把握しやすくなり、適切な対応を検討するための根拠となります。厚生労働省の指針に基づくメンタルヘルス対策では、医師による面接指導や職場環境の改善などが推奨されており、診断書はその第一歩となり得ます。
- 体調不良による遅刻や欠勤が続く場合:正当な理由であることを証明し、懲戒などの不利益を回避するため。
- 業務内容や労働時間の調整を依頼したい場合:医師の意見として、具体的な配慮内容(例:残業を減らす、特定の業務から外れるなど)を会社に伝えるため。
- 定期的な通院が必要な場合:通院のための時間的な配慮や、フレックスタイム勤務などの制度利用を申請するため。
- ハラスメントや人間関係が原因である場合:具体的な原因を診断書に記載することは通常難しいですが、ストレスが原因で心身に不調をきたしている客観的な証拠として提示することで、会社が問題解決に動くきっかけとなることがあります。
診断書を提出することで、会社は従業員の健康状態を把握する義務に基づき、安全配慮義務の観点からも対応を検討することになります。もちろん、診断書を提出したからといって、全ての要望が叶えられるわけではありませんが、状況を改善するための第一歩となることは多いです。
休職・欠勤・異動の正当な理由として
ストレスによる不調が深刻で、現在の業務を続けることが困難になった場合、休職、長期の欠勤、あるいは異動(配置転換)を検討することになります。これらの措置は、従業員の心身の回復を図り、職場環境を調整するために非常に有効です。
これらの措置を会社に申請する際、診断書は病状の深刻さや、なぜその措置が必要なのかを示す客観的な証拠となります。
- 休職の申請: ストレス診断書に「〇ヶ月間の休養を要する」といった記載があることで、会社は休職の必要性を判断し、休職期間や復職に向けた計画を立てるための根拠とします。多くの会社では、休職規定に診断書の提出が定められています。
- 長期欠勤: 短期間の有給休暇では回復が見込めない場合や、有給休暇を使い切った場合など、診断書があれば病気療養のための長期欠勤が認められやすくなります。業務外疾病による休業時の賃金補償に関する法令解釈においても、医師の証明は重要な要素となります。
- 異動(配置転換): 現在の部署や業務がストレスの原因となっている場合、診断書に「現在の環境から離れて療養することが望ましい」「業務内容の変更が必要」といった医師の意見が記載されることで、会社が異動や配置転換を検討する際の重要な判断材料となります。
これらの人事上の措置は、会社にとって人員配置や業務への影響が大きいため、診断書という公式な書類に基づいた客観的な判断が求められることが一般的です。
1日休むだけでも診断書は必要?
「ストレスでどうしても今日は会社に行けない」「体調が悪くて1日だけ休みたい」という場合でも、診断書は必要なのでしょうか。これは、会社の就業規則によって異なります。
多くの会社では、数日程度の体調不良による欠勤に対しては、診断書の提出を必須とはしていません。口頭やメールでの連絡で認められることが一般的です。しかし、以下のような場合は、1日の欠勤であっても診断書の提出を求められることがあります。
- 頻繁に体調不良で休む場合: 欠勤が常態化していると見なされ、病状の確認や適切な対応を検討するために提出を求められることがあります。
- 重要な業務や会議を欠席する場合: 責任のある立場であったり、欠席の影響が大きい場合に、欠席の正当性を証明するために求められることがあります。
- 会社の規定で定められている場合: 短期間の欠勤でも診断書が必要と明確に規定されている会社もあります。
また、会社の規定に関わらず、診断書があれば、その日の欠勤が病気による正当な理由であることをより明確に証明できます。これにより、不要な誤解や不信感を生むリスクを減らすことができます。ただし、1日休むためだけに診断書を取得すると、費用(通常、保険適用外で数千円程度)がかかる点も考慮する必要があります。
結論として、1日の欠勤で診断書が必要かは会社の規定によりますが、取得することでより確実に病気療養として扱われる可能性が高まります。悩む場合は、まずは会社の担当部署(人事部など)に確認してみるのが良いでしょう。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

ストレス診断書のもらい方・取得方法

ストレスで診断書を取得するには、医師の診察を受け、その結果に基づいて医師に診断書の発行を依頼する必要があります。自己判断で診断書を作成したり、知人などに書いてもらったりすることはできません。診断書は、医師法に基づいて医師のみが発行できる公的な書類です。
ここでは、ストレス診断書をもらうための具体的なステップを解説します。
病院の心療内科・精神科を受診する
ストレスによる不調で診断書が必要だと感じたら、まずは病院を受診することが第一歩です。特に、精神的な不調や原因不明の身体症状がストレスによるものだと疑われる場合は、心療内科や精神科を受診するのが最も適切です。
- 心療内科: 主に、ストレスが原因で胃痛、頭痛、めまい、不眠などの身体症状が現れている場合を扱います。心と体の両面からアプローチします。
- 精神科: 気分の落ち込み、不安、焦燥感、幻覚・妄想など、精神症状が中心の場合を扱います。精神疾患全般を専門とします。
どちらを受診すべきか迷う場合は、かかりつけ医に相談したり、インターネットでクリニックの情報を調べたりして、自身の症状に合った診療科を選びましょう。初診の場合は予約が必要な医療機関が多いため、事前に電話やインターネットで確認し、予約を取るようにしてください。大学病院などの専門機関でも、適応障害やうつ病の診断プロセスについて情報提供している場合があります。例えば、大学病院の心療内科の案内などを参考に、受診先を検討することもできます。
診察時に医師に診断書発行を依頼する
受診した際は、現在の症状や困っていること、どのような状況で診断書が必要なのかを正直に医師に伝えます。診察の中で、医師があなたの症状が診断書の発行に値すると判断した場合に、診断書の発行が可能となります。
診断書の発行を希望する場合は、診察の際に医師に直接依頼します。「ストレスによる不調で、会社(または学校)に提出するための診断書が必要なのですが、発行していただけますでしょうか?」といったように、必要な診断書の種類と目的を具体的に伝えましょう。
医師は診察の結果、あなたの症状が診断基準を満たしているか、診断書を発行することが治療上適切かなどを判断します。すぐに診断名が確定せず、しばらく通院して経過を見ないと診断書が発行できないケースもあります。また、診断書に記載してほしい具体的な内容(例:休職が必要な期間、特定の業務からの除外など)がある場合は、相談してみると良いでしょう。ただし、最終的な記載内容は医師の医学的判断に基づきます。
症状や状況を正確に伝えるポイント
医師が適切な診断を行い、必要に応じて診断書を発行するためには、患者さん自身が自身の症状や状況を正確に伝えることが非常に重要です。診察時間が限られていることも多いので、事前に整理しておくとスムーズです。
以下は、診察時に医師に伝えるべきポイントです。
- 具体的な症状: いつからどのような症状(例:眠れない、食欲がない、常に疲れている、集中できない、イライラする、不安感が強い、動悸がする、頭痛がする、胃が痛いなど)が現れているか、具体的に説明します。症状の強さや頻度、一日の中で症状が変化するかなども伝えると良いでしょう。産業医向けに作成された精神疾患対応の実践ガイドなどでも、症状把握の重要性が強調されています。
- 症状によって困っていること: 症状によって、仕事や日常生活にどのような支障が出ているか(例:遅刻や欠勤が増えた、業務中にミスをするようになった、家事ができない、人と会うのが辛いなど)を具体的に伝えます。
- ストレスの原因: ストレスを感じる具体的な状況(例:職場の人間関係、業務量、長時間労働、家庭内の問題、将来への不安など)を伝えます。ただし、医師は医学的診断を行うため、特定の人物や状況を告発することが目的ではない点に留意しましょう。
- これまでの経緯: これまでにも似たような症状が出たことがあるか、過去に精神科や心療内科を受診したことがあるかなども伝えます。
- 現在の状況: 現在の仕事や学業の状況、家族構成や生活環境なども、医師が全体像を把握する上で役立ちます。
- 診断書が必要な理由と目的: 会社に提出するため、休職の申請のため、傷病手当金の申請のためなど、なぜ診断書が必要なのか、何のために使うのかを明確に伝えます。休職が必要な期間や、希望する配慮の内容があれば相談しましょう。
これらの情報を正直かつ具体的に伝えることで、医師はあなたの状況を正確に理解し、適切な診断と治療方針を立てることができます。それが、必要に応じた診断書の発行につながります。
過度なストレスで診断書はどこでもらえる?適切な受診先

ストレスで診断書が必要になった場合、どこで診察を受ければ良いのか悩む方もいるかもしれません。ストレスによる不調は精神的なものだけでなく、身体症状として現れることも多いため、いくつかの選択肢が考えられます。しかし、ストレス診断書の取得という目的を考えると、適切な受診先を選ぶことが重要です。
主に、心療内科や精神科クリニック、総合病院の精神科・心療内科が専門的な診断を受けられる場所となります。場合によっては、かかりつけ医でも対応可能なことがあります。
心療内科・精神科クリニック
ストレスによる不調が精神的な症状(気分の落ち込み、不安、不眠など)や、それに伴う身体症状(頭痛、胃痛など)として現れている場合、心療内科クリニックや精神科クリニックを受診するのが最も一般的で適切な選択肢です。
メリット
- 専門性が高い: ストレス関連疾患や精神疾患の診断・治療を専門としており、経験豊富な医師が多いです。産業医向けの実践ガイドなどでも、専門医による診断の重要性が述べられています。
- 通いやすい: 比較的数が多く、自宅や職場から近い場所で見つけやすい場合があります。
- 予約が取りやすい: 総合病院に比べて予約が取りやすく、比較的スムーズに診察を受けられることがあります。(ただし、人気のクリニックは予約が取りにくい場合もあります)
- 待ち時間が短い: 予約していれば、総合病院に比べて待ち時間が短い傾向があります。
デメリット
- 専門領域が限られる: 精神科単科や心療内科単科の場合、身体的な疾患が複雑に絡み合っている場合に、他の診療科との連携が難しい場合があります。
- 緊急対応に限りがある: 重篤な状態になった場合の入院対応などは難しく、総合病院への紹介となる場合があります。
多くのストレス関連疾患の診断や、休職・復職のための診断書発行は、心療内科や精神科クリニックで十分対応可能です。まずは地域のクリニックを探してみることをおすすめします。クリニックのウェブサイトなどで、診療内容や予約方法、診断書発行について確認しておくと良いでしょう。
総合病院の精神科・心療内科
ストレスによる不調が重篤である、身体的な合併症がある、他の診療科での治療も必要であるといった複雑なケースの場合は、総合病院の精神科や心療内科を受診するという選択肢もあります。大学病院の心療内科など、大規模な医療機関では、より複雑な症例に対応できる体制が整っています。
メリット
- 幅広い疾患に対応: 重篤な精神疾患や、身体的な疾患と精神的な不調が合併している場合など、より複雑な病態に対応できます。
- 他の診療科との連携: 総合病院内には様々な診療科があるため、必要に応じて他の専門医と連携して治療を進めることができます。
- 入院対応が可能: 必要に応じて入院による治療やケアを受けることができます。
デメリット
- 予約が取りにくい: 初診の予約が数週間先になるなど、比較的予約が取りにくい傾向があります。
- 待ち時間が長い: 予約していても、診察まで長時間待つことがあります。
- アクセス: 地域の基幹病院である場合が多く、自宅や職場からのアクセスが限られる場合があります。
- 紹介状が必要な場合: 大病院では、他の医療機関からの紹介状がないと受診できない場合や、費用が加算される場合があります。
症状が重い場合や、複数の身体症状があって診断が難しい場合は、総合病院の精神科・心療内科が良い選択肢となります。まずはかかりつけ医に相談し、紹介状を書いてもらうとスムーズです。
その他のかかりつけ医で可能な場合
ストレスによる不調が、主に身体症状(頭痛、胃痛、めまいなど)として現れており、普段から相談しているかかりつけ医(内科医など)がいる場合は、まずかかりつけ医に相談してみることも可能です。
かかりつけ医はあなたのこれまでの病歴や健康状態を把握しているため、相談しやすいというメリットがあります。ストレスによる身体症状である可能性を疑い、必要に応じて診断書を発行してくれる場合もあります。
ただし、かかりつけ医が精神疾患やストレス関連疾患の診断・治療にどの程度習熟しているかは医師によって異なります。
- 診断書発行の可能性: 診断書の発行が可能かどうか、記載内容をどこまで詳しく書けるかは、医師の専門性や判断によります。精神科や心療内科医ほど、精神的な不調に関する診断書の発行に慣れていない可能性もあります。
- 専門医への紹介: 症状が精神的な側面に強く関連している、あるいは診断が難しいと判断された場合は、専門である心療内科や精神科への受診を勧められることが一般的です。
まずは身近なかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらう、という流れも良いでしょう。ただし、最初から精神的な不調を証明する診断書が必要だと分かっている場合は、最初から心療内科や精神科を受診するのが最も効率的です。
受診先の選び方まとめ
| 受診先 | こんな人におすすめ | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 心療内科・精神科クリニック | ストレスによる精神症状・身体症状が中心で、比較的症状が安定している、通いやすさを重視する | 専門性が高い、通いやすい、比較的予約が取りやすい、待ち時間が短い傾向 | 専門領域が限られる、緊急対応に限りがある |
| 総合病院の精神科・心療内科 | 症状が重篤、他の身体疾患がある、入院が必要な可能性がある、他の診療科との連携が必要 | 幅広い疾患に対応、他科との連携、入院対応が可能 | 予約が取りにくい、待ち時間が長い、アクセスが限られる、紹介状が必要な場合がある |
| その他のかかりつけ医 | ストレスによる身体症状が中心、普段から通っていて相談しやすい、まずは身近な医師に相談したい | 相談しやすい、これまでの病歴を把握している | 精神疾患の専門性は高くない場合がある、診断書発行に限界がある場合がある |
自身の症状や状況、優先したい点(専門性、通いやすさ、待ち時間など)を考慮して、適切な受診先を選びましょう。
ストレスで診断書は即日発行できる?

ストレスによる不調が辛く、すぐにでも会社や学校を休むために診断書が必要な場合、「受診したその日に診断書をもらえるのだろうか?」と考える方も多いでしょう。結論から言うと、ストレス診断書の即日発行は難しいケースが多いです。
即日発行が難しい理由
ストレス関連疾患や精神疾患の診断は、内科的な疾患のように血液検査や画像検査だけで確定できるものではありません。患者さんの訴え、これまでの経過、診察時の様子などを総合的に判断して行われます。大学病院の心療内科の案内でも、診断プロセスには複数のステップが必要であることが示唆されています。
初診の段階では、医師は患者さんの状態を十分に把握できていないことがほとんどです。正確な診断をするためには、症状の経過を観察したり、いくつかの検査(心理検査など)を行ったり、複数の診察を通じて患者さんの状態をより深く理解する必要があります。
そのため、特に初診で初めて受診する場合、医師は慎重な判断を要するため、その場で診断書の発行に至らないケースが多いのです。
- 診断の確定に時間がかかる: ストレスによる不調か、他の病気か、あるいはどのような疾患(適応障害、うつ病、不安障害など)なのかを診断するには、ある程度の時間と情報収集が必要です。
- 経過観察が必要: 症状が一時的なものか、継続的なものか、治療によってどのように変化するかなどを判断するため、数回通院して経過を見ないと診断書が発行できない場合があります。
- 医師の判断: 診断書を発行することが患者さんにとって最善の治療方針であるかどうかも、医師は考慮します。単に休むためだけに診断書を求めるのではなく、病状を改善するためのステップとして診断書が必要であると医師が判断した場合に発行されます。
これらの理由から、診察を受けたその日に「はい、どうぞ」と診断書がすぐに発行されることは、一般的なケースでは少ないと考えておいた方が良いでしょう。
当日発行に対応しているクリニックの探し方
即日発行が難しいとはいえ、全く不可能というわけではありません。以下のようなケースでは、当日発行に対応してもらえる可能性が高まります。
- すでに通院している場合: 以前からその医療機関に通院しており、医師があなたの病状や経過を十分に把握している場合は、病状が悪化した場合などに診断書を当日発行してもらえることがあります。
- 緊急性の高い症状: ストレスによる症状が非常に重く、すぐにでも休養が必要であると医師が判断した場合など、緊急性の高いケースでは配慮してもらえる可能性もあります。
- クリニックの方針: 一部のクリニックでは、初診の場合でも、問診や診察の結果、診断名や必要な療養期間がおおむね確定できると判断した場合に、当日診断書を発行しているところもあります。
当日発行に対応しているクリニックを探す場合は、以下の方法を試してみてください。
- クリニックのウェブサイトを確認: クリニックのウェブサイトの「診断書について」「Q&A」などのページに、診断書の即日発行に関する情報が記載されている場合があります。「即日発行可能」と明記しているクリニックもあれば、「原則として次回以降の診察時に発行」などと記載されている場合もあります。
- 電話で問い合わせる: 受診を検討しているクリニックに直接電話で問い合わせてみるのが確実です。「ストレスによる不調で、すぐにでも会社に提出する診断書が必要なのですが、初診でも当日発行は可能でしょうか?」といったように具体的に質問します。ただし、電話での回答はあくまで可能性であり、最終的な判断は診察後の医師が行うことを理解しておきましょう。
ただし、当日発行が可能だからといって、十分な診察や判断が行われないまま診断書が発行されるわけではありません。あくまで医師が医学的に適切であると判断した場合に限られます。安易に「即日発行」だけを目的とするのではなく、自身の症状をしっかりと伝え、医師の診断に基づいて診断書を取得することが最も重要です。
ストレスで診断書をもらえないケースとその理由

ストレスによる不調を感じて医療機関を受診しても、必ずしも診断書を発行してもらえるとは限りません。医師が診断書の発行を困難と判断するケースや、診断基準を満たさない場合があります。
診断基準を満たさない場合
診断書は、医師が患者さんの状態を医学的な根拠に基づいて診断し、証明する書類です。そのため、医師が診察した結果、特定の病気として診断できる基準を満たさない場合、診断書は発行できません。産業医向けの実践ガイドなどでも、診断基準に基づいた判断の重要性が強調されています。
例えば、以下のようなケースです。
- 一時的なストレス反応: 新しい環境や出来事に対して一時的にストレスを感じているだけで、数日経てば回復が見込まれるような軽微な症状の場合。医学的な診断を要するレベルではないと判断されることがあります。
- 医学的な根拠に乏しい場合: 患者さんが「ストレスが原因だと思う」と訴えても、客観的な身体症状や精神症状が見られず、医師が医学的に診断を下す根拠に乏しい場合。
- 他の疾患の可能性: 症状がストレスによるものではなく、他の身体疾患や精神疾患によるものであると医師が判断した場合、ストレス診断書としては発行されません。その場合は、別の診断名で診断書が発行されるか、専門医への紹介となります。
医師は、問診や診察、必要に応じて検査などを行い、様々な可能性を考慮しながら診断を行います。診断基準を満たさないと判断された場合、診断書を発行することは医師法に反する行為となるため、発行を断られます。
医師が発行を困難と判断した場合
診断基準を満たす病状であっても、医師が診断書の発行を困難、または不適切と判断するケースもあります。
- 診断書発行が治療上不適切: 例えば、患者さんが診断書を悪用する可能性があると医師が判断した場合や、診断書を発行することが患者さんの自立を妨げ、治療の妨げになると判断した場合など。医師は、患者さんの健康と回復を第一に考えて判断します。
- 患者さんの訴えと診察結果の乖離: 患者さんが訴える症状と、診察時の様子や客観的な検査結果に大きな乖離がある場合。医師は患者さんの訴えを尊重しつつも、医学的な視点から総合的に判断します。
- 症状の把握が不十分: 特に初診の場合など、一度の診察では病状の全体像や経過を十分に把握できないことがあります。正確な診断や、必要な療養期間などの記載が難しいと医師が判断した場合、診断書の発行は保留となり、数回通院して経過を見ることが求められる場合があります。
- 医師の専門外: かかりつけ医など、精神科や心療内科を専門としない医師に診断書を依頼した場合、精神的な不調に関する詳細な診断書の発行は難しいと判断されることがあります。その場合は、専門医への受診を勧められます。
診断書の発行は、医師の裁量に委ねられています。医師は患者さんの訴えを聞き、医学的な知識と経験に基づいて総合的に判断します。診断書が必要な状況を正確に伝え、医師との信頼関係を築くことが重要です。もし診断書の発行を断られた場合は、その理由を医師に確認し、今後の治療方針についてよく話し合いましょう。
ストレスでもらえる診断書に記載される主な内容

診断書には、医師が診断した患者さんの状態に関する情報が記載されます。記載される内容は診断書の種類や提出先(会社、学校、公的機関など)によって多少異なりますが、一般的に以下のような項目が含まれます。厚生労働省が定める診断書標準様式を参照すると、より具体的な記載項目を確認できます。
診断名(適応障害など)と症状
診断書には、医師が医学的に診断した病名が記載されます。ストレスに関連する代表的な診断名としては、以下のようなものがあります。大学病院の心療内科の案内でも、これらの疾患の診断について触れられています。
- 適応障害: ストレスの原因が明確で、そのストレス要因に反応して心身の不調(気分の落ち込み、不安、不眠、身体症状など)が現れ、社会生活や学業・仕事に支障が出ている状態。ストレスの原因がなくなると症状が軽減するのが特徴です。
- うつ病: 気分の落ち込みや意欲の低下が続き、不眠、食欲不振、疲労感などの身体症状を伴い、日常生活に大きな支障が出ている状態。適応障害よりも症状が重く、ストレスの原因がなくなっても回復に時間がかかることが多いです。
- 不安障害: 過度な不安や心配が続き、落ち着かない、動悸、呼吸困難、めまいなどの身体症状を伴う状態。パニック障害や社交不安障害なども含まれます。
これらの診断名のほか、「自律神経失調症」といった診断名が記載されることもあります。
診断名に加えて、現在の具体的な症状(例:不眠、食欲不振、全身倦怠感、集中力低下、不安焦燥感など)も記載されます。これにより、診断名だけでなく、患者さんが具体的にどのような状態にあるのかを提出先に伝えることができます。
必要な療養期間や治療内容
診断書には、医師が医学的に判断した、病状回復のために必要な療養期間が記載されます。
- 療養期間: 「〇週間(または〇ヶ月間)の休養を要する」「〇年〇月〇日まで自宅療養を要する」といった形で具体的に記載されます。この期間は、病状の程度や回復の見込みに基づいて医師が判断します。会社の休職制度などを利用する場合、この記載期間が重要な目安となります。
- 治療内容: 現在行っている治療(例:自宅療養、薬物療法、精神療法など)や、今後行う予定の治療について記載されることがあります。
これらの記載は、提出先(会社など)が患者さんの回復計画を立てたり、復職に向けた準備を進めたりする上で参考となります。
就労に関する医師の意見
診断書には、患者さんの現在の病状を踏まえ、就労について医師がどのような意見を持っているかが記載されることがあります。厚生労働省が定める診断書標準様式でも、職場復帰に必要な医学的意見を記載する欄が設けられています。
- 休職の必要性: 「当面の間、休職を要する」「就労は困難であり、休養が必要」といった、休職の必要性について明確に記載されます。
- 就労制限: 「軽作業であれば可能」「時間短縮勤務が望ましい」「特定の業務からの離脱が望ましい」など、就労に関する具体的な制限や配慮事項について記載されることがあります。これは、復職を目指す段階や、病状が比較的軽い場合に、会社に配慮を求める際の根拠となります。
- 復職の可能性: 「病状の改善に伴い、復職が可能となる見込み」「段階的な復職が望ましい」など、復職に向けた見通しについて触れられることもあります。厚生労働省の指針でも、休職・復職支援のプロセスが示されています。
これらの医師の意見は、会社が従業員の就労継続の可否や、復職支援、配置転換などを検討する際に最も重要視する部分の一つです。
診断書に記載される内容は、患者さんの病状や提出先の要望、そして医師の判断によって異なります。どのような内容を記載してほしいか希望があれば、診察時に医師に相談してみましょう。ただし、最終的な記載内容は医師の医学的判断に基づきます。
診断書に記載される主な内容まとめ
| 項目 | 具体的な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 診断名 | 適応障害、うつ病、不安障害、自律神経失調症など | 病状を医学的に特定し、証明する |
| 症状 | 不眠、食欲不振、疲労感、集中力低下、不安感、身体症状など具体的な状態 | 診断名だけでなく、患者さんの具体的な状態を伝える |
| 必要な療養期間 | 〇週間/ヶ月間の休養を要する、〇年〇月〇日まで自宅療養を要するなど具体期間 | 病状回復のために必要な期間を示す、会社の休職期間の目安となる |
| 治療内容 | 自宅療養、薬物療法、精神療法など | 現在の治療状況を伝える、今後の治療方針を示す |
| 就労に関する意見 | 休職の必要性、就労制限(軽作業のみ可、時間短縮勤務など)、復職の可能性など医師の意見 | 就労継続の可否、必要な配慮、復職支援などを検討する根拠となる |
これらの記載内容を通じて、診断書は患者さんの健康状態を客観的に伝え、必要なサポートや手続きを進めるための重要な役割を果たします。
ストレス診断書の発行にかかる費用

ストレス診断書の発行には、費用がかかります。これは、診断書の発行が健康保険の適用外となる自費診療扱いだからです。費用は医療機関によって異なりますが、一般的な相場があります。
診断書の種類による一般的な料金
診断書には、いくつかの種類があります。主に、特定の目的のために医療機関が発行する文書全般を指しますが、ストレス診断書として一般的に会社や学校に提出するものは、以下のような種類に分類されることがあります。
- 一般的な診断書: 病名、症状、療養期間、就労に関する意見などが簡潔に記載されたもの。最も一般的な診断書です。
- 傷病手当金申請用の診断書(意見書): 健康保険から支給される傷病手当金を申請する際に必要となる診断書。医師が労務不能である期間やその原因などを記載する「意見書」の形式を取ることが多いです。申請書類の様式が指定されている場合があります。傷病手当金に関する厚生労働省の見解でも、診断書(意見書)の必要性に触れられています。
- その他の詳細な診断書: 精神障害者保健福祉手帳の申請用など、より詳細な病歴や症状の経過、能力に関する評価などが記載されるもの。
これらの診断書の種類によって、発行にかかる費用が異なるのが一般的です。
一般的な診断書費用の相場
- 一般的な診断書: 3,000円~10,000円程度
- 傷病手当金申請用の診断書(意見書): 3,000円~10,000円程度(傷病手当金の申請書に医師が記載する形式の場合、文書料として請求されます)
- 精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書: 5,000円~15,000円程度
ただし、これはあくまで目安であり、医療機関(クリニックか総合病院か、規模など)や地域によって料金設定は異なります。受診する際に、診断書発行にかかる費用を事前に確認しておくことをおすすめします。医療機関の受付やウェブサイトに料金表が掲示されている場合が多いです。
保険適用について
先述の通り、診断書の発行費用は、原則として健康保険の適用外となります。つまり、全額自己負担となります。
ただし、医療機関によっては、診断書発行のための診察費用と診断書費用をまとめて請求する場合と、診察費用は保険適用(3割負担など)で、診断書費用のみ自費として請求する場合があります。
例えば、診察を受けて診断書を発行してもらった場合、
- 診察費用(保険適用):数千円(保険証による負担額)
- 診断書費用(自費):3,000円~10,000円程度
合計で数千円から1万円以上の費用がかかることになります。
傷病手当金の申請用の診断書も、申請書に医師の意見を記載してもらう部分が文書料として請求されるため、これも通常は保険適用外です。業務外疾病による休業時の賃金補償に関する法令解釈においても、文書料は保険給付の対象外となることが示唆されています。
診断書が必要な場合は、費用がかかることを念頭に置いておきましょう。ただし、病状の回復や、休職・傷病手当金の受給など、診断書によって得られるメリットを考慮すれば、必要な費用であると言えます。
診断書の費用について不明な点があれば、受診時に遠慮なく医療機関のスタッフに尋ねてみましょう。
診断書提出後の流れと注意点

診断書を取得したら、次に必要となるのは会社や学校、あるいは公的機関への提出です。診断書を提出した後、どのような流れになるのか、またどのような点に注意すべきかを知っておきましょう。特に、休職や退職を検討している場合は、診断書の活用方法や手続きが重要になります。
会社への提出方法
会社に診断書を提出する場合、提出先は一般的に人事部や直属の上司、あるいは産業医など、会社の規定によって異なります。厚生労働省の指針でも、産業医や担当管理職との連携の重要性が述べられています。
- 誰に提出するか確認する: まずは会社の就業規則や社内規定を確認するか、人事部の担当者に問い合わせて、診断書の正式な提出先を確認しましょう。上司に直接手渡す場合と、人事部に郵送またはメールで提出する場合などがあります。
- 提出方法: 診断書は重要な書類なので、コピーを取ってから原本を提出することをおすすめします。万が一、紛失した場合の控えとなります。メールで提出する場合は、スキャンしたPDFファイルなどを送付します。
- 提出のタイミング: 病状が悪化し、休職や長期欠勤が必要になった際に、できるだけ早く提出するのが望ましいです。会社もあなたの状況を把握し、必要な手続きを進めるための準備ができます。
- 口頭での補足: 診断書は医学的な内容が記載されているため、会社側が内容を完全に理解できない可能性もあります。必要であれば、提出時に自身の口から現在の状況や診断書が必要になった背景などを簡潔に補足説明すると、より理解が得られやすくなります。ただし、病状の詳細を無理に話す必要はありません。
診断書を提出することで、会社はあなたの病状を把握し、安全配慮義務に基づいた対応を検討します。これにより、休職、配置転換、業務内容の変更などの措置が検討され、あなたの回復に向けたサポート体制が整えられます。
休職する場合の手続き(傷病手当金など)
ストレス診断書を提出し、会社に休職が認められた場合、いくつかの手続きが必要になります。
- 休職期間の決定: 診断書に記載された療養期間や、会社の休職規定に基づいて、具体的な休職期間が決定されます。まずは会社の休職規定を確認しましょう。厚生労働省の指針でも、休職期間の決定は重要なステップとされています。
- 休職中の給与: 会社の規定によりますが、休職中は給与が支給されない、あるいは減額されることが多いです。給与の有無や、支給される場合の金額などを確認しましょう。
- 社会保険料: 休職中も健康保険や厚生年金保険などの社会保険料は原則として発生します。会社によっては、休職中の社会保険料の支払いを一時的に猶予したり、会社が立て替えてくれたりする制度がある場合もありますので、確認が必要です。
- 傷病手当金の申請: 休職中に給与が支給されない場合や減額される場合、健康保険から傷病手当金が支給される可能性があります。これは、病気やケガで働けない場合に、生活保障として支給される公的な制度です。業務外疾病による休業時の賃金補償について解説した厚生労働省の資料でも、傷病手当金はこのケースに該当することが示されています。
傷病手当金について
- 受給要件:
- 業務外の事由による病気やケガであること。
- 仕事に就くことができないこと(労務不能であること)。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと(待期期間)。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと。
- 支給額: 概ね、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2に相当する額(日割り)。
- 支給期間: 支給開始日から最長1年6ヶ月。
- 申請方法: 加入している健康保険組合や協会けんぽに申請書類を提出します。申請書類には、医師の意見書(診断書)や、会社の証明、本人の記入欄があります。厚生労働省が定める診断書標準様式とは別に、傷病手当金申請用の専用様式があるのが一般的です。書類は、健康保険のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。
傷病手当金の申請は、休職中の重要な経済的支えとなります。診断書を取得する際に、傷病手当金申請用の意見書が必要であることを医師に伝え、記載してもらうようにしましょう。申請手続きは自分で行う必要がありますが、会社の担当部署(人事部など)がサポートしてくれる場合もあります。
退職する場合の注意点
ストレスによる不調が深刻で、休職しても回復が見込めない、あるいは現在の会社に戻ることに強い抵抗があるといった理由から、退職を選択する場合もあるかもしれません。ストレス診断書は、退職の際にもいくつかの点で役立つ可能性があります。
- 退職理由の説明: 会社に対して、体調不良による退職であることを説明する際に、診断書が客観的な証拠となります。これにより、会社側も理解を示しやすくなります。
- 失業保険(雇用保険の基本手当)の受給: 自己都合退職の場合、通常は7日間の待期期間に加え、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります。しかし、体調不良(病気やケガ)による退職が正当な理由であると認められた場合、特定理由離職者として、給付制限期間なしで失業保険を受給できる場合があります。この際、診断書が病状を証明する重要な書類となります。業務外疾病による休業が原因で退職した場合などが、特定理由離職者に該当しうるケースです。
- 傷病手当金の継続受給: 雇用保険の被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日の前日までに傷病手当金を受給している、または受給できる状態であった場合、一定の要件を満たせば退職後も傷病手当金を継続して受給できることがあります。この場合も、診断書は継続受給の要件を満たしていることを証明するために必要です。
退職を選択する場合でも、診断書があることで、円滑な退職手続きや、退職後の経済的な保障(失業保険や傷病手当金)を受ける上で有利になることがあります。退職を検討している場合は、診断書を持参してハローワークや健康保険組合に相談してみると良いでしょう。
診断書提出後の流れと注意点まとめ
| 提出先・目的 | 流れ・ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社への提出 | 提出先(人事部、上司、産業医など)を確認。コピーを取って原本を提出。必要に応じ口頭で補足。 | 会社の規定に従う。提出先や方法を間違えないようにする。病状をどこまで開示するかは自身の判断だが、診断書の内容で十分に伝わる。 |
| 休職手続き | 診断書に基づき休職期間決定。会社の休職規定、給与、社会保険料を確認。傷病手当金の受給申請を検討。 | 会社の休職規定を必ず確認する。傷病手当金の申請は自分で行う必要がある(会社のサポートを受けられる場合も)。診断書に傷病手当金申請用の記載が必要な場合がある。 |
| 退職する場合 | 退職理由の説明、失業保険の給付制限解除、傷病手当金の継続受給などに診断書が役立つ。 | 自己都合退職の場合でも診断書があれば正当な理由として認められやすい。ハローワークや健康保険組合に相談する際に診断書を持参すると良い。退職前にこれらの制度について確認しておくことが重要。 |
診断書を適切に活用することで、ストレスによる不調から回復するための時間や、退職後の生活を立て直すための支援を受けやすくなります。
診断書を取得するデメリット

診断書を取得することは、心身の回復や公的な手続きを進める上で多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。診断書を取得するかどうかを判断する際には、これらのデメリットも考慮に入れる必要があります。
会社に病状が知られること
ストレス診断書を会社に提出するということは、あなたの病状や精神的な不調がある程度、会社に知られることを意味します。厚生労働省の指針でも、病状に関する情報は慎重に取り扱うよう求められていますが、完全に秘匿できるわけではありません。
- 評価への影響: 診断書を提出し、休職や業務の軽減措置を取ることで、一時的に仕事のパフォーマンスが低下したり、責任のある業務から外れたりする可能性があります。これにより、今後の人事評価やキャリアパスに影響が出るのではないか、と懸念する人もいるかもしれません。
- 人間関係の変化: 同僚や上司に病状を知られることで、接し方が変わったり、腫れ物に触るような態度を取られたりする可能性もゼロではありません。また、病状について詮索されることにストレスを感じる人もいるでしょう。
- 復職後の懸念: 休職から復職した場合に、「また体調を崩すのではないか」と会社や周囲から思われ、重要な業務を任されにくくなるのではないか、といった不安を感じる人もいます。産業医向けの実践ガイドでも、復職支援の課題としてこれらの点が挙げられることがあります。
もちろん、会社には従業員の健康を守る義務があり、診断書に基づいた適切な対応が求められます。病状を隠して働き続けることで、症状が悪化し、かえって長期的なキャリアに悪影響を及ぼす可能性もあります。会社の規模や文化、上司や同僚の理解度によって、これらの影響は大きく異なります。診断書提出のメリットとデメリットを比較検討し、自身の状況にとって何が最善かを考えることが重要です。
転職活動への影響
ストレスによる不調で診断書を取得し、休職や退職をした場合、その経歴が転職活動に影響するのではないか、と心配する人も多いです。
- 職務経歴の説明: 履歴書や職務経歴書には、休職期間や退職理由について記載または説明を求められる場合があります。その際に、「体調不良による休職・退職」であることを正直に伝える必要があるか、どの程度詳しく話すべきか、といった点で悩むかもしれません。
- 採用側の懸念: 採用する企業側は、応募者が再び体調を崩さないか、安定して勤務できるか、といった点を懸念する可能性があります。特に、精神的な疾患に対する理解が十分でない企業や、即戦力を求めている企業では、不利になる可能性があると言われています。
ただし、全ての転職活動において不利になるわけではありません。
- 正直に伝えるメリット: 体調不良の経験から学び、どのように対処するようになったか、現在は回復して安定していることなどを正直に伝えることで、自己管理能力や困難を乗り越える力として評価される場合もあります。
- 企業の理解: 従業員の健康を重視し、多様な働き方を受け入れる企業も増えています。そのような企業であれば、過去の病歴よりも、現在のスキルや意欲を評価してくれるでしょう。
- 回復していることの証明: 診断書は過去の病状を証明するものですが、完治または寛解している場合は、現在の健康状態について医師に意見書などを記載してもらうことで、採用側の懸念を払拭できる可能性もあります。
転職活動への影響を最小限にするためには、自身の病状や回復状況を正確に把握し、採用担当者にどのように伝えるかを事前に準備しておくことが重要です。また、健康経営に取り組む企業や、精神疾患への理解がある企業を選ぶことも一つの方法です。
診断書を取得することによるデメリットは確かに存在しますが、それは主に病状を隠して無理を続けることによって生じるリスクを回避するためのトレードオフとも言えます。自身の健康を最優先に考え、必要なサポートを受けるための一歩として、診断書の取得を検討することが大切です。
ストレスによる不調を感じたら、まずは専門家へ相談を

ストレスによる心身の不調は、放置すると症状が悪化し、回復に時間がかかるだけでなく、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼす可能性があります。「これくらい大丈夫」「気のせいだろう」と我慢せず、少しでも辛いと感じたら、早めに専門家に相談することが非常に重要です。
診断書の取得を検討する以前に、まずはご自身の体調と向き合い、専門的なアドバイスを求めることが最優先です。
- 医療機関への受診: ストレスによる身体症状や精神症状が現れている場合は、心療内科や精神科、またはかかりつけ医を受診しましょう。医師はあなたの症状を医学的な観点から診断し、適切な治療法(休養、薬物療法、カウンセリングなど)を提案してくれます。大学病院の心療内科の案内など、専門的な医療機関の情報も参考になります。早期に受診することで、病状が軽いうちに回復できる可能性が高まります。診断書が必要かどうかも、医師に相談することができます。
- 職場の相談窓口: 多くの企業には、産業医や保健師による健康相談窓口、あるいは外部のEAP(従業員支援プログラム)などの相談窓口が設置されています。厚生労働省の指針でも、事業場における心の健康づくりの重要性が強調されています。これらの窓口では、プライバシーが守られた環境で、ストレスに関する相談やアドバイスを受けることができます。必要に応じて、医療機関への受診を勧められたり、会社との間の調整をサポートしてもらえたりすることもあります。
- 公的な相談窓口: 各自治体や精神保健福祉センターなどでも、精神的な健康に関する相談を受け付けています。専門の相談員が対応してくれるため、誰に相談すれば良いか分からない、という場合にも利用しやすいでしょう。
- 家族や信頼できる友人: 身近な人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。ただし、専門的なアドバイスが必要な場合は、やはり医療機関や専門の相談窓口を利用することをおすすめします。
ストレスは誰にでも起こりうるものであり、それによって体調を崩すことは決して珍しいことではありません。一人で抱え込まず、適切なサポートを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。
ストレス診断書は、あなたの病状を証明し、必要なサポートや制度を利用するための一つの手段です。しかし、診断書を取得すること自体が目的ではなく、ご自身の健康を回復させ、より良い状態を取り戻すことが最終的な目標のはずです。
もし今、ストレスによる不調に悩んでいるなら、この記事で得た情報を参考に、まずは勇気を出して専門家への相談の第一歩を踏み出してみてください。それが、あなたの心身の健康を取り戻すための、最も確実な方法です。
免責事項:本記事は、ストレス診断書に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の疾患の診断や治療を推奨するものではありません。個々の症状や状況については、必ず医師などの専門家にご相談ください。また、診断書の発行可否や記載内容、費用、および各種制度(休職、傷病手当金、失業保険など)の適用については、医師の判断、所属する会社や学校の規定、関連法規などによって異なります。最新の情報や詳細については、関係機関に直接ご確認ください。
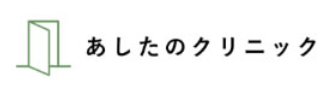

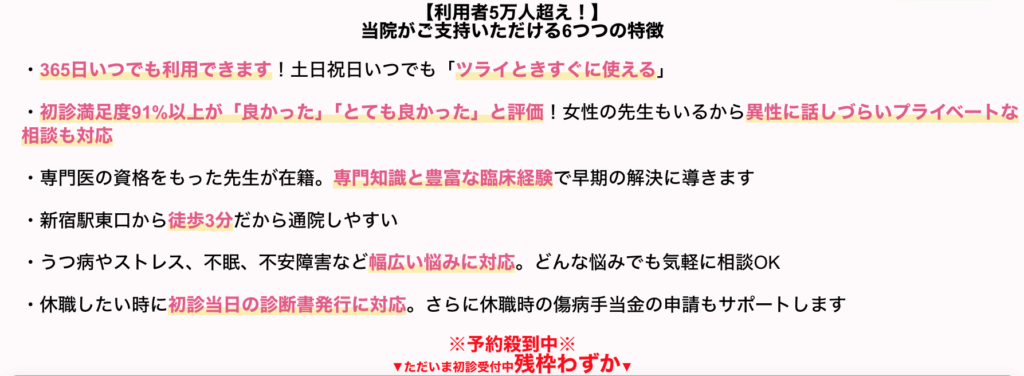



コメント