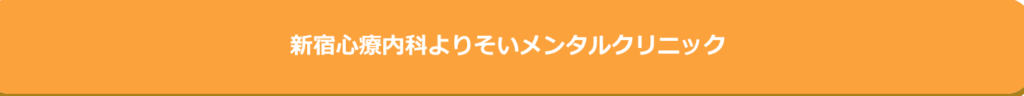
うつ病と診断され、働くことが難しくなったとき、経済的な不安はつきものです。「このまま収入が途絶えてしまったらどうしよう…」と一人で抱え込んでいませんか?そんな時、心強い支えとなる可能性があるのが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。
うつ病などの精神疾患も、条件を満たせば傷病手当金の支給対象となります。この記事では、うつ病で傷病手当金を受け取るための条件や申請方法、計算方法、支給期間、そして申請でつまずきやすいポイントやよくある疑問まで、うつ病と傷病手当金に関する情報を網羅的に解説します。
この記事を読めば、傷病手当金の制度を正しく理解し、安心して申請手続きを進めるための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
経済的な不安を少しでも軽減し、治療に専念するための一歩を踏み出しましょう。
傷病手当金とは?うつ病でも対象になる?

傷病手当金は、病気やけがによって会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために健康保険から支給される給付金です。
これは、労働者のセーフティネットの一つとして重要な役割を果たしています。
傷病手当金の制度概要と目的
傷病手当金は、健康保険法に基づいて設けられている公的な医療保険制度からの給付です。
その主な目的は、被保険者が業務外の理由による病気やけがで働くことができなくなり、収入が途絶えた際に、本人やその家族の生活を経済的に支えることにあります。
これにより、安心して療養に専念できる環境を整え、早期の社会復帰を支援することを目指しています。
対象となるのは、会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保など)の被保険者です。
国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんが、自治体によっては独自の傷病手当金制度を設けている場合もあります。
傷病手当金の制度概要については、協会けんぽのウェブサイトなども参考になります。
うつ病が傷病手当金の支給対象となる理由
「うつ病」は、精神疾患の一つであり、心身の機能に影響を及ぼし、就労が困難になる病気です。
傷病手当金は、病気やけがの種類を限定しているわけではなく、「療養のため働くことができない状態」であれば支給対象となります。
うつ病の場合、以下のような症状によって仕事に支障をきたすことがあります。
- 意欲・集中力の低下: 仕事への取り組む気力が起きない、物事に集中できない、判断力が鈍るといった症状により、業務遂行能力が著しく低下します。
- 倦怠感・疲労感: 体がだるく、疲れやすい状態が続くため、十分な休息をとっても回復せず、通常の勤務が困難になります。
- 不眠や過眠: 睡眠のリズムが乱れることで、日中の活動に支障が出ます。
- 不安感・焦燥感: 必要以上に不安を感じたり、イライラしたりすることで、対人関係や業務に悪影響が出ることがあります。
- 身体症状: 頭痛、肩こり、動悸、胃の不調など、様々な身体的な不調を伴うこともあり、これらの症状が仕事を困難にさせます。
これらの症状が医師によって診断され、「仕事に就くことができない状態である」と判断されれば、うつ病も傷病手当金の支給対象となります。
重要なのは、病気の名称そのものよりも、病気によって具体的にどのような症状が現れ、それが仕事にどのように支障をきたしているかという点です。
うつ病で傷病手当金をもらうための4つの条件

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
うつ病で申請する場合も例外ではありません。
これらの条件を正しく理解することが、スムーズな申請の第一歩です。
傷病手当金の支給要件については、各健康保険組合や自治体のウェブサイトで詳しく解説されています。
支給条件1:業務外の事由による病気やけが
傷病手当金は、業務外の病気やけがが原因で働くことができない場合に支給されます。
- 業務外の事由とは: 私的な病気やけが、すなわち仕事中や通勤中に発生したものではない病気やけがを指します。風邪、インフルエンザ、癌、心臓病、そしてうつ病などの精神疾患などがこれに該当します。
- 業務上・通勤上の事由との違い: 仕事中や通勤中の病気やけが(労働災害)の場合は、傷病手当金ではなく「労災保険」からの給付(休業補償給付など)の対象となります。後述しますが、うつ病の場合、その原因が仕事にあるか否かの判断が難しくなるケースがあります。
うつ病の場合、その発症に仕事上のストレスが関係していることは少なくありませんが、純粋に業務上・通勤上の災害と認められるケースは限られます。
多くの場合、私病として傷病手当金の対象となります。
支給条件2:仕事に就くことができない状態である
この条件は、傷病手当金の支給において最も重要な判断基準の一つです。
単に病気であるというだけでなく、病気やけがの療養のため、これまで行っていた仕事や、経験・能力を考慮して従事可能な他の仕事に就くことができない状態であることが必要です。
- 医師の判断が重要: この「仕事に就くことができない状態」であるかどうかの判断は、原則として療養を担当する医師の意見に基づいて行われます。
医師は、うつ病の症状の重さ、心身の状態、治療内容などを総合的に判断し、診断書(傷病手当金支給申請書に記載される「療養担当者記入欄」)に記載します。 - 具体的な判断基準:
- 特定の業務だけでなく、会社の他の部署での業務や、軽作業など、現時点の病状で就労可能な仕事が一切ないかどうか。
- 症状により、通勤自体が困難であるかどうか。
- 症状の波があり、継続的に働くことが困難であるかどうか。
- 治療に専念する必要があり、就労が治療の妨げとなるかどうか。
- 仕事内容との関連性: うつ病の症状が、本人の職種や具体的な仕事内容に与える影響も考慮されます。
例えば、対人業務が多い職種で社交性やコミュニケーション能力が著しく低下している場合や、高度な集中力を要する職種で集中力が保てない場合などは、就労が困難と判断されやすくなります。
自己判断ではなく、必ず医師とよく相談し、症状が仕事に与える具体的な影響を正確に伝えることが重要です。
支給条件3:連続した3日間の休み(待期期間)がある
傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み始めた日からすぐに支給されるわけではありません。
連続して3日間(公休日や祝日、有給休暇、欠勤など休み方の種類は問わない)仕事を休んだ後、4日目以降の休みから支給対象となります。
この連続した3日間を「待期期間」といいます。
- 待期期間の考え方:
- 仕事を休んだ最初の日を1日目として数えます。
- 土日祝日、有給休暇、欠勤など、休みの理由や形態に関わらず、仕事をしない状態が連続していれば待期期間として認められます。
- 3日間は連続している必要があります。途中で1日でも出勤すると、待期期間はリセットされ、最初からやり直しになります。
- 待期期間は支給対象外: 待期期間の3日間については、傷病手当金は支給されません。
支給されるのは、待期期間を満了した後の4日目以降の休業期間からです。 - 待期期間は一度でOK: 傷病手当金の支給対象となる病気やけがについて、一度待期期間を満了すれば、その後再び同じ病気で休業した場合に再度待期期間を満たす必要はありません(ただし、一旦仕事に復帰し、その後再び同じ病気で休業した場合でも、支給期間の通算には含みます)。
例えば、月曜日から水曜日まで連続して休んだ場合、月・火・水が待期期間となり、木曜日以降の休業日が傷病手当金の支給対象となります。
この3日間は、有給休暇を使っても、欠勤扱いにしても構いません。
支給条件4:休業した期間に給与の支払いがない
傷病手当金は、病気やけがで休業している期間について、事業主から給与の支払いがなかった場合に支給されます。
- 給与支払いがあった場合: 休業期間中に給与(基本給だけでなく、賞与なども含む)の支払いがあった場合、傷病手当金の支給額は、傷病手当金の日額よりも支払われた給与の日額が少ない場合に、その差額分が支給されるか、あるいは傷病手当金は支給されないことがあります。
具体的には、支払われた給与の日額が傷病手当金の日額と同等かそれ以上であれば、傷病手当金は支給されません。 - 一部支給: 給与の支払いが傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
- 有給休暇との関係: 休業中に有給休暇を取得した場合、その日は給与が支払われているとみなされるため、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を申請する期間は、有給休暇を使わないか、使い切った後に申請するのが一般的です。
会社によっては、休業期間中の給与について、給与規程や就業規則で定めがある場合があります。
申請前に、会社の担当部署(総務部や人事部など)に確認しておくと良いでしょう。
医師の診断書の重要性
傷病手当金の申請において、医師の診断書(傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入欄」)は、支給の可否を判断する上で最も重要な書類です。
- 就労不能であることの証明: 医師は、うつ病の症状、治療内容、予後見込みなどを医学的な見地から判断し、被保険者が「仕事に就くことができない状態である」ことを証明します。
この医師の判断が、支給条件2を満たしているかどうかの根拠となります。 - 傷病名の記載: 診断書には、うつ病であること(あるいは抑うつ状態など)が正式な傷病名として記載されます。
- 病状や治療経過の記載: 病気の症状の具体的な内容、治療の経過、日常生活への影響などが詳細に記載されることで、審査を行う健康保険組合等が病状を正確に把握することができます。
- 事業主記入欄との整合性: 申請書には事業主が記入する欄もあり、業務内容や休業期間中の勤務状況などを記載します。
医師の診断と、事業主の記載内容に矛盾がないことがスムーズな審査につながります。
医師に診断書を依頼する際は、ご自身の症状が仕事にどのように支障をきたしているかを具体的に、正直に伝えることが大切です。
例えば、「朝起き上がることが困難で通勤できない」「集中力が続かず、会議の内容が理解できない」「人と話すのが苦痛で、電話対応ができない」など、具体的な困りごとを伝えると、医師も診断書に反映させやすくなります。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

傷病手当金の申請方法と手続きの流れ

うつ病で傷病手当金を申請する場合の具体的な手続きと流れを解説します。
スムーズに申請を進めるために、必要な書類や提出先、期限などを事前に確認しておきましょう。
申請に必要な書類と入手先
傷病手当金の申請には、主に以下の書類が必要です。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険傷病手当金支給申請書 | ご加入の健康保険組合(健康保険証に記載されています)または、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。会社に問い合わせて入手できる場合もあります。 | 複数枚綴りになっています(被保険者記入用、事業主記入用、療養担当者記入用など)。 |
| 被保険者証(健康保険証) | – | 申請書に健康保険記号・番号などを記入します。コピーの提出が必要な場合もあります。 |
| 印鑑(認印) | – | 申請書に押印が必要です。 |
| 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー | – | 傷病手当金の振込先口座を確認するために必要です。 |
| その他 | 健康保険組合によっては、追加で書類の提出を求められる場合があります(例: 住民票、マイナンバー関連書類など)。加入している健康保険組合のホームページなどで確認してください。退職後に申請する場合は、資格喪失証明書などが必要になることがあります。 | 退職後の継続給付を申請する場合など、状況によって必要な書類が異なります。詳細は加入していた健康保険組合に確認が必要です。 |
申請書は、一般的に以下の4つの部分に分かれています。
- 被保険者記入用: 氏名、住所、マイナンバー、休業期間、給与支払い状況などを本人が記入します。
- 事業主記入用: 事業主が、休業期間、給与支払い状況、業務内容などを証明する欄です。
- 療養担当者記入用: 医師が、病状、就労不能であることの医学的判断、治療内容などを記入します(これが診断書にあたる部分です)。
- (場合によっては)被保険者証添付用など
申請書は、休業期間に応じて複数月分まとめて申請することも、1ヶ月ごとに申請することも可能です。
継続して休業する場合は、原則として1ヶ月ごとに申請するのが一般的です。
傷病手当金支給申請書の書き方
申請書は各項目を漏れなく正確に記入することが重要です。
特に、事業主記入欄と療養担当者記入欄の記載内容は、支給の可否に大きく影響します。
事業主(会社)記入欄の注意点
この欄は、原則として会社の総務部や人事部などが記入します。
以下の点に注意が必要です。
- 休業期間の正確な記載: 申請対象となる休業期間(待期期間満了後の最初の休業開始日から申請期間の末日まで)が正確に記載されているか確認しましょう。
- 休業期間中の給与支払いの有無・金額: 申請期間中に会社から支払われた給与(通勤手当や賞与なども含む)があるか、ある場合はその金額が正確に記載されているかを確認します。
給与の支払いがあった場合、その日や金額によっては傷病手当金が減額されたり、支給されなかったりします。 - 業務内容の記載: 申請者の担当業務が具体的に記載されます。
医師が就労の可否を判断する際の参考になります。 - 欠勤控除などの記載: 休業期間中の欠勤控除などがあれば記載されます。
- その他: 会社によっては、事業主の押印が必要な場合があります。
会社に記入を依頼する際は、早めに書類を渡し、記入期間を考慮して依頼しましょう。
療養担当者(医師)記入欄の注意点
この欄は、うつ病の治療を受けている医師が記入します。
傷病手当金の申請において最も重要な箇所です。
- 傷病名と発病年月日: 正式な傷病名(例: 抑うつ病、適応障害など)と、その病気によって初めて診療を受けた日(発病年月日)が記載されます。
うつ病の場合、発病年月日を特定するのが難しいこともありますが、医師が医学的な見地から判断し記載します。 - 病状と経過: うつ病の具体的な症状(例: 強い倦怠感、不眠、集中力低下、気分の落ち込みなど)や、これまでの治療の経過、現在の病状などが詳細に記載されます。
- 就労不能であることの医学的所見: この欄が最も重要です。
医師が、「上記の病状により、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの期間、仕事に就くことが困難であると医学的に判断できる」といった内容を記載します。
単に「休業が必要」というだけでなく、「仕事に就くことができない」という具体的な判断が記載されているか確認が必要です。 - 日常生活の状況: 日常生活における状況(例: 起床・就寝時間、食事・入浴の状況、外出頻度、対人交流の状況など)が記載されます。
これは、病状の重さや回復の程度を判断する参考になります。 - 予後: 病気の今後の見込みが記載されます。
- 治癒見込み: 病気が治る見込みについて記載されます。
医師に記入を依頼する際は、申請に必要な期間(例えば「〇月〇日から〇月〇日までの1ヶ月分の申請です」)を明確に伝えましょう。
また、ご自身の症状が日常生活や仕事にどのように影響しているかを改めて具体的に伝え、医師の判断の参考にしてもらうと良いでしょう。
申請期間と提出先
傷病手当金の申請には、原則として対象期間の翌日から2年以内という申請期間(時効)があります。
- 時効: 傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過すると時効によって消滅します。
例えば、4月1日に労務不能であった日については、その翌日である4月2日から数えて2年が経過すると申請できなくなります。
遡ってまとめて申請する場合も、時効に注意が必要です。 - 推奨される申請頻度: 一般的には、1ヶ月ごとに申請するのがスムーズです。
療養担当者(医師)の記入欄は、通常1ヶ月程度の期間で記載されることが多いためです。
また、早めに申請することで、経済的な支援を途切れさせることなく受け取ることができます。 - 提出先: 傷病手当金支給申請書の提出先は、ご自身が加入している健康保険組合または協会けんぽです。
通常は、会社の総務部や人事部を通して提出する場合が多いですが、直接ご自身で提出することも可能です。
提出方法は、郵送または窓口持参が一般的です。
会社の担当者や、加入している健康保険組合のホームページなどで、具体的な提出方法や締め切りを確認しておきましょう。
申請から支給までの審査期間目安
傷病手当金を申請してから実際に支給されるまでの期間は、申請先の健康保険組合や、申請内容、添付書類の状況によって異なります。
一般的な目安は、申請書類が受理されてから約2週間〜2ヶ月程度です。
- 審査に時間がかかる要因:
- 申請書類に不備がある場合(記入漏れ、押印漏れ、添付書類不足など)。
- 申請内容について確認が必要な場合(事業主への照会、医師への病状照会など)。
- 健康保険組合等の事務処理状況による場合。
- 初めての申請の場合。
- 確認の重要性: 申請から目安期間を過ぎても連絡がない場合は、健康保険組合等に問い合わせて、審査状況を確認してみましょう。
特に初めて傷病手当金を申請する場合や、複雑な事情がある場合は、審査に時間がかかる傾向があります。
余裕を持って申請手続きを進めることが大切です。
うつ病の傷病手当金はいくらもらえる?計算方法と支給期間

傷病手当金の支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。
また、支給される期間には上限があります。
1日当たりの支給額の計算方法
傷病手当金の1日当たりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
【計算式】
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均 を 30で割った額 の 3分の2
より具体的に説明すると、
- 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を算出:
- 「支給開始日」とは、待期期間を満了した後の、最初に傷病手当金の支給対象となる休業日です。
- 支給開始日が含まれる月以前の、直近12ヶ月間の健康保険の標準報酬月額(社会保険料を計算する際の基準となる月額)の合計額を算出します。
- この合計額を12で割って、1ヶ月当たりの平均標準報酬月額を求めます。
- ※もし被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれか低い額の3分の2が支給されます。
- 支給開始日以前の継続した被保険者期間における各月の標準報酬月額の平均額を30で割った額
- 標準報酬月額の平均額の算定にあたる期間において、その者の加入していた健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額(協会けんぽの場合は、その年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額を30で割った額)
- 1で算出した平均標準報酬月額を30で割る: これにより、1日当たりの標準報酬日額に相当する額が算出されます。
- 2で算出した額の3分の2を求める: これが、傷病手当金の1日当たりの支給額となります。
【計算例】
例えば、支給開始日以前12ヶ月間の平均標準報酬月額が30万円だった場合:
- 1日当たりの標準報酬日額に相当する額: 30万円 ÷ 30日 = 10,000円
- 1日当たりの傷病手当金支給額: 10,000円 × 2/3 = 6,666円 (小数点以下は四捨五入または切り捨てなど、健康保険組合によって処理が異なる場合があります)
支給される総額:
1日当たりの支給額 × 支給対象となる休業日数
となります。
傷病手当金が支給される期間(最長1年6ヶ月)
傷病手当金が支給される期間には上限があり、支給を開始した日から最長で1年6ヶ月間です。
- 通算期間: 支給期間の「1年6ヶ月」は、実際に傷病手当金の支給を受けた期間を通算して計算されます。
途中で仕事に復帰し、再び同じ病気やけがで休業した場合も、最初に傷病手当金の支給が開始された日から起算して1年6ヶ月以内であれば、通算した支給期間内で再び傷病手当金を受け取ることができます。
ただし、この1年6ヶ月の中には、待期期間や仕事に復帰していた期間、有給休暇を取得していた期間などは含まれません。 - 異なる病気の場合: もし、うつ病で傷病手当金を受け取っている期間中に別の病気にかかり、その病気でも労務不能になった場合、それぞれの病気について支給期間が計算されます。
ただし、どちらの病気でも同じ期間休業している場合は、重複して支給されるわけではありません。 - 1年6ヶ月を超えた場合: 支給期間が1年6ヶ月を経過した場合は、病状が回復していなくても、原則として傷病手当金の支給は打ち切りとなります。
ただし、退職後に継続給付を受けている間に1年6ヶ月が経過した場合や、同一の病気で障害年金等を受給している場合は、調整が行われることがあります。
うつ病の治療は長期化するケースも少なくありません。
傷病手当金の支給期間には上限があることを理解し、今後の生活設計を考える上で考慮に入れることが重要です。
うつ病で傷病手当金がもらえないケースと不支給理由

傷病手当金は、申請すれば必ず支給されるわけではありません。
以下のような場合には、不支給となることがあります。
主な不支給理由
傷病手当金が不支給となる主な理由は以下の通りです。
申請条件を満たさない場合
前述した4つの支給条件のいずれかを満たしていない場合は、傷病手当金は支給されません。
- 業務上・通勤上の病気やけが: 労災保険の対象となる場合は、傷病手当金は支給されません。
うつ病の原因が仕事にあると判断された場合、労災保険の申請を検討する必要があります。
うつ病などの精神疾患に関する職場のメンタルヘルス対策や休業時の支援制度については、厚生労働省の指針も参考にできます。 - 仕事に就くことができない状態ではないと判断された: 医師の診断書や会社の勤務状況などから、病状が就労に支障をきたすほどではないと判断された場合。
自己申告だけでなく、客観的な状況から判断されます。 - 待期期間を満たしていない: 連続した3日間の休業を満たしていない場合。
- 休業期間中に給与が支払われた: 傷病手当金の日額以上の給与が会社から支払われていた場合。
特に、「仕事に就くことができない状態であるか」の判断は、医師の診断書の記載内容に大きく依存します。
医師とのコミュニケーションが非常に重要になります。
虚偽の申請を行った場合(傷病手当 嘘)
傷病手当金の申請において、事実と異なる内容を申告したり、不正な手段で受給しようとしたりすることは、詐欺行為にあたります。
- 虚偽申請の例:
- 実際には就労可能な状態であるにも関わらず、「労務不能である」と偽って申請する。
- アルバイトなどで収入を得ているにも関わらず、その事実を隠して申請する。
- 医師に虚偽の病状を伝えて診断書を記載してもらう。
- 発覚した場合のペナルティ:
- 支給された傷病手当金の全額返還: 不正に受給した傷病手当金は、全額返還を求められます。
- 追徴金: 返還額に加えて、追徴金が課されることがあります。
- 詐欺罪等による罰則: 悪質な場合は、詐欺罪などで刑事罰の対象となる可能性もあります。
- 会社の懲戒処分: 会社に虚偽の申告をしたとして、解雇などの懲戒処分の対象となる可能性もあります。
傷病手当金は、本当に働くことができない人のための制度です。
絶対に虚偽の申請や不正受給は行わないでください。
症状が軽快して就労が可能になった場合は、速やかに申請を打ち切る必要があります。
申請が遅れた場合の影響
傷病手当金には時効(対象期間の翌日から2年以内)があります。
- 時効による申請権の消滅: 時効が成立した日については、遡って傷病手当金を申請することはできません。
つまり、もらえるはずだった傷病手当金を受け取ることができなくなります。 - 審査への影響: 申請が大幅に遅れた場合、当時の病状や休業状況に関する確認が難しくなり、審査に時間がかかったり、場合によっては支給判断が難しくなったりする可能性もゼロではありません。
経済的な支援を必要としているにも関わらず、申請を忘れたり、手続きが面倒で後回しにしたりした結果、時効を迎えてしまうのは非常にもったいないことです。
休業を開始し、待期期間を満了したら、できるだけ速やかに申請手続きに取り掛かることをお勧めします。
仕事が原因のうつ病の場合、傷病手当金は?

うつ病の発症に、長時間労働、ハラスメント、人間関係の悩みなど、仕事上の強いストレスが深く関わっているケースは少なくありません。
このような場合、傷病手当金ではなく労災保険の対象となる可能性が出てきます。
労災保険との関係性
傷病手当金は「業務外」の病気やけがが対象ですが、労災保険は「業務上」または「通勤上」の事由による病気やけがが対象です。
うつ病などの精神疾患についても、仕事が原因で発症したと認められれば、労災保険の対象となります。
- 労災保険の給付: 労災保険では、療養補償給付(治療費など)、休業補償給付(休業中の賃金補償)、障害補償給付、遺族補償給付など、様々な給付が用意されています。
休業補償給付は、原則として休業4日目から、給付基礎日額の8割(休業補償給付6割+休業特別支給金2割)が支給されます。 - 傷病手当金との調整: 同一の病気やけがに対して、労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の両方を同時に受給することはできません。
労災保険の給付が優先されます。
労災保険の給付を受ける場合、傷病手当金は支給されません。
業務起因性の判断について
うつ病が労災保険の対象となるか(業務起因性があるか)どうかの判断は、厚生労働省が定める認定基準に基づいて行われます。
この判断は非常に専門的であり、個別のケースごとに慎重な調査が必要です。
- 認定基準の概要: 認定基準では、「業務による心理的負荷評価表」を用いて、仕事の内容や状況を分析し、心理的負荷の強さを「強」「中」「弱」の3段階で評価します。
心理的負荷が「強」と判断され、かつ、業務以外の原因(個人的な問題など)による心理的負荷や既往歴・飲酒などの影響が認められない場合に、労災として認定される可能性が高くなります。 - 判断の難しさ: うつ病は、様々な要因が複合的に絡み合って発症することが多く、仕事だけが原因であると断定することが難しい場合があります。
そのため、業務起因性の判断は複雑であり、時間がかかることも少なくありません。 - どちらを申請すべきか: もし、うつ病の発症に仕事が強く関わっている可能性があると考える場合は、まずは労災申請を検討し、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
同時に、労災として認められない場合に備えて、傷病手当金の申請についても準備を進めておくことが賢明です。
労災申請が不支給となった場合は、改めて傷病手当金を申請することが可能です(ただし、時効には注意が必要です)。
どちらの制度を利用できるか不明な場合は、会社の労務担当者、労働組合、労働基準監督署、あるいは社会保険労務士などの専門家に相談すると良いでしょう。
傷病手当金以外に利用できる経済的支援

うつ病で休業する際に利用できる経済的支援は、傷病手当金だけではありません。
傷病手当金の支給期間が終了した後や、傷病手当金だけでは不十分な場合に、他の制度も検討することができます。
自立支援医療制度(うつ病 国からの補助金)
自立支援医療制度は、心身の障害を持つ方が、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
うつ病などの精神疾患も対象となります。
- 制度の目的: 精神疾患の治療を継続的に受ける必要のある方が、経済的な負担を気にせずに適切な医療を受けられるように支援すること。
- 対象となる医療費: 精神疾患に関する医療費(診察、薬代、デイケア、訪問看護など)が対象となります。
- 自己負担額の軽減: 通常、医療費の自己負担割合は3割ですが、自立支援医療制度を利用すると、原則として1割に軽減されます。
さらに、世帯の所得状況や病状に応じて、毎月の自己負担額に上限(自己負担上限月額)が設定されます。 - 申請方法: 住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
申請には、医師の診断書などが必要です。 - 傷病手当金との関係: 自立支援医療制度は、医療費の自己負担を軽減する制度であり、休業中の生活費を補償する傷病手当金とは異なる制度です。
傷病手当金を受給しているかどうかにかかわらず、自立支援医療制度を利用することは可能です。
両方の制度を併用することで、経済的な負担を総合的に軽減することができます。
うつ病の治療を継続している場合は、ぜひ自立支援医療制度の利用を検討してみてください。
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される年金です。
うつ病も、一定の障害状態にあると認められれば、障害年金の支給対象となります。
- 対象となる年金:
- 障害基礎年金: 国民年金の被保険者、または被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、一定の納付要件を満たしている方が対象です。
主に、国民年金に加入していた自営業者や専業主婦などが対象となります。 - 障害厚生年金: 厚生年金の被保険者であった方が対象です。
会社員などが対象となります。
- 障害基礎年金: 国民年金の被保険者、または被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、一定の納付要件を満たしている方が対象です。
- 障害等級: 精神疾患による障害の程度に応じて、1級、2級、3級(障害厚生年金のみ)に区分され、支給額が異なります。
うつ病の場合、日常生活能力や就労能力の程度などから総合的に判断されます。 - 受給要件:
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やけかについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、被保険者期間中であること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
- 障害状態要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、法令で定める障害の状態にあること。
- 傷病手当金との関係: 傷病手当金と障害年金は、原則として同時に全額を受給することはできません。
同じ病気やけがで両方の受給権がある場合、障害年金が優先され、その分傷病手当金が減額または支給調整されます。
ただし、障害年金の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額分が傷病手当金として支給されることもあります。 - 支給期間: 障害年金は、障害状態が続く限り(有期認定の場合は更新が必要)、原則として支給期間に上限はありません。
傷病手当金の支給期間(最長1年6ヶ月)が終了した後も、障害状態が続く場合に経済的な支えとなります。
うつ病で長期の療養が必要となり、傷病手当金の期間が満了に近づいている場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は、障害年金の申請を検討してみる価値があります。
障害年金の詳細な情報や申請手続きについては、日本年金機構の障害年金ガイドブックをご確認ください。
手続きは複雑な場合があるため、年金事務所や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯に対し、それぞれの世帯の状況に合わせた資金を貸し付ける制度です。
うつ病により収入が減少・途絶し、生活が困窮している場合などに利用できる可能性があります。
- 制度の目的: 低所得者世帯等に対して、生活の安定や経済的な自立を支援することを目的とした公的な貸付制度です。
- 資金の種類:
- 総合支援資金: 失業等により生活が困窮し、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金が必要な場合に貸し付けられます。
- 福祉資金: 療養に必要な費用、介護に必要な費用、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用など、様々な福祉に係る費用として必要な場合に貸し付けられます。
うつ病の療養に伴う費用なども、対象となる場合があります。 - 教育支援資金、不動産担保型生活資金などもあります。
- 申請窓口: 住所地の市区町村の社会福祉協議会が窓口となります。
- 貸付条件: 世帯の所得状況や、資金の種類によって貸付条件や貸付額、償還期間などが異なります。
無利子または低利子で借り入れできるのが特徴です。 - 傷病手当金との関係: 傷病手当金を受給しているかどうかにかかわらず、生活福祉資金貸付制度の対象となる場合があります。
傷病手当金だけでは生活費が足りない場合や、緊急に資金が必要な場合に検討することができます。
うつ病による休業で生活が厳しくなった場合は、一人で悩まず、まずは社会福祉協議会に相談してみましょう。
専門の相談員が状況を聞き取り、利用できる制度や支援についてアドバイスしてくれます。
うつ病の傷病手当金に関するよくある疑問

傷病手当金の申請について、多くの人が抱く疑問とその回答をまとめました。
審査期間はどれくらいかかりますか?
前述しましたが、申請から支給までの審査期間は、申請先の健康保険組合や申請内容、添付書類の状況によって異なります。
一般的には、申請書類が受理されてから約2週間〜2ヶ月程度です。
書類に不備があったり、確認事項があったりすると、さらに時間がかかる場合があります。
特に初めての申請や、複雑な病状の場合は、審査に時間がかかる傾向があります。
申請から1ヶ月半〜2ヶ月程度経過しても連絡がない場合は、加入している健康保険組合等に問い合わせて、審査状況を確認してみることをお勧めします。
退職後も傷病手当金はもらえますか?
はい、一定の条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れる場合があります(任意継続被保険者制度とは異なります)。
これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
- 継続給付の条件:
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者期間や、共済組合の組合員期間、国民健康保険の期間は含まれません)。
- 退職日において、傷病手当金を受けているか、または受けられる状態であること(すなわち、退職日の前日までに、傷病手当金の支給条件である4つの条件をすべて満たしており、待期期間も完了していること)。
- 支給期間: 支給期間は、退職前から受けていた期間と通算して、最長1年6ヶ月間です。
- 申請先: 退職前に加入していた健康保険組合または協会けんぽに直接申請します。
会社の証明は不要になりますが、退職したことなどを証明する書類が必要となる場合があります。
退職後に傷病手当金の継続給付を希望する場合は、退職前に会社の担当者や加入している健康保険組合等に必ず確認し、必要な手続きについて詳細を把握しておくことが重要です。
傷病手当金申請中にアルバイトはできますか?
原則として、傷病手当金は「仕事に就くことができない状態」である場合に支給されるものです。
したがって、傷病手当金の受給期間中にアルバイトなどで収入を得ることは、「仕事に就くことができる状態である」とみなされ、傷病手当金の支給が停止されたり、減額されたりする可能性が非常に高いです。
- 判断基準: 軽易な作業であっても、それが収入を伴う就労であれば、「仕事に就くことができた」と判断される可能性があります。
たとえ短時間や短期間のアルバイトであっても、安易に行うべきではありません。 - 収入があった場合: もし、申請期間中にアルバイトなどで収入を得た場合は、その旨を正直に申請書に記載する必要があります。
収入があった期間や金額によっては、傷病手当金の支給額が調整されるか、支給されないことになります。
事実を隠して申請すると、不正受給となりますので絶対にやめましょう。 - リハビリ目的の就労: 病状が回復し、リハビリや試し出勤として短時間・短期間の勤務を検討する場合もあるでしょう。
このような場合でも、収入が発生するのであれば原則として傷病手当金の支給対象とはなりません。
ただし、病状の回復段階でのリハビリテーションとしての就労について、個別の状況や健康保険組合の判断によっては考慮される可能性もゼロではありませんが、非常に稀なケースと考えられます。
基本的には、完全に治癒・寛解して就労可能になった段階で傷病手当金の支給を終了するのが原則です。
傷病手当金を受給している期間は、療養に専念することが本来の目的です。
焦ってアルバイトなどを始めることは避け、まずは治療に専念し、医師と相談しながら段階的に社会復帰を目指すのが望ましいです。
傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?
前述しましたが、傷病手当金と障害年金は、原則として同一の病気やけがに対して同時に全額を受給することはできません。
- 調整: 同じ病気やけがで傷病手当金と障害年金(障害厚生年金または障害基礎年金)の両方の受給権がある場合、障害年金が優先して支給されます。
そして、傷病手当金の額は、障害年金の額との差額分のみが支給されるか、あるいは障害年金の額が傷病手当金の額以上であれば、傷病手当金は支給されません。 - 障害厚生年金と障害基礎年金: 障害厚生年金を受給している場合は、その全額が優先されます。
障害基礎年金のみを受給している場合も同様に調整が行われます。 - 異なる病気の場合: 異なる病気やけがでそれぞれ傷病手当金と障害年金の受給権がある場合は、調整の対象とはなりません。
うつ病で傷病手当金を受給中に障害年金の申請を検討する場合は、将来的に両方の受給権が発生する可能性があることを理解し、受給額がどのように調整されるのかを事前に確認しておくと良いでしょう。
年金事務所や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
申請書の「仕事内容」や「日常生活の状況」の書き方は?(抑うつ状態 傷病手当金 書き方)
傷病手当金支給申請書の「被保険者記入用」には、ご自身の仕事内容や休業期間中の日常生活の状況を記載する欄があります。
特にうつ病(抑うつ状態)で申請する場合、これらの項目を具体的に、正直に記載することが重要です。
- 仕事内容:
- 単に職種名だけでなく、具体的な業務内容を記載しましょう。
例えば、「事務職」であれば、「データ入力、電話・来客対応、会議資料作成、営業担当者との連携」など、日々の業務を細かく記述します。 - 業務遂行に求められる能力(例: 集中力、判断力、コミュニケーション能力、対人折衝能力、長時間労働への耐性など)も補足すると、病状が仕事に与える影響を理解してもらいやすくなります。
- 単に職種名だけでなく、具体的な業務内容を記載しましょう。
- 休業期間中の日常生活の状況:
- 具体的な生活リズムや活動内容を記載します。
例えば、「朝起き上がることが困難で、午前中は寝ていることが多い」「食事の準備や片付けが辛く、簡単なもので済ませている」「入浴は週に数回程度」「ほとんど外出せず、自宅で静かに過ごしている」「読書やテレビなど、集中力を要することは難しい」「家族以外との会話はほとんどない」など、病状によってできなくなったことや、困難を感じていることを中心に記述します。 - 良い日と悪い日がある場合は、その症状の波についても触れると、病状がより正確に伝わります。
- 誰かの介助や支援が必要な状況があれば、具体的に記載します(例: 食事の準備を家族に頼んでいる、外出時に付き添いが必要など)。
- 具体的な生活リズムや活動内容を記載します。
これらの項目を具体的に記載することで、健康保険組合等の審査担当者が、あなたのうつ病の症状が日常生活や仕事にどれだけ支障をきたしているのかをより正確に把握し、就労不能であるかどうかの判断材料とします。
正直に、ありのままの状況を記述することが大切です。
うつ病で困ったらまずは傷病手当金を検討しよう

うつ病によって働くことが難しくなったとき、経済的な不安は治療へのモチベーションを低下させたり、回復を遅らせたりする要因となり得ます。
傷病手当金は、そのような状況にある方の生活を経済的に支え、安心して治療に専念できる環境を整えるための大切な制度です。
うつ病も、病状が就労に支障をきたすほど重いと医師が判断すれば、傷病手当金の支給対象となります。
受給のためには、「業務外の病気やけが」「仕事に就くことができない状態であること」「連続した3日間の待期期間があること」「休業期間中に給与の支払いがないこと」という4つの条件を満たす必要があります。
申請手続きは、健康保険傷病手当金支給申請書に必要事項を記入し、医師と事業主(会社)にそれぞれの欄を証明してもらい、ご加入の健康保険組合等に提出します。
特に医師の診断書(療養担当者記入欄)は、就労不能であることの重要な証明となるため、ご自身の症状を正確に医師に伝えることが大切です。
傷病手当金の支給額は、過去1年間の標準報酬月額の平均をもとに計算され、1日当たりの額は標準報酬日額の約3分の2となります。
支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月です。
申請内容に不備があったり、条件を満たさなかったり、あるいは虚偽の申請を行ったりした場合は、不支給となることがあります。
また、労災保険の対象となる業務上のうつ病の場合は、傷病手当金ではなく労災保険からの給付となります。
傷病手当金以外にも、医療費の自己負担を軽減する自立支援医療制度や、長期の障害状態に対する障害年金、生活資金の貸付制度である生活福祉資金貸付制度など、利用できる経済的支援制度は複数あります。
ご自身の状況に合わせて、これらの制度の利用も検討してみましょう。
うつ病による休業は、心身ともに辛い状況です。
経済的な不安を抱え込まず、まずは傷病手当金の制度について理解し、申請を検討してみてください。
申請手続きで分からないことや不安なことがあれば、会社の担当部署、加入している健康保険組合、あるいは社会保険労務士などの専門家に相談することも可能です。
この記事が、うつ病で休業されている方が傷病手当金を活用し、安心して療養に専念するための一助となれば幸いです。
【免責事項】
この記事は、傷病手当金に関する一般的な情報提供を目的としており、法律や制度に関する専門的なアドバイスを提供するものではありません。
傷病手当金の支給に関する最終的な判断は、ご加入の健康保険組合等が行います。
個別のケースに関する具体的な手続きや要件については、必ずご自身の加入している健康保険組合または協会けんぽ、あるいは専門家にご確認ください。
制度は改正される可能性があり、最新の情報については厚生労働省や健康保険組合等の公式発表をご確認ください。
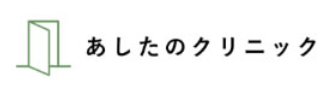

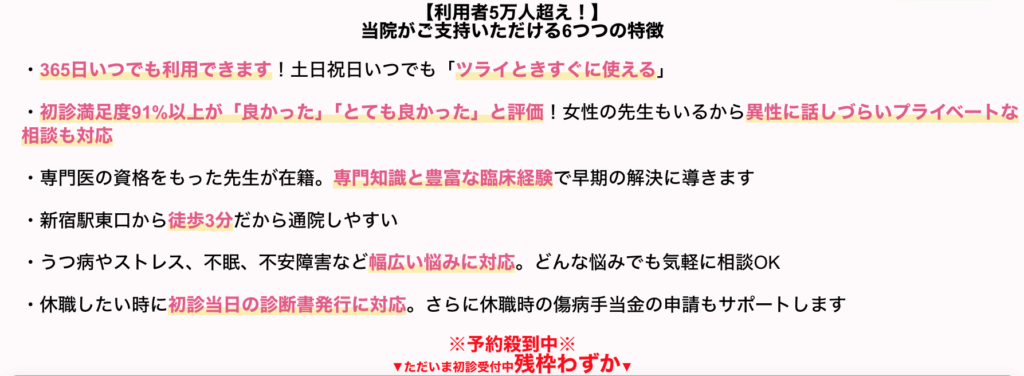



コメント