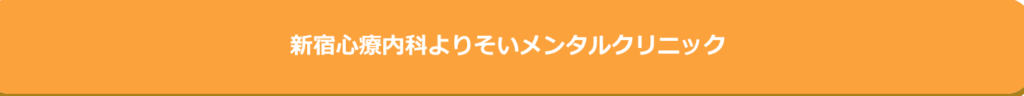
パワハラによって心身の不調を感じているとき、その状況を証明するための手段として「診断書」の取得を検討する方が多くいます。しかし、パワハラにおける診断書がどのような意味を持つのか、どのように取得し、何に活用できるのか、そしてその有効性にはどのような限界があるのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。
この記事では、パワハラによる診断書の役割や取得方法、記載内容、活用方法、そして注意点まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。パワハラによる苦しみから抜け出し、適切な対応を取るための一歩として、ぜひ参考にしてください。
パワハラで診断書が必要となるケース

パワハラによって診断書が必要となるのは、主に以下のようなケースが考えられます。ご自身の状況と照らし合わせながら、診断書が必要か検討してみてください。
- 体調不良の証明: パワハラが原因で心身の健康を害し、体調不良が続いていることを客観的に証明したい場合。
- 休職・休業手続き: 医師の判断に基づき、心身の回復のために一定期間の休職や休業が必要となった場合、会社に提出する診断書が必要です。
- 会社への改善要求や交渉: 会社に対してパワハラの事実を認めさせたり、加害者への処分、配置転換、再発防止策などを求めたりする際に、診断書が交渉材料となります。
- ハラスメント相談窓口への相談: 会社内外のハラスメント相談窓口に相談する際に、状況の深刻さを伝えるための資料として診断書を提出することがあります。
- 労働組合への相談・支援依頼: 労働組合を通じて会社と交渉を進める場合に、診断書が組合員の状況を説明する根拠となります。
- 法的手続き(労働審判、訴訟など): パワハラを理由に会社に対して損害賠償請求や地位確認などを求める場合、診断書は被害の証拠として提出されます。
- 労災申請: パワハラによる精神疾患や、それが原因で発症した病気について労働災害として申請する場合、診断書は不可欠な証拠となります。
- 慰謝料請求: パワハラによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求する際に、診断書は精神的損害の程度を証明する重要な資料となります。
これらのケースにおいて、診断書は単に病状を証明するだけでなく、「パワハラという出来事によって、これだけ心身に不調をきたしている」という事実を医師という第三者が医学的に証明する重要な役割を担います。
パワハラ被害に診断書は証拠となるのか?有効性と限界

パワハラ被害を訴える上で、診断書は非常に重要な証拠の一つとなり得ます。しかし、診断書があればすべてが解決するわけではなく、その有効性と限界を理解しておくことが大切です。
診断書が証拠として認められる条件
診断書が証拠として認められるためには、いくつかの条件があります。
- 信頼できる医療機関・医師によるもの: 診断を行った医療機関が適切であり、医師が医学的根拠に基づいて診断していることが前提です。
- 具体的な病名・症状の記載: 「体調不良」といった曖昧な記載ではなく、具体的な傷病名(例:適応障害、うつ病など)や、その病状を示す具体的な症状(例:不眠、食欲不振、倦怠感、抑うつ気分、不安感など)が明確に記載されている必要があります。
- 診断期間や治療の見込み: 診断された病状がどのくらいの期間続いているか、または今後どのくらいの治療期間が必要かといった情報が記載されていると、被害の継続性や深刻さを示す上で有効です。
- 医師の意見の記載(可能であれば): 医師が診察を通じて、「職場環境(パワハラ)との関連が考えられる」といった意見を追記している場合、証拠としての価値がさらに高まります。
これらの要素が明確に記載されている診断書は、あなたの体調不良が単なる個人的な問題ではなく、パワハラという外部要因によって引き起こされた可能性が高いことを医学的に示唆する強力な証拠となります。
診断書だけでは不十分な理由と他の証拠
診断書は「パワハラによって体調が悪化した」という結果や状態を証明する医学的な証拠ですが、「どのようなパワハラがあったか」という具体的な加害行為そのものを直接証明するものではありません。これが、診断書だけでは不十分とされる理由です。
パワハラの事実を立証するためには、診断書に加えて、以下のような客観的な証拠をできる限り多く収集することが重要です。法的手続きにおける証拠収集の要領については、厚生労働省の資料も参考にしてください。
- 録音・録画データ: パワハラ発言や行為を直接記録したものは、最も強力な証拠となり得ます。
- メールやチャットの記録: 業務時間外の頻繁な連絡、理不尽な指示、誹謗中傷などが記録されている場合、パワハラの間接的な証拠となります。
- 業務日報や日記: いつ、誰から、どのようなパワハラを受けたのか、その時の自分の体調や気持ちはどうだったのかを具体的に記録したものです。後から見返した際に、状況を正確に伝えるのに役立ちます。
- 目撃者の証言: 同僚などがパワハラを目撃していた場合、その証言は有力な証拠となります。可能であれば、証言書を作成してもらうとより良いでしょう。
- 人事評価や業務指示書: 明らかに不当な評価や、達成不可能な業務量を課された指示書なども、パワハラの間接的な証拠となり得ます。
診断書は、これらの客観的な証拠と組み合わせて提出することで、初めてその真価を発揮します。「このようなパワハラ行為(客観的証拠)があったから、私はこのような病状(診断書)になったのです」というストーリーを組み立て、より説得力のある主張を展開することが可能になります。
精神的苦痛を証明する診断書の役割
パワハラの被害において、目に見えない精神的な苦痛は、周囲に理解されにくい側面があります。診断書は、この精神的な苦痛が単なる「気分」や「気のせい」ではなく、医学的に診断されるべき病状として現れていることを証明する重要な役割を果たします。
医師によって下された診断名や症状の記載は、パワハラがあなたの心に与えたダメージの深刻さを明確に示します。「抑うつ状態」「不眠症」「適応障害」といった診断は、あなたが経験している苦痛が専門家によって認められたものであることを意味し、会社や第三者機関に対して、あなたの置かれている状況の深刻さを効果的に伝えることができます。これにより、会社側も事態をより重く受け止めざるを得なくなり、改善に向けた対応を促すことに繋がります。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

パワハラ 診断書のもらい方・取得方法

パワハラによる診断書を取得するためには、適切な医療機関を受診し、医師に状況を正確に伝えることが重要です。具体的なもらい方のステップを解説します。
診断書を依頼する医療機関の選び方(何科?)
パワハラによる心身の不調の場合、主に以下の科を受診することを検討しましょう。
- 精神科・心療内科: パワハラによって、うつ病、適応障害、不安障害、不眠症などの精神的な症状が強く出ている場合に最も適しています。精神的な側面からの診断や治療を専門としています。
- 内科: 胃腸の不調、頭痛、めまい、倦怠感など、身体的な症状が強く出ている場合や、まずは気軽に相談したい場合に選択肢となります。ただし、パワハラとの因果関係を診断書に明確に記載してもらうには、精神科や心療内科の方が適していることが多いでしょう。
- その他専門科: 特定の身体症状(例:皮膚科的な症状、消化器系の症状など)が顕著な場合は、それぞれの専門科を受診することも考えられます。
【医療機関選びのポイント】
- 通いやすさ: 継続的な治療や相談が必要になる場合もあるため、自宅や職場から通いやすい場所にあるかを確認しましょう。
- 医師との相性: 医師に正直に話せるかどうか、信頼できると感じるかどうかも大切です。初診で合わないと感じたら、他の医療機関を検討しても構いません。
- 職場の近くは避けることも検討: 職場の近くの医療機関だと、同僚などに会ってしまうリスクがあります。プライバシーを考慮して、少し離れた場所を選ぶのも一つの方法です。
- 産業医との連携: 会社の産業医に相談し、適切な医療機関を紹介してもらうことも可能です。ただし、産業医も会社側の人間であるため、情報共有の範囲などについては慎重に判断が必要です。産業医の役割については、産業医向けに作成された職場環境評価の基準なども参考になります。
まずは予約を入れる際に、「パワハラが原因で心身の不調を感じており、診断書を検討しています」といった形で相談内容を伝えてみると、受付の対応などで病院の雰囲気を把握できることがあります。
医師への伝え方と診察の流れ
診察時には、医師にあなたの状況を正確に伝えることが非常に重要です。診断の精度や、診断書に記載される内容に影響するためです。
- 予約時の相談: 可能であれば、予約時に「パワハラによる体調不良で受診したい」「診断書の発行をお願いする可能性がある」ということを伝えておくとスムーズです。
- 診察前の準備:
- パワハラの具体的な内容を整理: いつ、誰から、どのようなパワハラ(暴言、暴力、嫌がらせ、過酷なノルマ、無視など)を受けたのか、具体的なエピソードや発言内容、頻度などをメモにまとめておくと、診察時に伝えやすくなります。
- 体調の変化を記録: パワハラが始まってから、いつ頃からどのような体調の変化(不眠、食欲不振、気分の落ち込み、動悸、頭痛など)が現れたのか、その症状によって日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを具体的に記録しておきましょう。
- 診断書が必要な目的を伝える: 休職のため、会社に提出するため、労災申請のためなど、診断書が必要な目的を明確に伝えましょう。
- 診察時の伝え方:
- 率直に話す: 恥ずかしがらず、医師に正直にパワハラの状況やそれによって感じている苦痛、体調の変化を伝えましょう。
- 具体的なエピソードを話す: 事前にまとめたメモを見ながら、具体的なエピソードを交えて話すと、医師も状況を把握しやすくなります。「〇月〇日頃から、△△さんから□□と言われるようになり、その頃から夜眠れなくなりました」など、時期や人物、具体的な内容を伝えるように心がけましょう。
- パワハラと体調の関連性を伝える: 「あの出来事があってから、この症状が出始めたように思います」「職場に行くのが怖くて、朝起きるのが辛いです」など、パワハラと体調不良の関連性を感じていることを伝えましょう。
- 診断書が必要な理由を改めて伝える: 診断書が必要な理由(例:休職を考えている、会社に現状を理解してもらいたいなど)を再度伝えます。
医師はあなたの話を聞き、必要に応じて問診や検査(血液検査、心理検査など)を行い、総合的に診断を下します。診断が確定したら、診断書の発行が可能か、どのような内容で記載できるかなどを医師と相談します。
診断書にかかる費用と期間(即日発行は可能?)
診断書の発行にかかる費用や期間は、医療機関や診断書の種類によって異なります。
- 費用: 診断書の費用は保険適用外となることが多く、一般的に数千円から1万円程度です。医療機関によって料金設定が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
- 発行期間: 診察を受けた当日に即日発行してもらえる場合もあれば、診断に時間を要したり、医師が他の業務で多忙であったりするため、数日から1週間程度かかる場合もあります。診断書に記載してほしい事項が多い場合や、複雑な病状の場合は、さらに時間がかかることもあります。
【即日発行について】
診察を受けたその場で診断書を作成してもらうことも不可能ではありませんが、医師があなたの状況を十分に把握し、適切な診断を下した上で診断書を作成するには、ある程度の時間が必要です。特に、パワハラと体調不良の因果関係について医師の意見を記載してもらいたい場合などは、慎重な判断が伴うため、即日発行が難しいケースが多いでしょう。
もしお急ぎの場合は、診察時にその旨を医師に伝え、いつ頃発行可能か確認するようにしましょう。ただし、診断書の信頼性を確保するためにも、医師の判断に委ねることが重要です。
診断書に記載される病名

パワハラによって心身に不調をきたした場合、診断書には医学的な診断名が記載されます。パワハラが原因となりやすい代表的な病名と、病名以外の記載事項について解説します。
パワハラが原因となりやすい精神疾患(適応障害など)
パワハラのような強いストレス要因が継続的に作用することで発症しやすい精神疾患には、以下のようなものがあります。
- 適応障害: 特定のストレス要因(この場合はパワハラ)に反応して、抑うつ気分、不安、不眠、イライラ、体調不良などの症状が現れ、社会生活や職業生活に支障をきたす状態です。ストレス要因がなくなれば改善することが多いとされます。パワハラによる診断書で最も多く見られる病名の一つです。
- うつ病: 適応障害よりも深刻な気分の落ち込みや意欲の低下が続き、日常生活全般に大きな支障が出る状態です。不眠、食欲不振、倦怠感、自殺念慮などの症状を伴うことがあります。パワハラが発症の引き金になったり、症状を悪化させたりすることがあります。
- 不安障害(全般性不安障害、パニック障害など): 過剰な不安や心配が続き、様々な身体症状(動悸、息苦しさ、震えなど)を伴う状態です。パワハラによるストレスが不安障害を引き起こすことがあります。
- 不眠症: 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、眠りが浅いなど、睡眠に関する問題が続く状態です。ストレスは不眠の大きな原因となります。
- 身体表現性障害(例:心身症): ストレスが原因で、特定の臓器や器官に身体的な症状が現れる状態です(例:ストレス性胃炎、過敏性腸症候群、緊張型頭痛など)。内科で診察を受けた場合、これらの病名が記載されることがあります。
これらの病名以外にも、個々の症状や医師の判断によって、様々な診断名が記載される可能性があります。重要なのは、これらの病名が「パワハラという外部からの強いストレスによって引き起こされた可能性が高い」と医師が判断していることです。
病名以外の記載事項(診断期間、意見など)
診断書には、病名以外にもいくつかの重要な情報が記載されます。
- 患者氏名、生年月日
- 傷病名(診断名)
- 現在の病状:具体的な症状や、日常生活・職業生活への影響などが記載されます。
- 診断年月日
- (医師が判断した)病状の開始時期:パワハラが始まった時期と一致していると、因果関係を示す上で有利になります。
- 治療期間または診断期間:現時点での病状がいつまで続く見込みか、または診断書の発効日からどのくらいの期間の診断となるかが記載されます。休職する場合などは、この期間が重要になります。
- 就労の可否または療養の必要性:「休業(休職)を要する」「通勤は可能だが、業務内容の配慮が必要」など、就労に関する医師の判断が記載されます。
- 医師の意見・備考欄:ここに、医師が診察を通じて感じた「パワハラ(職場環境)が体調不良の原因である可能性が高い」といった意見を記載してもらえると、診断書の証拠能力が格段に向上します。ただし、医師が医学的に断定できない場合は記載が難しいこともあります。診察時に、パワハラとの関連性を強く感じていることを具体的に伝え、記載の可能性について相談してみましょう。
- 医療機関名、医師名、署名、捺印
診断書を受け取ったら、記載内容に不備がないか、必要な情報(特に病名、就労に関する意見、可能であれば医師の意見)が記載されているか確認しましょう。
パワハラによる心身の不調と診断書の因果関係

パワハラの被害を訴え、会社に責任を認めさせたり、損害賠償や労災認定を求めたりする上で、パワハラと心身の不調との間に医学的な因果関係があることを証明することが最も重要かつ難しいポイントの一つです。診断書は、この因果関係を示すための有力な証拠となります。
因果関係が重要な理由と証明の難しさ
なぜ因果関係の証明が重要なのでしょうか?
- 会社の責任追及: 会社がパワハラによってあなたの心身の健康を害した責任を負うのは、パワハラ行為と病状との間に因果関係が認められるからです。因果関係が証明できなければ、「あなたの体調不良は別の原因によるものではないか」と会社に反論される可能性があります。
- 損害賠償請求: 精神的苦痛に対する慰謝料や、休職による減収などの損害賠償を請求する場合、その損害がパワハラによって生じたことを証明する必要があります。
- 労災認定: パワハラによる精神疾患が労働災害として認められるためには、業務上の強いストレス(パワハラ)によって発病したと判断される必要があります。これも因果関係の証明が鍵となります。労働災害認定のための具体的な審査基準は、厚生労働省によって定められています。
しかし、因果関係の証明は容易ではありません。なぜなら、心身の不調にはパワハラ以外にも、元々の健康状態、家庭環境、他のストレス要因など、様々な要素が影響し得るからです。「パワハラだけが原因である」と医学的に断定することは難しく、多くの場合は「パワハラが主要な原因である」「パワハラが病状を悪化させた」といった形で判断されます。
医師に因果関係を記載してもらうためのポイント
診断書においてパワハラと病状の因果関係を示すためには、診察時に医師に以下の点を丁寧に伝えることが重要です。
- パワハラの具体的な内容と深刻さ: どのようなパワハラ行為(例:人格否定、長時間の叱責、隔離、過酷な業務強要など)が、どのくらいの頻度、どのくらいの期間行われたのかを具体的に説明します。その行為があなたにとってどれだけ精神的に大きな負担であったかを伝えます。
- 体調の変化の時期とパワハラ開始時期の関連: パワハラが始まった時期と、体調不良の症状が現れ始めた時期が一致していることを明確に伝えます。「パワハラが始まってから、急に眠れなくなった」「〇月頃のパワハラの後から、会社のことが頭から離れなくなり、食欲がなくなってきた」など、時間的な関連性を具体的に示します。
- パワハラ以外のストレス要因の有無: パワハラ以外にも大きなストレス(例:家族の病気、経済的な問題など)がある場合は、正直に医師に伝えましょう。その上で、「パワハラが最も大きなストレスであり、他のストレス要因だけではこのような病状にはならなかったと思う」といった形で、パワハラの突出した影響を伝えます。
- パワハラによる具体的な影響: パワハラによって、仕事のパフォーマンスが著しく低下した、趣味や楽しみに関心がなくなった、引きこもりがちになったなど、日常生活や社会生活にどのような具体的な支障が出ているかを伝えます。
- 医師への依頼: 診察の終わりに、「この体調不良はパワハラが原因だと強く感じています。診断書に、職場での出来事(パワハラ)が原因である可能性について、先生のご意見を記載していただけないでしょうか」と、丁寧に依頼してみましょう。
医師は、あなたの訴え、診察所見、必要に応じて検査結果などを総合的に判断し、医学的な知見に基づいて因果関係について判断します。すべてのケースで因果関係について明確な記載が得られるわけではありませんが、詳細な情報提供は医師の判断の一助となります。
また、診断書に「業務上のストレスが原因と考えられる」といった記載があったとしても、最終的に会社や裁判所、労働基準監督署が因果関係を認めるかどうかは、診断書以外の証拠や状況全体を考慮して判断されることを理解しておきましょう。
診断書を会社や法的手続きで活用する方法

取得した診断書は、あなたの状況を改善し、失われた権利を回復するための様々な場面で活用できます。具体的な活用方法について解説します。
会社への提出と交渉(休職手続き含む)
パワハラ診断書を会社に提出することは、パワハラの事実とその結果生じた体調不良の深刻さを会社に認識させるための有効な手段です。
- パワハラの停止と改善要求: 診断書を添付し、会社に対してパワハラ行為の即時停止、加害者への適切な処分、配置転換などの再発防止策を講じるよう文書で求めましょう。診断書があることで、あなたの訴えが単なる感情論ではなく、医学的な根拠に基づいていることを示せます。
- 休職手続き: 医師から休職が必要と判断された場合、診断書は休職手続きに不可欠です。会社所定の休職届に診断書を添付して提出します。診断書には休職期間や療養が必要である旨が明記されている必要があります。
- 業務内容や勤務時間の配慮: 休職までは必要ないが、現在の業務を続けることが難しい場合、診断書を提出して業務内容の変更や、短時間勤務、時差出勤などの配慮を求めることができます。診断書に医師の意見として「業務内容の軽減」「特定の人物との接触を避ける配慮」などが記載されていると、会社への要求が通りやすくなります。
会社に診断書を提出する際は、直接手渡しするのではなく、内容証明郵便などを利用して記録に残る形で送付すると、後々の証拠として残せるためより確実です。また、提出前にコピーを取っておくことを忘れずに行いましょう。
労働審判や訴訟での証拠(訴える場合)
パワハラ問題を解決するために、労働審判や訴訟といった法的手続きを選択する場合、診断書は損害賠償請求の根拠となる重要な証拠となります。
- 被害の深刻さの証明: 診断書に記載された病名や症状、診断期間は、パワハラによってあなたが受けた精神的・身体的苦痛の程度を示す証拠となります。病状が重いほど、パワハラの悪質性や影響の大きさを主張しやすくなります。
- 因果関係の立証: 診断書にパワハラと病状の因果関係を示唆する医師の意見が記載されている場合、パワハラがあなたの体調不良の主要な原因であることを示す有力な証拠となります。他の客観的証拠と組み合わせて提出することで、裁判官や労働審判委員会に対して、因果関係の存在を強く訴えることができます。
- 休業損害の請求: 休職せざるを得なくなった場合、その期間の給与の減少分(休業損害)を会社に請求することができます。診断書は、休職が必要であったこと、その期間が医学的に妥当であったことを証明する根拠となります。
ただし、法的手続きにおいては、診断書だけでなく、パワハラの具体的な言動を記録した証拠(録音、メールなど)、被害を受けた状況を記した陳述書、目撃者の証言など、他の証拠も組み合わせて提出する必要があります。診断書はあくまで医学的な側面からの証明であり、パワハラ行為そのものの証明には別の証拠が必要となるからです。
労災申請における診断書の役割
パワハラによる精神疾患などが労災として認定されるためには、労働基準監督署に対して、パワハラが原因で病気を発症したことを証明する必要があります。診断書は、この労災申請において不可欠な書類です。
労災申請では、心理的負荷による精神障害の認定基準に基づき、業務による強い心理的負荷(この場合はパワハラ)と精神疾患の発病との間の因果関係が判断されます。
- 病名の証明: 診断書に記載された精神疾患の病名(例:適応障害、うつ病など)は、労災認定基準で対象となる疾患であることを示します。
- 発病時期の証明: 診断書に記載された病状の開始時期は、パワハラによる強い心理的負荷を受けた時期と一致しているかどうかが確認されます。
- 医師の意見: 可能であれば、診断書に「業務上の強い心理的負荷(パワハラ)が発病の原因と考えられる」といった医師の意見が記載されていると、労災認定において非常に有利になります。
- 病状の経過: 診断書に記載された病状の重さや経過も、認定審査の際に考慮されます。
労災申請の際には、診断書の他にも、パワハラの具体的な内容や期間、それによって受けた心理的負荷の程度を詳細に記した書類(申立書や調査に対する回答など)を提出する必要があります。労働基準監督署の担当官による事実確認も行われます。診断書は、あくまで医学的な側面から労災の可能性を示唆するものであり、認定にはパワハラ行為そのものの立証も必要です。
労災申請は手続きが複雑な場合があるため、不安な場合は労働組合や弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
慰謝料請求と診断書
パワハラによる慰謝料は、パワハラによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。慰謝料の金額を算定する上で、診断書は被害の程度を客観的に示す重要な証拠となります。
- 診断された病名と病状: うつ病などの精神疾患と診断され、症状が重いほど、パワハラによる精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料額が高くなる傾向があります。適応障害でも、休職を余儀なくされたり、長期間の治療が必要であったりするなど、病状が深刻であれば慰謝料額に影響します。
- 診断期間・治療期間: 病状が長期間続いている場合や、継続的な治療が必要である場合も、苦痛が大きかったとみなされ、慰謝料額に影響します。
- 休職の有無と期間: パワハラが原因で休職した場合、休職期間の長さも慰謝料額を判断する際の考慮要素となります。診断書は休職の必要性を医学的に証明します。
- 医師の意見: 診断書にパワハラと病状の因果関係や、病状の深刻さに関する医師の意見が記載されていると、慰謝料請求の根拠としてより強力になります。
ただし、慰謝料額は、パワハラの具体的な内容(回数、期間、態様など)、加害者の役職、会社の対応、被害者の年齢・役職など、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。診断書はその中の重要な要素の一つですが、それだけで金額が決まるわけではありません。適切な慰謝料額を請求するためには、弁護士に相談することをお勧めします。
パワハラにおける診断書に関する注意点

診断書を取得し、活用する際には、いくつかの注意点があります。
診断書取得のタイミング
パワハラによる心身の不調を感じ始めたら、できるだけ早い段階で医療機関を受診し、診断書を取得することを検討しましょう。
- 体調が悪化してから: 我慢せずに、体調不良を感じたらすぐに受診することが大切です。症状が軽いうちに受診することで、早期の回復につながる可能性が高まります。また、症状が悪化してから診断書を取得することで、パワハラの継続的な影響を証明しやすくなります。
- パワハラが続いている間: パワハラを受けている最中に診断書を取得することで、「現在進行形でパワハラによって苦しんでいる」という状況を証明できます。
- 退職前: 退職後に医療機関を受診した場合、病状の原因が「退職」というストレス要因である可能性も否定できなくなります。パワハラが原因であることを明確にするためには、退職前に受診し、診断書を取得しておくことが望ましいです。
- 証拠集めと並行して: 診断書取得と並行して、パワハラの具体的な証拠集め(録音、メール保存、日記記載など)も進めましょう。両者を揃えることが、後の交渉や手続きにおいて非常に強力な武器となります。
タイミングを逃すと、パワハラと体調不良の因果関係を証明することが難しくなる可能性があります。
会社への伝え方
診断書を会社に提出する際は、どのように伝えるかも重要です。
- 提出の目的を明確に: ただ診断書を提出するだけでなく、「パワハラによる心身の不調のため、休職させて頂きたく存じます」「パワハラによる体調不良につき、業務内容の変更をお願いしたく、診断書を提出いたします」など、診断書提出の目的を明確に伝えましょう。
- 誰に提出するか: 診断書は、通常、直属の上司ではなく、人事部やハラスメント相談窓口、または会社の代表者宛に提出します。パワハラ加害者である上司に直接提出するのは避けましょう。
- 書面で提出し記録を残す: 口頭で伝えるだけでなく、診断書を添付した書面を作成し、内容証明郵便などで送付することで、提出した日時と内容の記録を残せます。会社側が「受け取っていない」と主張するのを防ぐためです。
- 感情的にならない: 診断書を提出する際、感情的にならず、冷静に、そして毅然とした態度で臨むことが大切です。あなたの主張に客観性と説得力を持たせるためです。
休職したくない場合の対応
パワハラによる体調不良があっても、経済的な理由などから休職したくないと考える方もいるかもしれません。診断書は、休職以外の目的でも活用できます。
- 配置転換や異動の要望: 診断書を提出し、パワハラ加害者から離れるための配置転換や部署異動を会社に要望できます。診断書に医師の意見として「特定の人物との接触を避ける必要がある」といった記載があれば、会社も配慮せざるを得ないでしょう。
- 業務内容の変更や軽減: 現在の業務内容や業務量が体調不良の原因となっている場合、診断書を提出して業務負担の軽減や内容の変更を求めることができます。
- 労働時間の短縮: 体力的に厳しい場合、診断書を提出して時短勤務などを相談できます。
- パワハラ対策の強化要望: 診断書を提出し、会社に対してパワハラ防止研修の実施や相談体制の強化など、職場環境全体の改善を求める際の根拠とすることができます。
診断書は「就労不能=休職」を意味するだけでなく、「就労には一定の配慮が必要」といった医師の意見を記載してもらうことも可能です。医師とよく相談し、あなたの希望する働き方に合わせた内容で診断書を作成してもらえるか確認しましょう。
パワハラに関する相談先

パワハラ被害や診断書について一人で悩まず、適切な相談先を利用することが重要です。様々な相談先があり、それぞれの得意分野が異なります。
| 相談先 | 主な役割・できること |
|---|---|
| 弁護士 | 法的な専門家。パワハラの違法性の判断、会社や加害者への損害賠償請求、交渉、訴訟手続きの代理。証拠集めのアドバイス。法的な解決や強力な交渉が必要な場合。 |
| 労働組合(ユニオン) | 労働者の権利を守るための団体。会社への団体交渉の申し入れ、労働条件や職場環境の改善要求を会社に行う。個人で加入できる合同労組(ユニオン)もある。 |
| 精神科医・心療内科医 | 心身の不調に対する診断と治療、診断書の発行、病状に関する医学的なアドバイス。体調の回復を優先する場合や診断書取得が目的の場合。 |
| 産業医・産業保健師 | 会社に所属する医師・保健師。労働者の健康管理、職場環境改善に関するアドバイス。会社内の窓口だが、会社側の人員でもあるため、情報共有の範囲に注意が必要。 産業医向けに作成された職場環境評価の基準なども参考に。 |
| 労働基準監督署 | 労働基準法に基づき、労働者の権利を守る公的機関。労働基準法違反に関する相談・是正指導。パワハラそのものへの直接的な介入は限定的だが、労働時間や安全配慮義務違反に関連する場合は相談可能。労災申請の窓口。 労働基準監督署の所在地などを参考。 |
| 総合労働相談コーナー | 各都道府県労働局に設置された公的な相談窓口。労働問題全般に関する相談に対応。専門の相談員が助言や情報提供を行う。必要に応じて紛争解決援助やあっせんの案内も。まずはどこに相談すべきか迷ったら。 総合労働相談コーナー所在地など参考。 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 経済的に余裕がない方向けに、無料の法律相談や弁護士費用の立替制度を提供する公的機関。弁護士に相談したいが費用が心配な場合。 法テラス公式サイトを参考。 |
| 各自治体の相談窓口 | 自治体によっては、労働問題やメンタルヘルスに関する無料相談窓口を設けている場合があります。 |
これらの相談先は、診断書を取得する前段階での状況整理やアドバイス、診断書取得後の活用方法について具体的な支援を提供してくれます。複数の相談先を組み合わせて利用することも有効ですし、厚生労働省のウェブサイトなど、公的な情報も確認してみる価値があります。
パワハラでの診断書取得前に知っておくべきこと

パワハラによる心身の不調に苦しんでいる方にとって、診断書は状況を改善するための一歩となり得る重要なツールです。しかし、その有効性には限界があり、万能ではないことを理解しておくことが大切です。この記事で解説した重要なポイントをまとめます。
- 診断書は、パワハラによって体調が悪化したことを医学的に証明する証拠となります。休職手続き、会社への交渉、法的手続き、労災申請など、様々な場面で活用できます。
- 診断書が証拠として認められるには、信頼できる医療機関・医師による具体的な病名、症状、診断期間などの記載が必要です。
- 診断書は「パワハラによる結果」を証明しますが、「どのようなパワハラ行為があったか」を直接証明するものではありません。パワハラそのものを立証するには、録音、メール、業務日報、目撃者の証言など、他の客観的な証拠を併せて収集することが不可欠です。法的手続きでの証拠収集については、紛争解決手続きにおける証拠収集の要領も参考になります。
- 最も重要かつ難しいのは、パワハラと心身の不調の間の因果関係を証明することです。診断書に医師の意見として因果関係を示唆する記載があると非常に有利ですが、それだけで認定されるわけではありません。診察時には、パワハラと体調変化の関連性を具体的に医師に伝えましょう。労災認定基準についても厚生労働省の資料を確認できます。
- 診断書を取得する際は、精神科・心療内科を中心に、信頼できる医療機関を選びましょう。診察時には、パワハラの具体的な内容や体調の変化、診断書の目的を正確に伝えることが重要です。費用は通常保険適用外で数千円~1万円程度、発行には数日から1週間程度かかる場合があります。
- 診断書は休職だけでなく、配置転換や業務軽減など、休職以外の目的で会社に配慮を求める際にも活用できます。
- パワハラによる体調不良を感じたら、できるだけ早い段階で医療機関を受診し、診断書を取得することをお勧めします。特に退職前に取得しておくことが望ましいです。
- 診断書を会社に提出する際は、書面で目的を明確に伝え、記録が残る方法(内容証明郵便など)で送付しましょう。
- 一人で抱え込まず、弁護士、労働組合、医療機関、公的な相談窓口など、様々な相談先を積極的に利用しましょう。
診断書は、あなたの苦しみを医学的に裏付け、解決に向けた具体的な行動を起こすための第一歩となります。診断書を適切に取得・活用し、パワハラ問題の解決と心身の回復を目指してください。
会社側のパワハラ対策については、企業向けの予防・再発防止策実践ガイド(厚生労働省)も参考にしてください。また、パワハラの定義や判断基準の詳細は、厚生労働省の公式文書をご参照ください。
【免責事項】
この記事の情報は、一般的な情報提供を目的としており、特定の個人に対する医学的アドバイスや法的な助言を行うものではありません。個々の状況については、必ず専門家(医師、弁護士など)に相談してください。記事内容によって生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
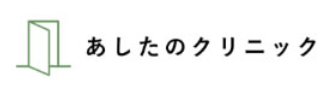

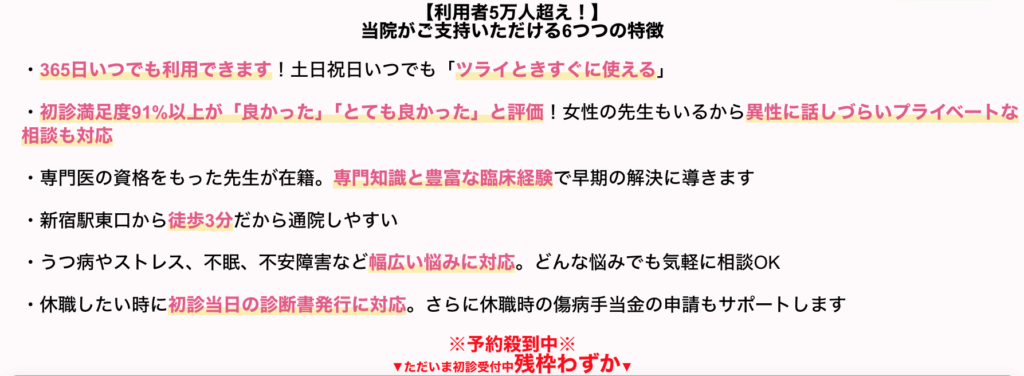



コメント