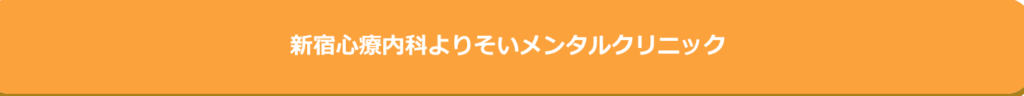
うつ病と診断され、現在の仕事の継続が難しくなったとき、「退職」という選択肢が頭をよぎる方もいるかもしれません。心身ともに疲弊している中で、退職に向けた手続きや会社とのやり取りをスムーズに進めるのは、大きな負担に感じられるでしょう。
この記事では、うつ病で退職を考えている方が、落ち着いて、そして後悔なく退職を進められるように、具体的な退職までの流れ、必要な手続き、会社への伝え方、さらには退職後の生活や利用できる支援について詳しく解説します。ご自身のペースで情報を確認し、回復に向けた一歩を踏み出すための参考にしてください。
うつ病で退職する流れ

うつ病を理由に退職を検討する際は、感情的にならず、段階を踏んで進めることが大切です。計画的に進めることで、退職後の生活への不安を軽減し、回復に専念できる環境を整えやすくなります。まずは全体の流れを把握しましょう。
退職までの主な流れは以下のステップで進めることが一般的です。
- 退職前に病状や選択肢を確認する: 医師の診断に基づき、現在の病状や退職以外の可能性を検討します。
- 会社へ退職意思を伝える準備: 就業規則の確認、退職時期の検討、誰に伝えるかを決めます。
- 会社へ退職を伝える: 上司にアポイントを取り、退職の意思と理由を伝えます。必要に応じて診断書を提出し、退職届を提出します。
- 退職日までの手続きと引き継ぎ: 業務の引き継ぎ、有給休暇の消化、会社からの貸与物返却などを行います。
- 退職後の生活に向けた手続き: 健康保険、年金、失業保険などの公的手続きを行います。
これらのステップを、ご自身の体調と相談しながら、一つずつ進めていきましょう。
うつ病と診断されたら退職前に確認すること
うつ病と診断されたからといって、すぐに退職しなければならないわけではありません。まずは冷静に状況を把握し、ご自身の病状や会社で利用できる制度を確認することが重要です。
医師の診断と診断書の取得
うつ病であるという診断は、今後の進め方を考える上で非常に重要です。まずは、精神科医や心療内科医から正式な診断を受けましょう。
診断を受けた際には、主治医に現在の病状、仕事への影響、今後の見通しなどについて詳しく相談してください。そして、会社へ提出するための診断書の発行を依頼します。
診断書には、病名、現在の病状、仕事への影響(例: 休養が必要、業務内容の変更が必要、特定の業務遂行が困難など)、療養期間の見込みなどが記載されます。この診断書は、会社に病状を理解してもらい、今後の対応を検討する上で非常に有効な客観的証拠となります。特に、休職制度の利用や退職する際の理由として、診断書があるかどうかは会社の対応に大きく影響する可能性があります。
診断書の内容について、会社にどの程度まで開示するかはご自身で判断できますが、病状の深刻さや仕事への影響を正確に伝えるためには、ある程度の詳細が記載されている方が望ましいでしょう。医師と相談しながら、必要十分な内容の診断書を作成してもらってください。
病状から退職の必要性を検討
診断書を取得したら、改めてご自身の病状と現在の仕事内容を照らし合わせ、退職が本当に最善の選択肢なのかを検討します。
うつ病の症状には波があり、回復の過程で改善することもあります。現在の仕事環境が病状を悪化させている明確な原因である場合や、症状が重く働くことが極めて困難である場合は、退職が回復への近道となることもあります。
一方で、仕事内容の一部を変更したり、働く時間を短縮したりすることで、仕事を続けながら治療することも可能なケースもあります。また、職場環境に問題がある場合は、部署異動や配置転換によって状況が改善する可能性もゼロではありません。
この検討は、ご自身だけで抱え込まず、必ず主治医と十分に話し合って行ってください。医師は医学的な見地から、現在の病状でどのような働き方が可能か、休養期間はどの程度必要かなど、専門的なアドバイスをしてくれます。会社の産業医やカウンセラーに相談できる環境があれば、そちらも活用を検討しましょう。
退職以外の選択肢(休職など)を考慮する
退職を考える前に、会社にどのような制度があるかを確認し、退職以外の選択肢を検討することが非常に重要です。特に、休職制度は、退職せずに病気療養に専念できる制度として多くの会社に導入されています。
休職制度とは、従業員が傷病などの理由により長期にわたって労務を提供できない場合に、雇用契約を維持したまま一定期間就業義務を免除する制度です。休職期間中も会社に籍を置いたまま治療に専念できるため、回復後に元の職場に復帰できる可能性があります。
休職期間中には、会社の給与は支払われないことが一般的ですが、健康保険から傷病手当金を受給できる場合があります。傷病手当金については後述しますが、これにより休職期間中の一定の生活費を賄うことが可能です。
その他、会社によっては、短時間勤務制度や配置転換、業務内容の軽減といった配慮を受けられる可能性もあります。
これらの制度を利用できるかどうか、また利用した場合の条件(期間、給与、復職のルールなど)は、会社の就業規則によって定められています。まずは就業規則を確認し、人事担当者や直属の上司に相談してみましょう。
休職のメリットは、雇用関係を維持したまま療養に専念できる点です。回復すれば元の職場に戻れる安心感があります。デメリットとしては、休職期間には上限があること、必ずしも復職できる保証はないことなどが挙げられます。
退職は雇用関係を解消するため、再就職には改めて就職活動が必要になります。しかし、病状が回復せず、元の職場で働くことが困難な場合や、仕事内容・職場環境そのものが病気の原因となっている場合は、環境を根本的に変えるために退職が有効な手段となることもあります。
どちらの選択肢が良いかは、ご自身の病状、回復の見込み、会社の制度、経済状況、将来のキャリアプランなどを総合的に考慮して判断する必要があります。主治医や家族ともよく相談し、ご自身にとって最も良い方法を選んでください。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

会社へ退職意思を伝えるための準備

退職以外の選択肢を検討した結果、やはり退職が最善であると判断した場合、いよいよ会社に退職の意思を伝える準備を始めます。この段階での準備が、スムーズな退職交渉につながります。
就業規則で退職に関するルールを確認
会社には、退職に関するルールを定めた就業規則があります。まずはご自身の会社の就業規則を確認しましょう。
特に確認すべき点は以下の2点です。
- 退職希望日のどのくらい前までに退職の意思表示をする必要があるか:多くの会社では、「退職希望日の1ヶ月前まで」や「2週間前まで」などと定められています。
- 退職届の提出方法や提出先:誰に、どのような形で提出する必要があるかを確認します。
民法上は、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています(民法第627条)。しかし、就業規則にこれと異なる定めがある場合、まずは会社の就業規則に則って手続きを進めるのが一般的です。ただし、就業規則の定めが民法の規定よりも従業員に不利な場合は、民法の規定が優先されることもあります。
うつ病で退職する場合、病状によっては就業規則に定められた期間よりも早く退職したいと希望することもあるでしょう。その場合でも、まずは会社のルールを把握しておくことが交渉の出発点となります。
退職時期は医師や会社と相談して決める
退職時期を決める際は、ご自身の病状、医師の意見、業務の引き継ぎにかかる時間、会社の都合などを総合的に考慮する必要があります。
理想的には、主治医と相談し、療養に必要な期間を踏まえた上で、無理のないスケジュールを立てることが大切です。病状が不安定な中で無理に引き継ぎを行ったり、会社との交渉を急いだりすることは、かえって病状を悪化させることにもなりかねません。
会社に対しては、就業規則に基づいた期間を基本としながらも、病状を説明し、ご自身の体調を最優先にした退職時期について相談してみましょう。診断書を提示することで、病状の深刻さを理解してもらいやすくなります。有給休暇の消化期間も考慮に入れて、最終的な退職日を決めます。
スムーズな退職のためには、会社との円満な話し合いが不可欠です。一方的に期日を決めるのではなく、可能な範囲で会社の都合も考慮しつつ、現実的な退職時期を設定することを目指しましょう。
誰に退職の意思を伝えるか
退職の意思を伝える相手は、多くの場合、直属の上司となります。まずは、上司に「ご相談したいことがあります」と伝え、二人きりで落ち着いて話せる時間を作ってもらうように依頼しましょう。
人事担当者やさらに上の役職者に直接伝えるのが適切かどうかは、会社の組織構造や人間関係によって異なりますが、まずは一番身近な上司に伝えるのが一般的なマナーとされています。上司が不在の場合や、パワハラなどにより上司に伝えにくい事情がある場合は、人事部や会社の相談窓口に連絡することを検討してください。
伝える相手を決めたら、事前に話す内容を整理しておきましょう。感情的にならず、冷静に、しかし真摯に退職の意思と理由を伝えることが重要です。
会社へ退職を伝える方法と注意点

退職の意思を会社に伝えることは、精神的に大きな負担となるステップかもしれません。しかし、しっかりと準備をして臨めば、必要以上に不安を感じることはありません。
直属の上司にアポイントを取る
まずは直属の上司に「ご相談したいことがありますので、少々お時間をいただけないでしょうか」などと伝え、二人きりで話せる機会を設けてもらいましょう。メールや電話で伝えるのではなく、直接会って話すのが丁寧な方法とされています。会議室や応接室など、他の社員に聞かれない場所で話すことが望ましいです。
相談の時間を設けてもらったら、改めて感謝の気持ちを伝え、切り出しにくい話であることを前置きしつつ、退職の意思を伝えます。
伝え方のポイント(うつ病を理由にするか、診断書を提出するか)
退職の理由を伝える際、うつ病であることを正直に伝えるかどうかは悩ましい問題です。しかし、うつ病により就業が困難になったという理由であれば、正直に伝えることにはメリットがあります。
うつ病を理由に伝えるメリット:
病状による退職の必要性を会社に理解してもらいやすい。
診断書を提出することで、理由に客観性が生まれる。
退職時期や引き継ぎについて、体調への配慮を求めやすくなる。
退職理由が「正当な理由のある自己都合退職」として認められ、失業保険の受給において有利になる可能性がある(後述)。
うつ病を理由に伝えるデメリット:
病状やプライベートなことに立ち入られる可能性がある。
会社からの同情や不要な詮索を受ける可能性がある。
多くのケースでは、病状を理解してもらうためにうつ病であることを伝え、診断書を提出することをおすすめします。診断書は、病気が原因で働くことが困難になったという客観的な根拠となり、会社の理解を得る上で強力なツールとなります。
伝え方としては、「現在うつ病の診断を受けており、医師から療養が必要と言われました。現在の体調では業務を続けることが難しいため、誠に勝手ながら、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談に参りました。」などと、冷静に、しかし真摯に伝えましょう。診断書は「医師からの診断書がございますので、よろしければご覧ください」と差し出す形で提出します。
もし、うつ病であることを伏せて退職したい場合は、「一身上の都合により」と伝えることも可能です。ただし、この場合、会社から詳細な理由を聞かれる可能性があり、病状による困難を理解してもらいにくい場合があります。また、失業保険の手続きにおいて不利になる可能性もあります。ご自身の状況と、会社との関係性を考慮して判断してください。
退職届の提出
退職の意思を口頭で伝えた後、会社から退職届の提出を求められます。退職届は、会社に対して退職の意思を正式に伝える書類です。
退職届には、退職日、氏名、所属部署などを記載し、署名・捺印します。退職届のテンプレートはインターネット上にも多数ありますが、会社の指定する書式がある場合はそれに従ってください。
退職届と似た書類に退職願がありますが、両者には違いがあります。
退職願:会社に対して退職を「お願い」する書類です。会社がこれを承認した時点で雇用契約の解除に合意したことになります。原則として、会社が承認するまでは撤回が可能です。
退職届:会社に対して一方的に退職を「届け出る」書類です。原則として、会社が受理した時点で退職の意思表示が完了し、撤回はできません。
一般的には、退職の意思が固まっている場合は退職届を提出します。会社に退職を伝えた後、会社から退職届を提出するように指示されるのが一般的な流れです。
即日退職は可能か?
うつ病の病状が非常に重く、一刻も早く会社に行けない、業務が一切できないという状況の場合、「即日退職」を希望する方もいるかもしれません。
民法上は、期間の定めのない雇用契約の場合、原則として退職希望日の2週間前までに会社に意思表示をする必要があります。これは、会社が後任者の手配や引き継ぎを行うための期間を確保するためです。
しかし、民法第628条には、「やむを得ない事由があるとき」は、いつでも雇用契約を解除できると定められています。「やむを得ない事由」には、病気や怪我により働くことが極めて困難になった場合が含まれると解釈されています。
うつ病が重症化し、業務の遂行が全く不可能であり、かつ症状の回復に相当な時間を要すると医師が診断した場合、これは「やむを得ない事由」に該当し、即日退職が認められる可能性があります。この場合も、医師の診断書が強力な根拠となります。
ただし、即日退職は会社の就業規則に反する場合が多く、会社との話し合いが必要不可欠です。一方的に「今日で辞めます」と伝えるのではなく、病状の深刻さを伝え、即日退職を希望する理由を丁寧に説明し、会社と合意の上で退職日を決定することが望ましいです。会社が即日退職に応じない場合でも、診断書を提出することで、せめて2週間の期間を短縮するなどの交渉ができる可能性があります。
合意が得られない場合は、退職代行サービスの利用も選択肢の一つとなりますが、まずは会社と誠実に話し合う姿勢が重要です。
会社から引き止められた場合の対応

退職の意思を伝えた際、会社から引き止められることもあります。「君は必要な人材だ」「もう少し頑張ってみないか」「休職して様子を見よう」などと言われるかもしれません。
引き止められる背景には、人手不足や、これまでの貢献に対する期待などがあるでしょう。しかし、うつ病は十分な休養と治療が必要な病気であり、無理をして働き続けることは病状を悪化させるリスクが高いです。
引き止めにあった場合は、改めて現在の病状で働くことが困難であること、医師からも療養が必要であると診断されていることを丁寧に伝えましょう。感情的にならず、「会社には大変お世話になりましたが、今は心身の回復を最優先に考えたいと思います」などと、穏やかに、しかし退職の意思が固いことを伝え続けることが重要です。
曖昧な態度をとると、会社は「まだ説得すれば翻意するかもしれない」と考えて引き止めを続ける可能性があります。感謝の気持ちを伝えつつも、退職の意思は変わらないことを明確に伝えましょう。診断書を改めて提示することも有効です。
診断書があっても退職を認めてくれない場合
医師の診断書を提出し、うつ病で働くことが困難であることを伝えたにもかかわらず、会社が退職を認めない、あるいは就業規則に定められた以上の期間(例: 1ヶ月前まで)で退職を受け付けないといったケースも稀にあります。
まず、労働者には「退職の自由」があり、期間の定めのない雇用契約であれば、原則として退職の意思表示から2週間が経過すれば退職は成立します(民法第627条)。就業規則で1ヶ月前までの申し出が必要と定められていても、法的には2週間で退職が可能です。ただし、スムーズな手続きのためには、会社の就業規則を尊重し、話し合いで合意を目指すのが望ましいです。
診断書は、病気により働くことが困難であるという「正当な理由」があることを示す強力な証拠です。会社が病状を理解せず、不当に退職を認めない場合は、以下の対応が考えられます。
- 内容証明郵便で退職届を送付する:退職の意思表示をしたことの証拠を残すことができます。就業規則に則り、退職希望日の〇ヶ月前までに送付するのが丁寧ですが、病状が重ければ2週間前の意思表示として送付することも可能です。
- 労働組合や労働基準監督署に相談する:労働組合に加入している場合は相談できます。労働基準監督署は、労働基準法違反に関する相談窓口ですが、退職に関するトラブルについてもアドバイスをもらえる場合があります。
- 弁護士に相談する:会社との交渉を代行してもらったり、法的なアドバイスを受けたりできます。ただし費用がかかります。
- 退職代行サービスを利用する:本人に代わって会社に退職の意思を伝え、退職手続きを代行してくれるサービスです。会社との直接のやり取りを避けられるため、精神的な負担を減らせます。ただし、サービス内容や費用は事業者によって異なります。弁護士が運営しているサービスは法的に安心ですが、費用は高めです。非弁護士が運営するサービスは法的なトラブルになった際に十分な対応ができない可能性があります。利用を検討する際は、慎重に選びましょう。
診断書があれば、病気で働くことが困難な状況は客観的に証明できます。会社が不当な対応をとる場合は、一人で抱え込まず、外部の専門機関に相談することを検討してください。
退職日までに必要な手続き・引き継ぎ
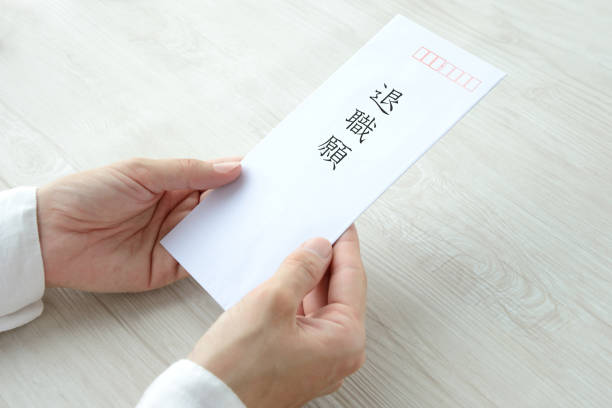
退職日が決定したら、退職日までに必要な手続きや業務の引き継ぎを行います。体調と相談しながら、無理のない範囲で進めましょう。
業務の引き継ぎを丁寧に行う
これまでの業務内容や進行状況を後任者やチームメンバーに引き継ぐ必要があります。可能な範囲で、以下の準備を進めましょう。
- 引き継ぎ資料の作成: 担当業務の一覧、日々の業務内容、担当顧客リスト、進行中のプロジェクトの状況、ファイルや資料の保存場所、よくある問い合わせとその対応方法などをまとめた資料を作成します。
- 口頭での説明: 引き継ぎ資料だけでは分かりにくい点や、口頭で補足すべき点などを後任者に説明します。
- 関係者への挨拶: 関係部署や取引先など、必要に応じて退職の挨拶と後任者の紹介を行います。
うつ病の病状が重く、十分な引き継ぎができない状況である場合は、正直にその旨を会社に伝えましょう。引き継ぎ資料の作成が精一杯であったり、口頭での説明が難しかったりすることもあるかもしれません。会社は、従業員の退職に伴う業務の引き継ぎ体制を整える責任がありますので、できる範囲で協力する姿勢を見せつつ、無理はしないことが最も重要です。
残っている有給休暇を消化する
退職日までに残っている有給休暇があれば、全て消化する権利があります。退職日までの期間と残日数を確認し、計画的に有給休暇を消化しましょう。
有給休暇の消化は、心身の休養にもつながり、退職後の生活準備の時間も確保できます。会社が有給休暇の取得を拒否することは原則として違法ですが、業務の引き継ぎとの兼ね合いで会社から時期の調整を求められることはあります。しかし、退職日までに消化できない有給休暇は消滅してしまうため、基本的には全て消化できるよう会社と調整してください。
もし、有給休暇を消化せずに退職することになった場合でも、買い取りを会社に請求する権利は原則ありません。ただし、会社の就業規則に有給休暇の買い取りに関する定めがある場合や、労使慣行として買い取りが行われている場合は、買い取りを求めることができる可能性もあります。
健康保険証など会社からの貸与物を返却
退職日までに、会社から借りていたものを全て返却する必要があります。
一般的に返却するものとしては、以下のものがあります。
健康保険証
社員証
通勤定期券(会社購入の場合)
社用携帯電話
社用PC
制服や作業着
会社支給の書類や備品
これらの返却物は、退職日までに人事担当者や総務担当者に確認し、漏れがないように全て返却しましょう。
離職票など退職後の必要書類を受け取る
退職後、様々な手続きを行うために会社から受け取る必要がある書類があります。これらの書類は、退職日から一定期間後に会社から自宅へ郵送されることが一般的ですが、いつ頃送付されるか事前に確認しておきましょう。
特に重要な書類は以下の通りです。
- 離職票(雇用保険被保険者離職票):失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きに必要です。通常、退職後10日前後で会社からハローワークへ提出され、その後本人に交付されます。ハローワークへの手続きにはこの書類が必須です。
- 雇用保険被保険者証:雇用保険に加入していたことを証明する書類です。再就職先で提出を求められることがあります。通常、会社が保管していますが、退職時に返却されます。
- 源泉徴収票:その年に会社から支払われた給与と、そこから差し引かれた所得税の金額が記載されています。退職後の年末調整や確定申告、再就職先での手続きに必要です。
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書):国民年金や厚生年金への加入状況を示す書類です。退職後の年金手続きに必要です。
これらの書類は、退職後の生活や次のステップに進むために不可欠です。退職日までに、いつ、どのように交付されるか、人事担当者に必ず確認しておきましょう。
退職後の生活に必要な手続きと支援

会社を退職すると、健康保険や年金の切り替え、失業保険の手続きなど、ご自身で行わなければならない手続きが多く発生します。また、療養に専念するための生活費や、回復後の再就職に向けた支援制度もあります。これらの情報を事前に把握しておくことで、退職後の不安を軽減できます。
健康保険・年金の切り替え手続き
会社員が加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)と厚生年金保険は、退職すると資格を失います。退職後は、以下のいずれかの健康保険に加入する必要があります。
- 国民健康保険:お住まいの市区町村が運営する健康保険です。退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で加入手続きを行います。保険料は前年の所得などに基づいて計算されます。
- 会社の健康保険の任意継続被保険者制度:退職する会社の健康保険に、引き続き最大2年間加入できる制度です。加入するには、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること、退職日の翌日から20日以内に手続きを行うことなどの条件があります。保険料は会社負担分がなくなり、全額自己負担となるため、現役時の約2倍になります。ただし、扶養家族がいる場合は、国民健康保険よりも保険料が安くなる可能性があります。
- 家族の健康保険の被扶養者となる:配偶者や親など、家族が加入している健康保険の扶養に入れる場合があります。扶養に入れる条件は、主として家族の収入で生計を維持しており、自身の年収見込みが130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることなどです。加入者の勤務先の健康保険組合などに申請します。
どの健康保険に加入するのがご自身の状況に最適かは、保険料、扶養家族の有無、将来の収入見込みなどを考慮して検討が必要です。市区町村の窓口や会社の健康保険組合に相談してみましょう。
| 加入する健康保険 | 特徴 | 保険料 | 手続き先・期限 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 誰でも加入できる。保険料は前年の所得等で算出。 | 前年の所得等による。 | 市区町村役場、退職日の翌日から14日以内 |
| 会社の健康保険(任意継続) | 最大2年間継続可能。扶養家族がいる場合は有利な場合も。 | 全額自己負担(現役時の約2倍)。 | 会社の健康保険組合等、退職日の翌日から20日以内 |
| 家族の健康保険(被扶養者) | 家族の扶養に入れる場合。収入要件あり。 | なし(家族の保険料に含まれる)。 | 家族の勤務先の健康保険組合等、退職後速やかに |
年金についても、会社員が加入していた厚生年金保険から、国民年金に切り替える手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。第1号被保険者となり、保険料を自分で納めることになります。ただし、家族の扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続き
雇用保険に加入していた方が、離職後に就職の意思と能力があるにもかかわらず仕事に就けない場合に受け取れるのが、失業保険(雇用保険の基本手当)です。うつ病で退職した場合でも、病状が回復し、働くことができる状態になれば受給資格を得られます。
受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
原則として、離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること。
ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
離職理由が、雇用保険の受給資格者となる要件を満たしていること。
うつ病で退職した場合、失業保険の手続きを行うのは、病状が回復し、働くことができる状態になってからになります。主治医に相談し、「働くことができる」という判断が得られたら、ハローワークで求職の申し込みと失業保険の受給手続きを行いましょう。この際、病気による退職であることを証明するために、医師の診断書が必要になる場合があります。
特定理由離職者として申請するメリット
うつ病による退職は、離職理由が「やむを得ない事由」によるものとして、特定理由離職者に区分される可能性があります。特定理由離職者と認められると、失業保険の受給において以下のメリットがあります。
- 給付制限がない: 自己都合退職の場合、通常7日間の待期期間に加え、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間がありますが、特定理由離職者の場合はこの給付制限がありません。待期期間満了後すぐに基本手当の支給が始まります。
- 所定給付日数が長くなる可能性がある: 特定理由離職者は、会社都合退職者(特定受給資格者)と同等に扱われ、年齢や被保険者期間に応じて、自己都合退職よりも長い期間基本手当を受け取れる場合があります。
うつ病で退職した場合、医師の診断書を提出し、病状が働くことに支障をきたしていたことをハローワークに説明することで、特定理由離職者として認められる可能性が高まります。
自己都合退職との違い
失業保険の受給における自己都合退職と特定理由離職者(会社都合退職と同等)の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 自己都合退職 | 特定理由離職者(うつ病等) |
|---|---|---|
| 給付制限 | あり(2ヶ月または3ヶ月) | なし |
| 給付開始時期 | 待期期間7日+給付制限期間満了後 | 待期期間7日満了後 |
| 所定給付日数 | 短め(被保険者期間に応じて90日〜150日) | 長め(被保険者期間、年齢に応じて90日〜330日) |
| 離職理由 | 自己の都合による退職(例:転職、キャリアアップ) | 正当な理由のある自己都合退職(例:傷病、家族の介護、ハラスメント) |
うつ病による退職の場合、特定理由離職者として申請することで、より早く、より長い期間失業保険を受け取れる可能性が高まります。ハローワークでの手続きの際に、必ず病気による退職であることを伝え、医師の診断書などを提示してください。
傷病手当金の継続受給
休職中に傷病手当金を受給していた方が、退職後も引き続き療養が必要な場合、一定の条件を満たせば退職後も傷病手当金の受給を継続できる場合があります。
退職後に傷病手当金の継続給付を受けるための主な条件は以下の通りです。
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者期間は除く)。
退職日時点で傷病手当金を受給している、または傷病手当金の受給要件を満たしていること(労務不能の状態であること)。
退職日後も、引き続き労務不能の状態であること。
これらの条件を満たす場合、最長で支給開始日から通算して1年6ヶ月の間、傷病手当金を受給できます。これは、被保険者の資格を失った後も、傷病手当金の受給権が継続される制度です。
ただし、傷病手当金は「働くことができない状態」に対して支給されるため、失業保険(働く意思と能力がある状態に対して支給)とは同時に受け取ることはできません。傷病手当金の受給が終了し、病状が回復して働ける状態になったら、改めて失業保険の手続きに進むことになります。
傷病手当金の継続受給の手続きは、加入していた健康保険組合または協会けんぽに対して行います。必要書類や手続き方法については、ご自身の健康保険組合等に確認してください。
障害年金の申請
うつ病が重症化し、日常生活や就労が著しく困難な状態が一定期間続いている場合、障害年金を申請できる可能性があります。障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事に支障が出ている方に対して支給される公的な年金です。
障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金保険から支給される障害厚生年金があります。
- 障害基礎年金:国民年金の被保険者期間中に初診日がある場合などに申請できます。障害等級1級または2級に認定されると支給されます。自営業者、学生、無職の方などが対象となることが多いですが、会社員だった方でも、初診日が厚生年金加入期間中であっても障害基礎年金は対象となり得ます。
- 障害厚生年金:厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合に申請できます。障害等級1級、2級、または3級に認定されると支給されます。会社員などが対象となります。
障害年金を受給するためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件:障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診察を受けた日(初診日)が特定できること。
2. 保険料納付要件:初診日の前日において、一定期間の年金保険料を納めていること、または保険料の免除期間があること。
3. 障害状態要件:初診日から原則として1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)において、法令で定める障害等級に該当する程度の障害状態にあること。
うつ病の場合、初診日を特定することや、精神疾患の特性上、障害状態の評価が難しい場合もあります。申請手続きは複雑で、診断書や病歴申立書など多くの書類が必要です。ご自身での申請が難しい場合は、社会保険労務士(特に障害年金に詳しい社労士)や、お住まいの市区町村の障害年金相談窓口に相談することをおすすめします。
利用できる支援機関・サービス
退職後の療養期間や再就職に向けて、様々な支援機関やサービスを利用できます。一人で悩まず、積極的に活用しましょう。
ハローワーク
失業保険の手続きだけでなく、就職相談や求人情報の提供など、再就職に向けた様々な支援を行っています。うつ病などの病気で退職した方向けの専門窓口を設けているハローワークもあります。病状が回復し、働くことができる状態になったら、まずはハローワークに相談してみましょう。
地域障害者職業センター
障害のある方(精神障害を含む)に対して、職業リハビリテーションや就職に関する専門的な支援を提供しています。職業評価、職業指導、就職準備訓練、職場適応援助など、障害の特性に応じたきめ細やかな支援を受けることができます。うつ病からの回復途上の方や、復職・再就職に不安がある方に特に役立ちます。
転職エージェント・退職代行サービス
転職エージェントは、求職者の希望やスキルに合った求人を紹介し、応募書類の添削や面接対策などのサポートをしてくれる民間のサービスです。病状が回復し、転職活動を行う際に役立ちます。
退職代行サービスは、従業員に代わって会社に退職の意思を伝え、退職に関する手続きを代行するサービスです。うつ病の症状が重く、ご自身で会社と交渉することが困難な場合や、会社が退職を不当に認めない場合などに利用を検討できます。ただし、費用がかかること、サービス内容や信頼性は事業者によって異なることに注意が必要です。弁護士が運営する退職代行は法的な交渉も可能ですが、費用は高めです。非弁護士が運営するサービスは法的なトラブルになった際に十分な対応ができない可能性があります。利用を検討する際は、慎重に選びましょう。
退職後の療養と生活リズムの調整

退職は、うつ病からの回復に向けた重要な一歩です。焦らず、まずは心身の回復に専念しましょう。
退職後は、会社に行く必要がなくなり、生活リズムが崩れやすくなることがあります。しかし、うつ病の回復には規則正しい生活が非常に重要です。可能な範囲で、毎日同じ時間に起床・就寝し、食事を摂るなど、規則的な生活リズムを心がけましょう。
十分な休養を取ることはもちろん大切ですが、完全に引きこもるのではなく、体調が良い日には散歩をしたり、軽い運動をしたり、気分転換になるような活動を取り入れたりすることも有効です。主治医と相談しながら、無理のない範囲で活動量を徐々に増やしていきましょう。
また、社会とのつながりを完全に断ってしまうと、孤立感や不安が増すことがあります。家族や信頼できる友人との交流を大切にしたり、回復者向けの自助グループに参加したりすることも、心の支えになります。
「早く回復して働かなければ」「他の人は頑張っているのに」などと、ご自身を責める必要は全くありません。うつ病は誰でもかかる可能性のある病気であり、治療と休養が必要です。退職を選んだことは、回復を最優先にした正しい選択です。焦らず、ご自身のペースで回復を目指してください。
うつ病での退職に関するよくある質問

うつ病で退職を考えるにあたり、様々な疑問や不安があるかと思います。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
うつ病で退職するときの「辞め方」はどうすれば良いですか?
うつ病で退職する際の「辞め方」としては、以下のステップを踏むことが一般的です。
- 医師の診断を受け、診断書を取得する。
- 就業規則を確認し、退職以外の選択肢(休職など)を検討する。
- 退職を決意したら、直属の上司にアポイントを取り、退職の意思と理由(うつ病であること、診断書があること)を丁寧に伝える。
- 会社と退職時期や引き継ぎについて話し合い、合意形成を目指す。
- 退職届を提出する。
- 退職日までに可能な範囲で引き継ぎを行い、有給休暇を消化する。
- 退職日までに会社からの貸与物を返却し、退職後に必要な書類(離職票、源泉徴収票など)の受け取り方法を確認する。
最も重要なのは、ご自身の体調を最優先にし、無理なく手続きを進めることです。会社に病状を理解してもらうために、診断書を有効活用しましょう。
うつ病で退職すると「末路」はどうなりますか?「後悔」しますか?
うつ病で退職したからといって、「末路」が決まっているわけではありません。退職後の回復に向けた療養、生活の立て直し、そして再就職に向けたステップをどのように進めるかによって、その後の人生は大きく変わります。
退職直後は、収入が不安定になったり、社会とのつながりが一時的に減ったりすることで、不安を感じることもあるかもしれません。しかし、これは一時的なものであり、適切な療養と支援を受けることで、多くの方が回復し、再び社会参加や就労ができるようになります。
退職を「後悔」するかどうかは、その後の状況や個人の感じ方によります。病状が改善せず、経済的に苦しくなった場合は後悔を感じることもあるかもしれません。しかし、多くの場合、うつ病で限界まで追い詰められた状況から、回復のために退職を選んだこと自体は、ご自身の心身を守るための賢明な選択であったと感じる方が多いようです。退職によって心身が回復し、新たな道が開けた場合は、退職を前向きに捉えられるでしょう。
後悔しないためには、退職後の生活計画をしっかり立て、公的な支援制度や医療機関、支援機関を積極的に利用することが大切です。
うつ病で退職することの「デメリット」は何ですか?
うつ病で退職することには、以下のようなデメリットが考えられます。
- 収入が不安定になる:会社からの給与がなくなるため、失業保険や傷病手当金などの公的支援や貯蓄で生活費を賄う必要があります。受給までには時間がかかる場合もあります。
- 社会とのつながりが一時的に希薄になる:会社という居場所がなくなり、同僚との交流も減るため、孤立感を感じることがあります。
- 再就職への不安:病状回復後の再就職活動について、体力やブランクに対する不安を感じることがあります。うつ病の経験をどのように伝えるか悩む方もいるかもしれません。
- 健康保険・年金の手続きが必要になる:会社が代行してくれていた手続きを、自分で市区町村などで行う必要があります。
これらのデメリットはありますが、うつ病を抱えたまま無理に働き続けることで病状が悪化し、さらに深刻な状況に陥るリスクと比較すると、退職して療養に専念することのメリットの方が大きい場合も少なくありません。デメリットを理解し、対策を講じながら退職後の生活を進めることが重要です。
うつ病で退職すると周囲に「迷惑」をかけますか?
うつ病で退職を考える方は、「会社や同僚に迷惑をかけてしまうのではないか」と深く悩むことが多いです。これは、うつ病の症状として、自分を責めてしまう思考パターンが出やすいこととも関連しています。
しかし、迷惑をかけているという考えは、病気の影響である可能性が高いです。会社には、従業員の健康と安全に配慮する義務があり、従業員が病気で働けなくなった場合には、業務のカバーや人員配置の変更などを行う責任があります。もちろん、急な退職や引き継ぎ不足があれば一時的に業務に影響が出ることはあるかもしれませんが、それは会社として対処すべき問題であり、退職するあなたが一方的に責任を感じる必要はありません。
また、うつ病は治療が必要な病気であり、適切な休養を取ることは回復のために不可欠です。病状が改善しないまま無理に働き続けることの方が、長期的に見て会社にとっても、ご自身にとっても負担となる可能性が高いです。
「迷惑をかけている」という感情に囚われすぎず、まずはご自身の心身の回復を最優先に考えてください。
うつ病で休職からの退職は「ずるい」と思われますか?
うつ病で休職した後に、そのまま回復せずに退職を選択することに対して、「休職しておきながら結局辞めるのはずるい」と感じる人がいるかもしれません。しかし、これもまた、ご自身を責める必要のない考え方です。
休職は、病気療養のために会社から認められた正当な権利です。休職期間中に回復し、職場復帰できるのが理想ですが、病状によっては休職期間中に回復が見込めず、退職を選択せざるを得ない場合もあります。これは、休職制度の本来の目的である「回復と復帰」が叶わなかった結果であり、決して「ずるい」ことではありません。
うつ病は、本人の意思だけではコントロールできない病気です。病気のために働くことが困難になった結果として退職に至ったのであれば、それは正当な理由による退職です。周囲の人がどのように感じるかはコントロールできませんが、ご自身の置かれた状況や病気の特性を理解し、不必要に他人の評価を気にしないことが大切です。
うつ病で退職した後の「生活費」はどうすれば良いですか?
うつ病で退職した後、収入がなくなることに対する不安は大きいでしょう。退職後の生活費を賄うためには、いくつかの方法があります。
- 貯蓄:当面の生活費として、ある程度の貯蓄を取り崩すことになるかもしれません。
- 失業保険(雇用保険の基本手当):病状が回復し、働く意思と能力があれば受給できます。特定理由離職者と認められると、給付制限なく受け取れる可能性があります。
- 傷病手当金:退職日時点で傷病手当金を受給している、または受給要件を満たしている場合、一定の条件で退職後も最長1年6ヶ月まで継続受給できます。病気療養中の生活を支える重要な制度です。
- 障害年金:うつ病が重症で、一定の障害状態にあると認められた場合に受給できます。申請から受給までには時間がかかる場合があります。
- 家族からの支援:配偶者や親からの経済的な支援が得られる場合は、一時的に頼ることも選択肢の一つです。
- 生活保護:上記の公的支援や貯蓄、家族からの支援でも生活が成り立たない場合、最後のセーフティネットとして生活保護制度があります。
これらの制度を組み合わせて活用することで、退職後の生活費を確保することが可能です。まずは、ご自身がどの制度を利用できるか確認し、手続きを進めましょう。特に、傷病手当金や失業保険、障害年金は、ご自身の加入状況や病状によって受給可否や金額が異なりますので、早めに手続きを進めることが大切です。必要であれば、ハローワークや年金事務所、社会保険労務士などの専門家にも相談しましょう。
診断書があれば絶対に退職できますか?
医師の診断書は、うつ病によって就業が困難であるという客観的な証拠となり、会社に病状を理解してもらう上で非常に有効です。しかし、診断書があれば絶対に、かつ希望通りのタイミングで退職できるとは限りません。
前述の通り、民法上は退職の意思表示から2週間で退職が成立しますが、就業規則に1ヶ月前といった定めがある場合は、まずはそのルールに則って手続きを進めるのが一般的です。診断書は、病気による退職という「正当な理由」があることを示すものであり、会社が不当に退職を拒否したり、不合理な引き止めを行ったりする際には、ご自身の権利を主張するための根拠となります。
しかし、診断書があるからといって、会社がすぐに希望通りの退職日(特に即日退職)を受け入れなければならない法的な義務が常に生じるわけではありません。あくまで会社との話し合い、つまり合意退職を目指すのが基本です。病状の深刻さを丁寧に伝え、診断書の内容を説明し、可能な限り会社と協力して退職時期や引き継ぎについて調整することが円満な退職につながります。
会社が診断書の内容を軽視したり、病状を理由にした退職を不当に拒否したりする場合は、労働組合や労働基準監督署、弁護士、退職代行サービスなど、外部の力を借りることも検討してください。診断書は、これらの機関に相談する際にも、ご自身の状況を説明するための重要な書類となります。
うつ病からの回復と次のステップへ

うつ病を理由に退職を検討することは、心身ともに辛い状況の中で大きな決断を迫られる経験です。しかし、現在の職場環境が病状を悪化させている場合や、働くことが困難なほどに症状が重い場合、退職は回復に向けた有効な選択肢となり得ます。
退職をスムーズに進め、退職後の不安を軽減するためには、感情的にならず、段階を踏んで手続きを進めることが大切です。まずは主治医と十分に相談し、病状を正確に把握し、診断書を取得しましょう。そして、就業規則を確認し、退職時期や伝え方を準備します。会社には、病状と診断書を提示し、誠実に退職の意思を伝えることが望ましいです。
退職日までの引き継ぎや手続きは、体調と相談しながら無理のない範囲で行いましょう。特に、退職後の生活に不可欠な離職票や源泉徴収票などの書類は、必ず会社から受け取るように確認してください。
退職後は、健康保険や年金の切り替え、失業保険や傷病手当金、必要に応じて障害年金といった公的な手続きを忘れずに行うことが、生活の安定につながります。これらの制度や、ハローワーク、地域障害者職業センターなどの支援機関を積極的に活用しましょう。
そして何よりも、退職は終わりではなく、うつ病からの回復に向けた新たな始まりです。自分を責めたり、焦ったりする必要は全くありません。十分な休養を取り、規則正しい生活を心がけ、主治医の指導のもとで治療に専念してください。心身が回復したら、ご自身のペースで次のステップへと進んでいきましょう。
この情報が、うつ病で退職を考えている皆様にとって、少しでも心の支えとなり、安心して前に進むための一助となれば幸いです。個別の状況については、必ず専門家にご相談ください。
免責事項:本記事は、うつ病による退職の流れと手続きに関する一般的な情報を提供するものです。個々の状況や会社の就業規則、法的な解釈によって対応が異なる場合があります。実際の退職手続きや公的支援制度の利用にあたっては、必ず会社の担当者、主治医、ハローワーク、年金事務所、社会保険労務士、弁護士などの専門家にご相談ください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねます。
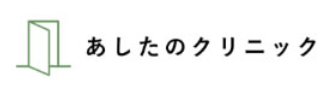

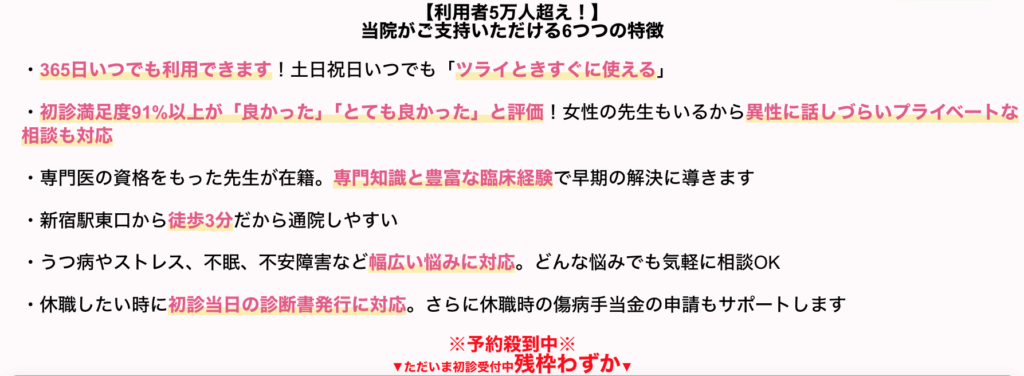



コメント