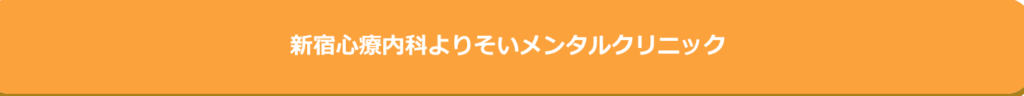
診断書が必要になったとき、気になることの一つにその「費用」があるでしょう。「一体いくらかかるのだろう?」「なぜこんなに高いのだろう?」といった疑問を持つ方も少なくありません。診断書は、病気や怪我の状態、治療内容などを医師が証明する重要な書類であり、休職手続きや保険金の請求、各種申請など、様々な場面で提出を求められます。
しかし、普段馴染みがないため、費用体系や手続きについてよく分からないと感じる方が多いようです。この記事では、診断書の発行にかかる費用について、相場や内訳、保険適用外の理由、そして具体的なもらい方まで、皆さんの疑問を解消できるよう網羅的に解説します。診断書が必要になった際の参考にしていただければ幸いです。
診断書の費用相場【いくらかかる?】

診断書の費用は、発行を依頼する医療機関の種類(病院の規模やクリニックなど)や、診断書の種類、記載内容の複雑さによって大きく異なります。一概に「いくら」と言い切ることは難しいですが、一般的な相場観を知っておくと、心構えができるでしょう。
診断書の発行にかかる一般的な料金
多くの医療機関で発行される比較的シンプルな診断書の場合、費用の相場は3,000円から10,000円程度となることが多いです。例えば、学校や職場に提出する簡単な病状証明や、健康診断の結果に対する意見書などがこれにあたります。
ただし、これはあくまで「一般的な」目安であり、医療機関によってはこれより安価な場合もあれば、高額になる場合もあります。特に、大規模な病院や大学病院などでは、文書料の設定が高めにされている傾向があります。例えば、千葉大学医学部附属病院では、診断書(大学様式)が5,500円から13,200円、英文診断書が11,000円、自賠責保険診断書が13,200円など、詳細な料金基準を公開しています。
また、診断書に記載する内容が複雑であったり、詳細な検査結果や治療経過の要約が必要だったりする場合は、その分手間がかかるため、費用が高くなる傾向があります。
診断証明書の料金(費用)相場は医療機関で異なる
先述の通り、診断書の費用は医療機関によって大きく異なります。これは、診断書の発行が健康保険の適用されない「自由診療」となるため、医療機関が独自に料金を設定できるからです。
医療機関の規模や種類によって料金設定が異なるのは、以下のような理由が考えられます。
- 病院の規模: 大規模病院ほど組織的な手続きや確認に時間を要する場合があり、事務コストなどが反映されることがあります。
- 地域性: 地域による物価や医療機関の経営状況なども影響することがあります。
- 診断書の種類: 特定の目的(例:障害年金申請など)のための診断書は、記載内容が詳細かつ専門的であるため、料金が高めに設定されているのが一般的です。
- 医療機関の方針: 各医療機関の経営方針によって、文書料に対する考え方が異なります。
【診断書費用の一般的な目安】
| 医療機関の種類 | 診断書の種類(例) | 費用相場(目安) | 特徴・傾向 |
|---|---|---|---|
| 小規模クリニック | シンプルな診断書(病状証明など) | 3,000円~5,000円 | 比較的安価な傾向。即日対応可能な場合もある。 |
| 中規模病院 | 各種申請用、保険会社指定の書式 | 5,000円~10,000円 | 用途により幅がある。 |
| 大規模病院・大学病院 | 詳細な病状証明、特定の専門分野の診断 | 8,000円~15,000円以上 | 設定が高めな傾向。専門的な診断書はさらに高額に。 |
| 特定の専門病院 | 特定の疾患に関する詳細な診断書 | 10,000円~30,000円以上 | 非常に専門的な内容の場合、高額になることがある。 |
上記はあくまで一般的な目安であり、個別の医療機関や診断書の詳細によって実際の費用は変動します。
診断書が必要になった場合は、必ず事前に医療機関の受付窓口やウェブサイトなどで料金を確認することをお勧めします。特に、特定の申請や保険金請求のために指定された書式がある場合は、その書式への記載費用について確認しておくと良いでしょう。
診断書費用はなぜ高い?保険適用外の理由

診断書を発行してもらう際に、「意外と費用が高い」と感じる方は多いかもしれません。その理由は何でしょうか?最も大きな理由は、診断書の作成が健康保険の適用対象外であることにあります。
診断書が医療行為ではないため
健康保険が適用されるのは、「傷病に対して行われる診療行為」です。具体的には、診察、検査、治療、投薬などがこれにあたります。しかし、診断書を作成する行為自体は、これらの「診療行為」とは異なると位置づけられています。このことは、厚生労働省の通知などでも示されており、診断書の作成行為は健康保険の対象外と明確に位置づけられています。
診断書は、あくまで診療の結果や患者さんの状態を「証明する書類」を作成する事務的な手続きや、その内容をまとめる作業とみなされます。患者さんの傷病の治療を直接目的とする行為ではないため、健康保険の給付対象とはならないのです。
全額自己負担となる背景
診断書の作成が健康保険の適用対象外であるため、その費用は医療機関が自由に設定できる「自由診療」となります。そして、自由診療にかかる費用は、患者さんがその全額を自己負担することになります。
健康保険が適用される医療行為には、国が定めた診療報酬点数があり、医療機関はそれに従って費用を請求します。自己負担割合(通常3割)を除いた残りは健康保険から支払われます。しかし、診断書作成にはこのような公定価格が存在しません。
医療機関は、診断書の内容の複雑さ、作成にかかる医師や事務職員の時間・労力、書類の保管コストなどを考慮して、独自の料金を設定しています。特に、詳細な病状の経過や、治療に対する意見、今後の見込みなど、専門的な判断や慎重な記載が求められる診断書ほど、作成には手間と責任が伴うため、費用が高くなる傾向があります。
また、医師が診断書を作成する際には、患者さんの診療情報(カルテなど)を正確に把握し、法律に基づいた適切な表現を用いる必要があります。これらの専門的な作業に対する対価として、費用が発生すると考えることができます。
このように、診断書費用が全額自己負担となり、医療機関によって料金が異なるのは、「医療行為ではないこと」と「自由診療であること」が主な背景となっています。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

診断書のもらい方

実際に診断書が必要になった場合、どのように依頼すれば良いのでしょうか。診断書のもらい方にはいくつかのステップがあり、それぞれに費用や期間が関連してきます。
病院で診断書を依頼する手順
診断書は、原則としてその傷病について診療を受けた医療機関に依頼します。診察を受けていない医療機関に診断書の作成を依頼することはできません。
- 依頼の申し出: 診断書が必要になったら、まずは受診した医療機関の受付に「診断書を作成してほしい」旨を伝えます。診察の際に医師に直接依頼することも可能ですが、まずは受付に相談するのがスムーズです。
- 必要事項の確認: どのような目的で、誰に提出する診断書なのかを明確に伝えます。提出先(会社、学校、保険会社、行政機関など)や、診断書に記載してほしい具体的な内容(例:「〇月〇日から〇月〇日まで休職が必要である」「〇〇病により△△の援助が必要」など)を具体的に伝えることが重要です。特定の書式がある場合は、その書式を医療機関に提出します。
- 費用の確認: 診断書の種類や書式に応じて費用が異なるため、この時点で料金を確認しましょう。医療機関によっては、依頼時に概算費用を教えてくれます。
- 作成期間の確認: 診断書が完成するまでの期間を確認します。簡単なものであれば比較的早く作成されますが、内容が複雑であったり、医師の診察が必要だったりする場合は、時間がかかることがあります。
- 支払いと受け取り: 診断書が完成したら、通常は医療機関の窓口で費用を支払い、診断書を受け取ります。郵送での受け取りが可能な場合もありますが、別途郵送料などがかかる場合があります。
【依頼時の注意点】
- 明確な目的を伝える: 診断書が必要な目的によって、記載すべき内容が異なります。提出先や用途を正確に伝えましょう。
- 指定の書式を持参する: 保険会社や会社などが指定する診断書用紙がある場合は、忘れずに持参・提出しましょう。
- 急ぎの場合は相談する: 急ぎで必要な場合は、その旨を伝え、対応が可能か相談してみましょう。ただし、対応できない場合や、追加費用がかかる場合もあります。
診断書発行までにかかる期間
診断書の発行にかかる期間は、医療機関や診断書の種類、医師の業務状況などによって大きく異なります。
- 即日~数日: 比較的簡単な病状証明や、定型の診断書などで、依頼時に医師が対応可能であれば、即日または数日中に発行されることがあります。
- 1週間~2週間: 一般的には、依頼から発行まで1週間~2週間程度の時間がかかることが多いです。医師が診察の合間にカルテを確認し、診断書を作成するため、ある程度の期間が必要となります。
- それ以上: 複雑な内容の診断書や、医師が長期不在の場合などは、それ以上の期間を要することもあります。
費用は、先述の通り診断書の種類や医療機関によって異なりますが、依頼時に確認した料金を、診断書の受け取り時に支払うのが一般的です。急ぎでの対応を依頼した場合に、通常の費用に加えて「速達料金」や「緊急作成料」のような追加費用が発生する医療機関もあります。
依頼前に「診断書の発行にはどれくらいの期間がかかりますか?」「費用はいくらですか?」と、必ず確認するようにしましょう。特に、提出期限がある場合は、早めに医療機関に相談し、発行までの期間を考慮して依頼することが大切です。
診断書の種類別費用目安

診断書は、提出する目的によって記載内容が異なり、それに伴って費用も変動します。ここでは、代表的な診断書の種類とその費用目安について解説します。
休職診断書の費用
休職診断書は、患者さんが病気や怪我のために就労が困難であることを証明し、会社に休職を申請するために提出する書類です。記載内容は比較的シンプルで、病名、症状、休職が必要な期間などが記載されます。
- 費用目安: 3,000円~8,000円程度
会社の指定書式がある場合と、医療機関の書式で良い場合があります。指定書式の場合は、医療機関側がその書式に合わせて記載する必要があるため、内容によっては費用が若干高くなることもあります。
傷病手当金申請用診断書の費用
傷病手当金は、病気や怪我で会社を休み、給与の支払いが受けられない場合に、健康保険組合から支給される手当金です。申請には、医師が記入する「療養担当者記入用」の書類が必要です。この書類には、傷病名、発病または負傷の原因、労務不能と認めた期間、今後の見込みなどが詳細に記載されます。
- 費用目安: 3,000円~10,000円程度
健康保険組合が指定する書式であることがほとんどです。記載項目が多く、労務不能期間の判断など、医師の専門的な意見が必要となるため、一般的な診断書よりも費用が高めになる傾向があります。
生命保険・医療保険申請用診断書の費用
生命保険や医療保険に加入している方が、病気や怪我で給付金を請求する際に必要となる診断書です。保険会社が指定する専用の書式であることが多いです。傷病名、治療内容、入院期間、手術の有無、後遺症の有無など、保険会社が必要とする詳細な情報が記載されます。
- 費用目安: 5,000円~15,000円程度
記載項目が非常に多く、病状の詳細な経過や治療内容、手術内容などが細かく問われるため、医師のカルテ確認や記載に手間がかかります。項目ごとに費用が加算される保険会社指定の書式もあり、合計費用が高額になることがあります。医療機関によっては、社会情勢などを背景に診断書料金を見直すこともあります。例えば、北野病院では、2025年4月より生命保険診断書を5,500円から7,700円へ改定しています。
障害年金・各種申請用診断書の費用
障害年金や身体障害者手帳、自立支援医療などの各種公的な制度を申請する際に提出する診断書です。これらの診断書は、指定された複雑な書式であり、傷病名、診断の根拠、治療内容、検査結果、日常生活や就労状況における具体的な障害の状態、予後などが詳細かつ専門的に記載されます。
- 費用目安: 8,000円~20,000円以上
公的な申請に関わる診断書は、記載内容が非常に専門的で詳細な情報が求められるため、他の診断書と比較して費用が高額になる傾向が強いです。特に精神疾患や難病など、診断や状態把握が複雑なケースでは、医師の作成にかかる時間や労力が大きくなるため、費用が高くなることがあります。前述の北野病院では、2025年4月より身体障害者診断書を3,300円から5,500円へ改定するなど、公的な診断書についても料金が見直されることがあります。
【診断書の種類別費用目安まとめ】
| 診断書の種類 | 主な用途 | 費用相場(目安) | 特徴・傾向 |
|---|---|---|---|
| シンプルな診断書 | 学校提出、簡単な病状証明、健康診断意見書 | 3,000円~5,000円 | 記載項目が少ない、定型の書式が多い。 |
| 休職診断書 | 会社への休職申請 | 3,000円~8,000円 | 就労困難であることの証明。 |
| 傷病手当金申請用診断書 | 健康保険組合への傷病手当金申請 | 3,000円~10,000円 | 労務不能期間の証明。保険者指定の書式。 |
| 生命保険・医療保険申請用診断書 | 保険会社への給付金請求 | 5,000円~15,000円 | 詳細な病状・治療経過の記載。保険会社指定の書式。項目加算の場合あり。 |
| 障害年金・各種申請用診断書 | 障害年金、手帳、自立支援医療等の申請 | 8,000円~20,000円以上 | 専門的で詳細な記載。公的な指定書式。複雑なケースはさらに高額に。 |
繰り返しますが、上記はあくまで目安であり、実際の費用は医療機関によって異なります。必ず依頼前に確認してください。
診断書をもらえないケースと対処法

診断書は必ずしもいつでも、誰でも、どんな内容でも書いてもらえるわけではありません。診断書の発行が困難なケースや、過去の診断書をあとから依頼する場合の注意点について解説します。
診断書の発行が困難な具体例
医師には、診療した患者さんから診断書の交付を求められた場合に、正当な理由なくこれを拒んではならないという医師法上の義務があります。しかし、「正当な理由」がある場合には、発行を断られることがあります。
- 診断に根拠がない場合: 診察や検査の結果、診断を確定できない場合や、患者さんが訴える症状と客観的な所見が一致しない場合など、医師が医学的に診断書の記載内容を証明できないケースです。「〇〇病と診断書に書いてほしい」と患者さんが希望しても、医学的根拠がない場合は記載できません。
- その傷病について診療を受けていない場合: 診断書は、原則として当該医療機関で診療を受けた傷病についてのみ発行されます。他院で治療を受けた傷病について、その内容を証明する診断書を依頼することはできません。
- 医師が専門外である場合: 例えば、内科の医師に外科的な疾患や精神疾患に関する詳細な診断書の作成を依頼するなど、医師の専門外の分野に関する診断書は、医学的な判断が難しいため発行が困難な場合があります。
- 不正な目的であると判断される場合: 虚偽の内容を記載させようとする場合や、不正な目的に利用される可能性があると医師が判断した場合なども、発行を拒否される正当な理由となり得ます。
- 患者さんの状態を把握できていない場合: 長期間受診がなく、現在の病状や状態を医師が把握できていない場合も、適切な診断書を作成することが難しいことがあります。
このようなケースでは、医師は診断書の作成依頼に応じられないことがあります。もし診断書の発行を断られた場合は、その理由を医師に説明してもらい、どのようにすれば発行が可能になるのか(例:追加の検査が必要、専門医の受診が必要など)を確認しましょう。
過去の診断書をあとから書いてもらう場合の費用と注意点
過去に診療を受けたことに関する診断書を、後日になってから書いてもらうことは可能です。しかし、いくつかの注意点があります。
- カルテの保存期間: 医療機関には、患者さんのカルテを一定期間(通常5年間、ただし例外規定あり)保存する義務があります。保存期間を過ぎると、診療記録が残っていないため、診断書の作成が不可能となる場合があります。
- 再受診が必要な場合: 依頼する時点から過去の診療日から時間が経過している場合や、現在の病状についても記載が必要な場合は、診断書作成のために再度受診が必要となることがあります。
- 費用の加算: 過去の診療に関する診断書作成は、現在のカルテを確認し、当時の状況を正確に把握する必要があるため、新規の診断書作成よりも手間がかかることがあります。そのため、通常の診断書費用に加えて、カルテの調査料や遡及期間に応じた加算費用が発生する医療機関もあります。費用については、依頼時に必ず確認が必要です。
- 記載内容の限界: 過去の診断書は、あくまで当時の診療記録に基づき作成されます。依頼日時点での最新の病状や、当時の記録にない事項について記載を求めることは難しい場合があります。
過去の診断書を依頼する場合は、できるだけ早めに医療機関に連絡し、依頼したい期間や内容を伝え、作成が可能か、かかる費用と期間はどれくらいかを確認しましょう。特に古い記録に関する依頼は、対応できない可能性も考慮しておく必要があります。
診断書費用に関するQ&A【よくある質問】

診断書費用について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
診断書の支払い方法
診断書の費用は、通常、診断書を受け取る際に医療機関の窓口で支払うのが一般的です。支払い方法は、医療機関によって異なります。
- 現金: 多くの医療機関で対応可能です。
- クレジットカード: クレジットカードでの支払いが可能な医療機関も増えていますが、すべての医療機関で対応しているわけではありません。特に小規模なクリニックでは現金払いのみの場合が多いです。
- その他: 一部の医療機関では、電子マネーやデビットカードでの支払いに対応している場合もあります。
事前に医療機関のウェブサイトで確認するか、窓口で支払い方法について問い合わせておくと安心です。
診断書発行にかかる日数は?
診断書の発行にかかる日数は、依頼する医療機関や診断書の種類、医師の業務状況によって異なります。
- 即日発行: 簡単な病状証明などで、医師が診察の合間に対応できる場合は、即日発行が可能な場合があります。
- 1週間~2週間: 一般的には、依頼から発行まで1週間~2週間程度かかることが多いです。医師は通常の診療業務の合間に診断書を作成するため、すぐに発行できるわけではありません。
- それ以上: 複雑な内容の診断書や、医師が学会や休暇などで不在の場合、また依頼が集中している時期などは、2週間以上かかることもあります。
【発行に日数がかかる理由】
- 医師の業務負荷: 医師は日常の診療に加え、手術や緊急対応、学会準備など多忙なため、診断書作成に専念できる時間が限られています。
内容の確認と記載: 診断書は公的な証明書であり、正確性が求められます。医師はカルテを詳細に確認し、内容を吟味して記載するため、時間がかかります。 - 医療機関内の手続き: 診断書の作成後、事務部門での確認や手続きを経て発行されるため、その過程でも時間がかかります。
提出期限がある場合は、余裕を持って依頼することが非常に重要です。依頼時に発行までにかかる日数を確認し、必要であれば早めに依頼するようにしましょう。
その他のよくある質問
- Q: 診断書は誰でももらえますか?
A: 原則として、その医療機関で診療を受けた本人にのみ発行されます。代理人が受け取る場合は、委任状や身分証明書が必要になることが一般的です。 - Q: 診断書の内容を修正してもらえますか?
A: 記載内容に事実と異なる点がある場合は、医療機関に相談し、修正を依頼することが可能です。ただし、医学的な判断に基づく記載内容について、患者さんの希望で変更を求めることはできません。 - Q: 診断書は郵送してもらえますか?
A: 多くの医療機関では窓口での受け取りが基本ですが、郵送に対応している医療機関もあります。ただし、郵送料や特定記録郵便などの費用が別途かかる場合があります。依頼時に確認しましょう。 - Q: セカンドオピニオンを受けた病院で診断書はもらえますか?
A: セカンドオピニオンはあくまで「意見を求める」場であり、本格的な診療や治療を受ける場ではありません。そのため、セカンドオピニオンの結果について診断書を発行してもらうことは基本的にできません。診断書が必要な場合は、実際に治療を受けている医療機関に依頼してください。 - Q: 診断書は英語でも書いてもらえますか?
A: 英語など外国語での診断書作成に対応している医療機関は限られています。国際的な病院や、外国人患者さんの対応が多い医療機関であれば可能な場合がありますが、対応していない場合は、日本語の診断書を受け取り、ご自身で翻訳会社などに依頼する必要があります。費用も通常より高額になることが多いです。
まとめ|診断書費用に関するポイント

診断書は、病気や怪我を証明するために様々な場面で必要となる重要な書類です。その費用については、馴染みが薄いため疑問に思う方も多いですが、いくつかのポイントを理解しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。
この記事で解説した診断書費用に関する主なポイントをまとめます。
- 診断書の費用は、医療機関や診断書の種類、記載内容によって大きく異なります。明確な公定価格はなく、医療機関が独自に料金を設定する自由診療です。
- 一般的な費用相場は3,000円から1万円程度ですが、複雑な内容や公的な申請に用いる診断書は1万円を超えることも珍しくありません。具体的な医療機関の例として、千葉大学医学部附属病院の料金表や、北野病院での料金改定などがあります。
- 診断書費用が全額自己負担となるのは、診断書の作成が健康保険の適用対象となる「医療行為」ではないとみなされるためです。この点は、厚生労働省の通知でも示されています。
- 診断書を依頼する際は、受診した医療機関の受付に申し出て、提出先や必要な内容、費用、作成にかかる期間を必ず確認しましょう。特定の書式がある場合は持参します。
- 診断書の発行には、即日~数日かかる場合もありますが、通常は1週間~2週間程度の期間を要します。提出期限がある場合は、余裕を持って依頼することが重要です。
- 診断書は、医学的な根拠がない場合や、当該医療機関で診療を受けていない場合など、正当な理由がある場合には発行を断られることがあります。
- 過去の診断書を依頼する場合、カルテの保存期間に注意が必要です。また、追加の費用が発生する可能性もあります。
診断書が必要になった際は、これらの点を参考に、まずはかかりつけの医療機関に相談してみてください。事前に費用や期間を確認することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
【免責事項】
この記事は、診断書費用に関する一般的な情報を提供することを目的としています。記載されている費用相場や期間はあくまで目安であり、実際の料金や対応は個別の医療機関によって異なります。また、制度の改正などにより情報が変更される可能性もあります。診断書が必要な場合は、必ず依頼する医療機関に直接お問い合わせいただき、最新の情報をご確認ください。この記事の情報に基づいて発生したいかなる損害についても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。
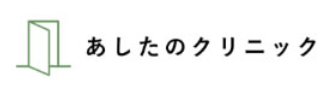

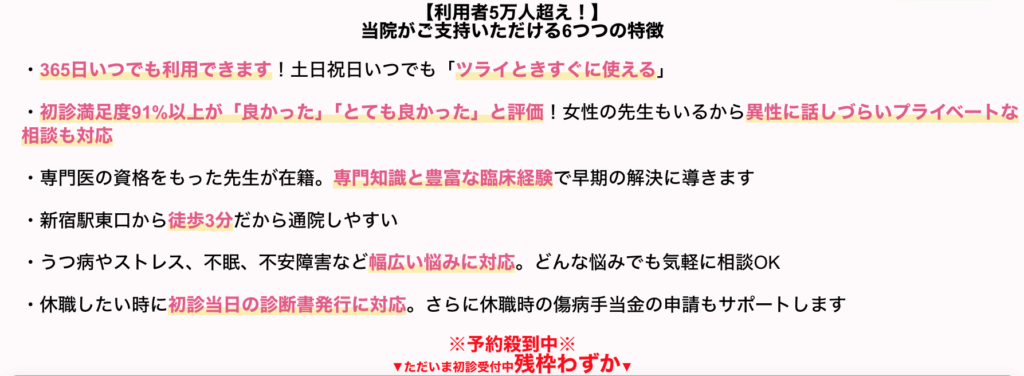



コメント