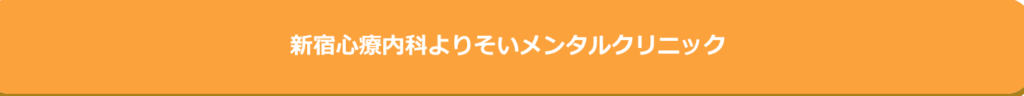
仕事に行けない状況は、誰にでも起こりうるつらい状態です。朝起き上がれない、体が重く感じる、会社の前まで行っても足がすくむなど、その症状はさまざまです。このような状態は、「甘え」ではなく、心や体が休息を求めているサインかもしれません。
一人で抱え込まず、まずは状況を理解し、適切な対処法を知ることが回復への第一歩となります。この記事では、仕事に行けない原因から、今すぐできる緊急時の対処法、そして根本的な解決に向けた方法までを詳しく解説します。あなたの状況を改善するためのヒントを見つける手助けになれば幸いです。
仕事に行けない原因を知る

仕事に行けないと感じる背景には、様々な原因が複雑に絡み合っていることがあります。原因を特定することは、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。自分の状況を客観的に見つめ直し、何が原因となっているのかを理解することから始めましょう。
精神的な原因
心の問題が仕事に行けない状況を引き起こしているケースは少なくありません。精神的な負担は、目に見えにくいため自分でも気づきにくいことがあります。
ストレス、燃え尽き症候群
日々の業務による過度なストレスや、長期間にわたる緊張状態は、心身を疲弊させます。特に、自分のキャパシティを超えた仕事量、厳しいノルマ、絶え間ないプレッシャーなどは、心に大きな負担をかけます。
燃え尽き症候群(バーンアウト)は、仕事に対して意欲を燃やしていた人が、過労やストレスの蓄積によって、心身ともに疲れ果ててしまう状態です。具体的には、仕事への関心が失われる、疲労感が続く、集中力が低下する、イライラしやすくなる、人と関わるのを避けるといった症状が現れます。これは単なる疲労ではなく、心身が限界を迎えているサインです。
適応障害、うつ病などの病気の可能性
仕事に行けない状態が続く場合、適応障害やうつ病といった精神疾患の可能性も考えられます。
適応障害は、特定のストレスの原因(この場合は仕事や職場環境)に対して、気分や行動面に著しい症状が現れるものです。ストレスの原因から離れると症状が改善するのが特徴ですが、原因となる環境にいる間は、抑うつ気分、不安、イライラ、不眠、集中力の低下、出社拒否などの症状が現れます。
厚生労働省が運営するポータルサイト「こころの耳」では、適応障害を「環境変化によるストレスが個人の順応力を越えた時に生じる情緒面および行動面の不調」と定義しています。回復には環境調整と個人の適応力向上が重要であることが示されています。(適応障害:用語解説|こころの耳より引用)
うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続き、日常生活に大きな支障をきたす病気です。仕事に行けないだけでなく、何をしても楽しめない、食欲がない、眠れない、体がだるい、自分を責めるといった症状が現れます。これらの病気は、適切な治療によって改善が見込めます。自己判断はせず、専門の医療機関を受診することが大切です。
身体的な原因
精神的な負担が、身体症状として現れることもありますし、純粋な身体の不調が仕事に行けない原因となることもあります。
体が動かない、出社前に体調が悪くなる
朝、体が重くて起き上がれない、ベッドから出られない、といった症状は、単なる寝坊とは異なります。強烈な疲労感や倦怠感に加え、吐き気、腹痛、頭痛、めまい、発熱といった身体症状が出ることがあります。特に、会社に行く準備を始めたり、会社のことを考えたりすると症状が悪化する場合、心因性の影響が大きいと考えられます。
これは、体や心が「これ以上、会社に行くのは危険だ」と信号を出している状態です。無理に動こうとすると、さらに症状が悪化することもあります。
睡眠不足、疲労の蓄積
慢性的な睡眠不足や、仕事による肉体的な疲労が十分に回復しないまま蓄積することも、仕事に行けない大きな原因となります。体が休息を必要としている状態であり、無理に出勤しようとするとパフォーマンスの低下だけでなく、事故やさらなる体調悪化を招くリスクもあります。
十分な睡眠や休息が取れていないと、集中力が低下し、ミスが増えたり、判断力が鈍ったりします。これがさらなるストレスとなり、悪循環に陥ることもあります。
職場環境の原因
職場の環境そのものが、仕事に行けない直接的な原因となっている場合もあります。個人の問題だけでなく、組織や人間関係の問題が深く関わっているケースです。
人間関係(上司、同僚)
職場の人間関係の悩みは、多くの人が抱える問題ですが、これが深刻化すると仕事に行けなくなる原因となります。上司からの理不尽な叱責(パワハラ)、同僚からのいじめや嫌がらせ、孤立などが挙げられます。毎日顔を合わせる相手との関係が悪化すると、職場にいること自体が強いストレスとなり、精神的に追い詰められてしまいます。
コミュニケーションがうまくいかない、チームワークがない、といった環境も、働く意欲を削ぎ、仕事に行きたくない気持ちを強くさせます。
仕事内容、仕事量
仕事内容が自分の適性に合わない、興味を持てない、またはあまりにも単調でやりがいを感じられないといった場合も、モチベーションが低下し、出社が億になることがあります。また、責任が重すぎる、あるいは逆に責任がなさすぎてやりがいがないといった極端な状況も問題となりえます。
さらに、明らかに処理能力を超える仕事量を与えられている、納期が厳しすぎるなど、物理的に過酷な状況も、心身を疲弊させ、仕事に行けない原因となります。長時間労働が常態化している職場も同様です。
ハラスメント
職場で受けるハラスメント(パワハラ、セクハラ、モラハラなど)は、被害者の尊厳を傷つけ、心身に深刻なダメージを与えます。ハラスメントが原因で職場に恐怖を感じ、仕事に行けなくなるケースは非常に多いです。自分が被害者であることに気づいていない場合や、「これくらいは我慢すべきだ」と思い込んでいる場合もありますが、どのような形のハラスメントであれ、許されることではありません。
もしハラスメントを受けていると感じたら、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが大切です。また、証拠を残しておくことも、後の対応のために重要になります。自分でできるハラスメントへの対応という情報源でも、自分を責めないこと、不快である意思表示、相談の重要性、記録を残すことなどが挙げられています。ハラスメントは、個人の問題ではなく、組織として対応すべき問題です。被害者が安心して働ける環境を整備する責任が職場にはあります。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

今すぐできる緊急時の対処法

朝、どうしても体が動かない、出社時間が迫っているのに準備ができない――。このような緊急時には、まず冷静になり、今できることを優先的に行うことが重要です。最も大切なのは、無理をしないことです。
会社に連絡する
仕事に行けないことが確定したら、できるだけ早く会社に連絡を入れる必要があります。無断欠勤は、後々の状況をさらに複雑にしてしまう可能性があります。
休む旨をどう伝えるか
会社に連絡する際、最も悩むのが「休む理由をどう伝えるか」ということです。正直に「精神的にきつくて行けません」と伝えることができれば良いですが、職場の雰囲気によっては難しい場合もあるでしょう。
伝える内容のポイント
- 結論を先に: まず「本日はお休みさせていただきます」と明確に伝えましょう。
- 理由は簡潔に: 詳しい説明が難しければ、「体調不良のため」「体調が優れないため」「休養が必要なため」といった表現で簡潔に伝えても構いません。精神的な不調も立派な体調不良です。
- 回復の見込み(未定でも可): いつまで休むかは未定の場合でも、「本日は」または「明日以降については、改めてご連絡いたします」のように伝えましょう。
- 業務への影響(もし可能であれば): 引き継ぎが必要な業務があれば、対応をお願いするか、指示を仰ぎましょう。しかし、緊急時でそれどころではない場合は、無理に考えなくても大丈夫です。
具体的な伝え方例
電話の場合: 「〇〇部の〇〇です。申し訳ありませんが、本日は体調不良のためお休みさせていただきます。明日以降については、改めてご連絡いたします。」
メール/チャットの場合:
件名:【〇〇部】本日の欠勤のご連絡(〇〇 〇〇)
本文:
〇〇部 △△様(または上司の名前)
お疲れ様です。〇〇です。
申し訳ありませんが、本日体調が優れないため、お休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
明日以降の出勤については、改めてご連絡いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
(署名)
どちらの方法を選ぶにしても、就業規則で定められた連絡方法があればそれに従いましょう。連絡する相手は、直属の上司が基本ですが、難しければ人事担当者や信頼できる同僚に相談することも考えてください。
精神的な理由でも休めるのか
「精神的な不調で休むなんて、認められないのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。しかし、心身の健康は働く上で最も重要であり、精神的な不調も身体的な不調と同様に、休息が必要な正当な理由です。
労働契約法第5条では、事業者は労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負うと定められています。あなたの精神状態が仕事に支障をきたす、あるいはさらに悪化する恐れがある場合、会社はあなたに休養を勧める、または休養を認める必要があります。
ただし、会社によっては精神的な理由での休暇に理解がない場合があるのも事実です。そのような場合は、前述のように「体調不良」として伝えても差し支えありません。必要であれば、後日医療機関を受診し、診断書を提出することも可能です。診断書があれば、会社も休養の必要性を認めざるを得なくなります。
とにかく休む
会社への連絡が終わったら、次にすべきことは「とにかく休む」ことです。これが最も重要です。
自分を責めない(甘えではないこと)
仕事に行けない状況になると、「自分が甘えているだけだ」「もっと頑張らなければいけないのに」と自分を責めてしまいがちです。しかし、これは断じて甘えではありません。あなたの心や体が、これ以上無理をすると壊れてしまうと警告しているサインです。
車だって、ガソリンが切れたり故障したりすれば動きません。人間も同じです。心身が疲弊し、エネルギーが枯渇している状態なのです。休息は、未来のあなたが健康に、そして再び仕事に向き合う力を蓄えるために不可欠な時間です。自分を責めるのではなく、「今は休息が必要な時期なんだ」と割り切り、まずは心と体を休ませてあげましょう。
心身を休める方法
「休む」といっても、何をすれば良いか分からないかもしれません。効果的な休息方法は人それぞれですが、いくつかのヒントを挙げます。
- 十分に睡眠をとる: 眠れるだけ眠りましょう。日中に眠くなったらいつでも寝てOKです。
- 無理に起き上がらない: ベッドや布団の中で、好きな音楽を聴いたり、本を読んだり、何も考えずに横になったりするだけでも構いません。
- 好きなことをする: 好きな映画を見る、趣味に没頭する、美味しいものを食べるなど、心が安らぐ、楽しいと感じることをしましょう。
- デジタルデトックス: スマートフォンやPCから離れ、情報過多な状態から距離を置くことも有効です。
- 軽い運動: 体調が許せば、近所を散歩する、ストレッチするなど、無理のない範囲で体を動かすと気分転換になります。
- 自然に触れる: 公園に行ったり、ベランダで日光浴をしたりするなど、自然に触れることでリラックス効果が得られます。
- 人と話す: 信頼できる家族や友人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。ただし、無理に話す必要はありません。
重要なのは、「〜しなければならない」という義務感から離れることです。仕事や社会生活から一時的に距離を置き、心身が回復するのを待ちましょう。
根本的な解決に向けた対処法

緊急時の対応で一時的に休息が取れたら、次に考えるべきは、同じ状況を繰り返さないための根本的な解決策です。原因が特定できているかいないかで、取るべきアプローチは変わってきますが、どちらにしても一歩ずつ進んでいくことが大切です。
原因を整理する
まず、仕事に行けなくなった原因について、落ち着いた状態で考えてみましょう。緊急時の対処法で心身が少し回復していれば、冷静に状況を見つめ直すことができるはずです。
原因整理のヒント
- 書き出す: ノートやスマートフォンのメモ機能などに、仕事に行けないと感じる理由を思いつくままに書き出してみましょう。「何がつらいのか」「どんな時に症状が出るのか」「誰との関係が苦痛か」「どんな仕事が嫌か」など、具体的に書き出すことで、自分の考えや感情が整理されます。
- ストレスの原因を探る: ストレスチェックリストなどを活用して、自分がどのようなストレスを抱えているかを客観的に見てみるのも良いでしょう。
- 体調の変化を記録する: いつから体調が悪くなったか、どのような症状が出るかを記録することで、原因との関連性が見えてくることがあります。
- 一人で抱え込まない: 原因が自分一人では判断できない場合や、感情的になってしまう場合は、信頼できる家族や友人、あるいは専門家と一緒に原因を探るのも有効です。
原因が明確になれば、それに対する具体的な対策を立てやすくなります。例えば、人間関係が原因なら関わり方を見直す、仕事量なら上司に相談する、精神的な不調なら医療機関を受診するといった具合です。
専門機関に相談する
仕事に行けない状態は、自分一人で解決するのが難しい場合があります。専門家の力を借りることで、状況が好転することは少なくありません。様々な相談先がありますので、自分の状況に合わせて選択しましょう。
病院(精神科、心療内科)
心身の不調が続いている場合、精神科や心療内科を受診することを強くお勧めします。
- 精神科: 気分の落ち込み、不安、不眠、意欲の低下といった精神症状が主な場合に適しています。
- 心療内科: ストレスが原因で、胃痛、頭痛、吐き気など身体症状が強く出ている場合に適しています。
どちらを受診すべきか迷う場合は、まずは心療内科を選んでみても良いでしょう。医師はあなたの症状を聞き、必要に応じて診断(適応障害、うつ病など)を行います。診断に基づいて、薬物療法や休養の指示など、適切な治療方針を示してくれます。診断書を発行してもらうことで、会社に休職や配置転換などを申請する際の根拠とすることもできます。
病院に行くことに抵抗を感じるかもしれませんが、これは体を壊したら内科に行くのと同じように、心の不調を治すための当たり前の選択です。早期に受診することで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。
カウンセリング
カウンセリングは、臨床心理士や公認心理師といった心の専門家と対話を通じて、自分自身の悩みや感情を整理し、解決策を見つけていく方法です。
- メリット:
- 自分の気持ちを安心して話せる場が得られる。
- 専門家からの客観的な視点やアドバイスをもらえる。
- 自己理解を深め、問題への対処スキルを身につけられる。
- 薬物療法に抵抗がある場合でも利用しやすい。
- デメリット:
- 医療行為ではないため、診断や投薬はできない。
- 費用がかかる場合が多い(保険適用外が多い)。
- 自分に合うカウンセラーを見つけるまでに時間がかかることもある。
病院での治療と並行してカウンセリングを受けることも可能です。最近では、オンラインカウンセリングも普及しており、自宅から手軽に利用できるようになっています。
産業医・職場の相談窓口
あなたが勤務する会社に、産業医や社内の相談窓口があれば、まずはそこを利用してみましょう。
- 産業医: 従業員の健康管理を行う医師です。健康相談、メンタルヘルス相談に応じてくれます。会社側の人間ではありますが、守秘義務があり、相談内容があなたの同意なく会社に伝えられることはありません(ただし、生命に関わる危険がある場合などは例外)。産業医に相談することで、会社に対して労働環境の改善や休職などを勧めてもらう橋渡し役になってもらえる可能性があります。
- 職場の相談窓口: 人事部内に設置されていることが多い相談窓口です。ハラスメントや人間関係の悩みなどについて相談できます。こちらも守秘義務が守られることが多いですが、相談内容によっては会社が事実確認のために動き出す可能性がある点は理解しておきましょう。
これらの社内リソースを活用することは、職場環境の改善や働き方の調整を会社に促す上で有効です。
公的な相談機関
病院や職場以外にも、公的な相談機関を利用することができます。多くの場合、無料で相談できます。
| 相談機関 | 主な相談内容 | 利用方法(例) |
|---|---|---|
| 保健所・精神保健福祉センター | 心の健康、精神疾患、ひきこもりなどに関する相談。専門家(医師、保健師、精神保健福祉士など)が対応。 | 電話、面談(要予約の場合あり) |
| 労働局・総合労働相談コーナー | 労働条件、解雇、パワハラ、セクハラなど、労働問題全般に関する相談。 | 電話、面談 |
| 法テラス | 法的な問題(未払い賃金、退職に関するトラブルなど)に関する相談。弁護士や司法書士を紹介してくれる場合も。 | 電話、面談 |
| よりそいホットライン | さまざまな困難を抱える人に寄り添い、一緒に解決方法を探す相談窓口。DV、自死、生活困窮など幅広い悩みに対応。 | 電話(無料) |
これらの機関は、問題解決のための情報提供や、適切な専門機関への橋渡しをしてくれます。どこに相談すれば良いか分からない場合でも、まずはこれらの窓口に連絡してみることで、次に取るべき行動が見えてくることがあります。
働き方や環境を調整する
原因が特定でき、専門家のサポートも得ながら、具体的な働き方や環境の調整を検討します。現在の職場で改善を目指すか、環境を変えるか、いくつかの選択肢があります。
配置転換、異動
現在の部署や業務内容、あるいは人間関係が原因である場合、配置転換や異動によって状況が改善する可能性があります。上司や人事に相談し、自分の状況を説明してみましょう。診断書があれば、会社側も真剣に検討せざるを得ないケースが多いです。
ただし、必ずしも希望が通るとは限りませんし、異動先が自分に合うとは限りません。しかし、原因が明確であれば、まずは社内での調整を試みる価値はあります。
休職
仕事に行けない状況が深刻で、すぐに復帰するのが難しい場合、休職という選択肢があります。休職とは、会社に籍を置いたまま、一定期間仕事を離れて療養に専念することです。
- メリット:
- 仕事を完全に離れて心身の回復に集中できる。
- 会社の福利厚生(傷病手当金など)を利用できる場合がある。
- 焦らずに復帰の準備ができる。
- キャリアを完全に断ち切らずに済む。
- デメリット:
- 収入が減少する可能性がある。
- 復職できる保証はない。
- 職場復帰への不安を感じることがある。
- 手続きが煩雑な場合がある。
休職制度の有無や詳細は会社の就業規則によります。診断書を持って会社に相談し、制度について確認しましょう。休職中は、医師の指示に従って療養に専念し、無理に仕事のことを考えすぎないようにすることが大切です。
転職・退職
現在の職場環境が根本的に改善の見込みがない、あるいは現在の働き方自体が自分に合わないと感じる場合は、転職や退職を検討することも視野に入ってきます。これは大きな決断ですが、自分の健康と幸せを最優先に考えるのであれば、必要な選択となることもあります。
転職を検討する場合:
- 仕事から離れて療養する期間を設けてから転職活動を行う。
- 自分の適性や、どのような働き方がしたいかをじっくり考える。
- 転職エージェントなどを利用し、自分に合った企業や職種を探す。
- 次の仕事が決まってから退職することで、無職期間をなくし、経済的な不安を軽減できる。
退職を検討する場合:
- まずは経済的な状況を確認し、当面の生活費を確保できるか検討する。
- 退職後の過ごし方(療養、資格取得、一時的な休息など)を具体的に計画する。
- 会社との退職手続きを円滑に進める。
転職や退職は、一時的な感情で決めるのではなく、心身が落ち着いてから慎重に検討することが重要です。焦らず、自分の未来にとって何がベストなのかを考えましょう。
仕事に行けない状態から回復するために

仕事に行けない状態を乗り越え、回復するためには、治療やリハビリテーション、そして再発予防の取り組みが必要です。時間はかかるかもしれませんが、着実にステップを踏んでいくことで、再び社会生活を送れるようになります。
治療やリハビリテーション
もし精神疾患と診断された場合は、医師の指示に従って治療を続けることが最優先です。薬物療法、精神療法(カウンセリングなど)を通じて、症状の改善を目指します。
症状が回復してきたら、段階的に社会生活への慣れを取り戻すためのリハビリテーションを行います。
- デイケア: 医療機関などが提供するプログラムで、集団活動などを通じて生活リズムを整えたり、対人スキルを練習したりします。
- リワークプログラム: うつ病などで休職した人が職場復帰を目指すためのリハビリテーションプログラムです。実際の仕事に近い環境で訓練を行ったり、ストレス対処法を学んだりします。
- 就労移行支援: 障害のある人が一般企業への就職を目指すための支援制度です。ビジネスマナーやPCスキル、グループワークなどを学び、就職活動のサポートを受けられます。
これらのプログラムを活用することで、安心して社会復帰に向けた準備を進めることができます。
再発予防
一度仕事に行けなくなった経験は、再発の不安を伴うことがあります。しかし、適切な対策を講じることで、再発のリスクを減らすことが可能です。
- ストレス管理: 自分にとってどのようなことがストレスになるのかを理解し、ストレス解消法をいくつか持っておくことが大切です。趣味の時間を作る、リラクゼーションを取り入れる、定期的な運動をするなど、自分に合った方法を見つけましょう。
- 自己ケアの習慣: 十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動といった健康的な生活習慣を維持することが、心身の安定につながります。
- 定期的な休息: 疲れを感じる前に意識的に休息を取るようにしましょう。有給休暇を取得したり、週末は仕事から完全に離れたりするなど、心身のリフレッシュを心がけます。
- 相談できる関係を作る: 職場内外に、悩みや不安を安心して話せる人(上司、同僚、友人、家族など)を作っておくことも重要です。
- 専門家とのつながりを維持: 必要に応じて、定期的にカウンセリングを受けたり、かかりつけ医に相談したりすることで、早期に不調のサインに気づき、対処することができます。
- 完璧主義を手放す: 全てを完璧にこなそうとせず、適度に力を抜くことも大切です。自分に課すハードルを少し下げてみることも検討しましょう。
- 働き方の見直し: 必要であれば、時短勤務、フレックスタイム制、リモートワークなど、自分に合った働き方を会社と相談し、調整を続けましょう。
再発予防は、特別なことではなく、日々の生活の中で自分の心身の状態に気を配り、適切に対応していくことの積み重ねです。
まずは心と体を休めることを優先

仕事に行けないという状況は、誰にとってもつらく、不安なものです。「甘えではないか」「自分が弱いだけではないか」と自分を責めてしまうかもしれませんが、それは心や体が限界を迎えているサインです。まずは、そのサインに気づき、「休息が必要だ」と認めることが何よりも大切です。
緊急時には、無理に会社に行こうとせず、まずは会社に連絡し、そして何よりも自分自身を休ませることを最優先にしましょう。休むこと自体が、回復への第一歩です。
休息が取れたら、仕事に行けなくなった原因を冷静に振り返り、必要であれば精神科や心療内科、カウンセリング、職場の相談窓口、公的な相談機関など、様々な専門機関に相談してみましょう。一人で抱え込まず、専門家のサポートを得ることで、問題解決への道が開けるはずです。
原因に応じて、働き方や環境を調整することも検討します。配置転換、異動、休職、そして必要であれば転職や退職も、あなたの健康と未来を守るための選択肢となり得ます。
回復には時間がかかることもありますが、治療やリハビリテーションに取り組み、再発予防のための習慣を身につけていくことで、再び安定した生活を送ることができるようになります。
もし今、あなたが仕事に行けない状況で苦しんでいるなら、この記事を読んだことをきっかけに、まずは「自分は休んで良いのだ」と自分に許可を与えてあげてください。そして、小さくてもいいので、次の一歩を踏み出してみましょう。あなたの状況が少しでも良い方向に向かうことを心から願っています。
免責事項:この記事は一般的な情報提供を目的としており、医療的なアドバイスや診断を代替するものではありません。心身の不調を感じる場合は、必ず専門の医療機関を受診し、医師の診断と指導を受けてください。この記事の情報に基づくいかなる判断や行動についても、一切の責任を負いかねます。
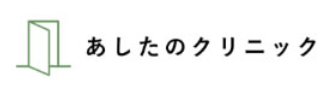

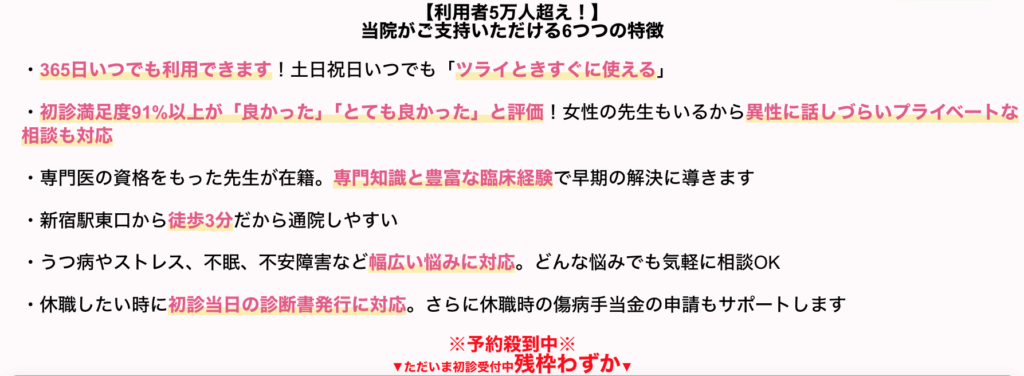



コメント