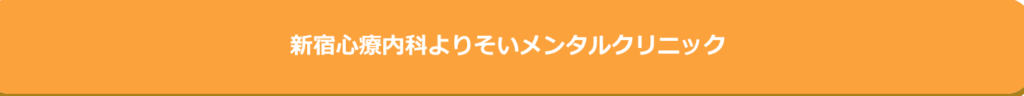
休職を検討している中で、「診断書はどうやって手に入れたらいいの?」「どこの病院に行けばいいの?」「費用はいくらくらいかかるの?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。心身の不調により仕事から離れて療養することは、回復のために非常に重要なステップです。そして、その第一歩となるのが、医師に診断書を作成してもらうことです。
この記事では、休職に必要な診断書の正しいもらい方について、具体的な手順や費用、期間、さらには診断書がもらえないケースとその対処法まで詳しく解説します。診断書取得から会社への提出まで、あなたがスムーズに手続きを進められるよう、役立つ情報を提供します。
休職に診断書は必要?役割と記載内容
休職を会社に申請するにあたり、「診断書」の提出を求められることが一般的です。法律で診断書の提出が義務付けられているわけではありませんが、多くの企業では就業規則などで休職の条件として診断書の提出を定めています。診断書は、単なる手続きのための書類ではなく、あなたが仕事から離れて療養する必要があることを客観的に証明する重要な書類だからです。
休職における診断書の重要性
休職における診断書の主な役割は以下の通りです。
- 会社が休職を認める判断材料: 医師の診断に基づき、現在の健康状態では就労が困難であることを証明することで、会社は休職の必要性を判断します。これにより、会社側も休職の申請を適切に処理し、あなたの状況に配慮した対応をとることができます。
- 傷病手当金などの申請に必要な添付書類: 健康保険組合から支給される傷病手当金や、会社の休職制度に基づく経済的支援を受ける際に、診断書が必要となるケースがほとんどです。これは、病気や怪我によって働くことができない状態であることを公的に証明するためです。
- 休職期間や復職可否の判断材料: 診断書には必要な療養期間や今後の見通しなどが記載されることがあり、これが会社が休職期間を決定したり、将来的な復職が可能かどうかを判断したりする上での重要な参考情報となります。
- 労働者への配慮: 診断書があることで、会社はあなたの健康状態に応じた適切な配慮(業務内容の変更、時短勤務、配置転換など)を検討しやすくなります。
このように、診断書は休職を円滑に進める上で欠かせない役割を担っています。適切な診断書を提出することで、あなた自身も安心して療養に専念できる環境を整えることができます。
診断書に記載される主な内容
診断書に記載される内容は、医療機関や医師、診断書の用途(会社提出用、傷病手当金申請用など)によって若干異なる場合がありますが、一般的には以下の項目が含まれます。
| 記載項目 | 具体的な内容 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 患者氏名 | 診断を受ける本人の氏名 | |
| 生年月日・性別 | 患者の基本的な個人情報 | |
| 傷病名(診断名) | 現在罹患している病気や怪我の正式名称 | 例: 適応障害、うつ病、不安障害、胃潰瘍、腰痛症など。精神的な疾患の場合、会社への報告範囲を相談することも。 |
| 病状 | 現在の症状の具体的な状態や程度 | 例: 倦怠感が強い、集中力が続かない、不眠、食欲不振、痛みの程度、体の動かしにくさなど。 |
| 経過 | 発症からの期間や、現在の症状に至るまでの経緯の簡潔な説明 | |
| 必要な療養期間 | 仕事を離れて療養するために必要と医師が判断する期間 | 例: ○ヶ月間、〇〇年〇月〇日まで。症状により期間が変動することもある。 |
| 就労に関する意見 | 現在の健康状態では就労が困難であること、自宅療養または入院が必要であることなど | 例: 現在の業務への従事が困難であるため、〇ヶ月程度の自宅療養が必要である。 |
| 今後の見通し(任意) | 回復の見込みや、復職時期に関する医師の意見 | 絶対的な日付ではなく、あくまで見込みとして記載されることが多い。 |
| 発行年月日 | 診断書が作成された日付 | |
| 医療機関情報 | 診断書を発行した医療機関の名称、住所、連絡先 | |
| 医師情報 | 診断書を作成した医師の氏名 | |
| 押印 | 医療機関または医師の公印 |
会社に提出する場合、病名がプライベートな情報であるため、どこまで会社に伝えるべきか悩む方もいるかもしれません。一般的には、休職の必要性を証明するためには病名の記載が必要ですが、精神疾患などの場合、会社によっては「業務に支障をきたす病状である」といった程度で、病名を伏せた形での診断書発行が可能か医師に相談できる場合もあります。ただし、多くの場合は正式な病名の記載が求められるため、事前に会社の規定や人事担当者と確認しておくことをお勧めします。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

休職のための診断書 もらい方:具体的な手順

休職のための診断書を取得するには、いくつかのステップがあります。適切に進めることで、スムーズに診断書を受け取ることができます。
ステップ1:医療機関を受診する
まずは、あなたの現在の不調について相談できる医療機関を受診することから始まります。
何科を受診すべきか(精神科・心療内科など)
どのような症状で休職を考えているかによって、受診すべき科が異なります。
- 精神的な不調が主な場合:
- 心療内科: ストレスなどが原因で、動悸や腹痛、頭痛、不眠といった身体的な症状が現れている場合や、気分の落ち込み、倦怠感などの精神的な症状があるが、まずは身体的な検査も含めて広く相談したい場合に適しています。内科的なアプローチも含めて診察を行う場合が多いです。
- 精神科: 気分の落ち込みがひどい、意欲が出ない、不安感が強い、幻覚や妄想があるなど、精神的な症状が顕著な場合に適しています。心の病気の専門医が診察を行います。
- どちらを選べば良いか迷う場合: どちらの科でも精神的な不調の相談は可能です。初診で診断書発行の可否や、自身の症状について相談したい旨を伝えて予約する際に、受付に相談してみるのも良いでしょう。最近では、心療内科と精神科の両方を標榜しているクリニックも多いです。
- 身体的な不調が主な場合:
- 不眠や胃腸の不調など、特定の身体症状が強い場合は、まず内科や消化器内科など、その症状に応じた専門科を受診するのが適切です。
- ただし、身体症状の背景にストレスや精神的な問題が強く疑われる場合は、心療内科や精神科の受診も視野に入れることが重要です。
ご自身の症状をよく観察し、どの科が適切か判断しましょう。判断が難しい場合は、かかりつけ医に相談するか、総合病院の窓口に問い合わせてみるのも一つの方法です。
医療機関の選び方と予約
受診する医療機関を選ぶ際は、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 専門性: あなたの症状に合った専門医がいるか。特に精神科や心療内科の場合、医師との相性も重要です。
- アクセス: 自宅や会社から通いやすい場所にあるか。定期的な通院が必要になる可能性もあります。
- 予約の取りやすさ: 初診は予約必須の医療機関が多いです。公式サイトや電話で予約状況を確認しましょう。人気のクリニックは予約が取りにくいこともあります。
- 診断書発行について: 初診での診断書発行が可能か、発行にどれくらい日数がかかるかなど、事前に電話などで確認できるとよりスムーズです。全ての医療機関が初診で診断書を発行するわけではありません。
- 口コミや評判: インターネット上の口コミや知人からの情報も参考になりますが、あくまで個人の感想であることを理解しておきましょう。
受診する医療機関を決めたら、必ず事前に予約を取りましょう。特に精神科や心療内科は予約なしでは診察を受けられない場合が多いです。予約時には、簡単な症状の説明と、休職のために診断書が必要になる可能性がある旨を伝えておくと、医療機関側も準備しやすくなります。
ステップ2:医師に現在の症状や状況を正確に伝える
診察時には、医師にあなたの現在の症状や困っている状況を正確かつ具体的に伝えることが非常に重要です。診断書は医師があなたの状態を医学的に判断し、作成するものです。情報が不足していると、適切な診断や、休職の必要性の判断が難しくなります。
伝えるべき内容の例:
- 症状について:
- いつ頃から症状が出始めたか(例: 〇ヶ月前から)
- どのような症状があるか(例: 朝起きられない、体がだるい、頭痛がひどい、眠れない、食欲がない、気分が沈む、集中できない、イライラする、物忘れが増えたなど)
- 症状の程度(例: どのくらいつらいか、一日の中で変動はあるか)
- 症状によって日常生活や仕事にどのような支障が出ているか(例: 通勤が困難、業務中にミスが増えた、会議に出られない、趣味を楽しむ気力がない、家事ができないなど)
- 仕事の状況について:
- 現在の職務内容
- 症状が仕事にどう影響しているか
- 職場の環境(人間関係、業務量、労働時間など)でストレスを感じていること
- 休職の希望について:
- 現在、休職を検討していること
- 休職したいと考えている理由(例: このままでは心身が壊れてしまう、回復のために仕事から離れたいなど)
- 会社から診断書の提出を求められていること
- これまでの対処:
- これまで自分でどのような対処を試みたか(例: 休息をとる、気分転換をする、市販薬を飲むなど)
- 他の医療機関を受診したことがあるか(ある場合はその経緯や診断結果)
可能であれば、症状が出始めた時期や、症状が特に辛いと感じる出来事、仕事内容などを事前にメモしておくと、診察時にスムーズに伝えられます。正直に、具体的に伝えることが、医師があなたの状態を正しく理解するための鍵となります。また、休職が必要であると医師が判断すれば、診断書の発行に進むことができます。
ステップ3:医師に診断書の発行を依頼する
診察の結果、医師が休職が必要な状態であると判断した場合、診断書の発行を依頼します。
診察の終わりに、医師に「休職のために診断書が必要なのですが、発行していただけますでしょうか?」と明確に依頼しましょう。この時、診断書の用途(会社提出用、傷病手当金申請用など)や、必要な記載事項(会社から指定されている場合)があれば伝えます。
発行の可否や発行までにかかる日数、費用についてもこの時に確認しておくと良いでしょう。多くの医療機関では、診断書は診察後すぐに発行されるわけではなく、作成に数日かかることが一般的です。
会社指定の診断書フォーマットがある場合
会社によっては、独自の診断書フォーマットを用意している場合があります。会社指定のフォーマットがあるかどうか、事前に人事担当者や上司に確認しておきましょう。
会社指定のフォーマットがある場合は、受診する際に必ず持参し、医師に「この書式で診断書を作成していただけますでしょうか?」と依頼します。医師がそのフォーマットへの記入が可能であれば対応してもらえますが、医療機関によっては独自の書式でのみ発行している場合もあります。その際は、医療機関の書式で発行してもらい、会社に提出する際に「医療機関の書式で発行してもらいました」と伝えれば、通常は問題なく受理されます。もし会社から改めて指定書式での提出を求められた場合は、再度医療機関に相談が必要になる可能性があります。事前に会社側とよく連携しておくことが重要です。
ステップ4:診断書を受け取る
診断書が完成したら、指定された日時に医療機関に受け取りに行きます。
受け取り時には、以下の点を確認しましょう。
- 記載内容: 患者氏名、傷病名、療養期間、発行年月日、医療機関名、医師名などに間違いがないか確認します。特に、療養期間が会社の休職規定に合っているか、またはあなたの希望する期間と大きくずれていないかなどは、医師と相談して決定した内容と照らし合わせましょう。
- 押印: 医療機関や医師の正式な押印があるか確認します。
- 枚数: 会社提出用と傷病手当金申請用など、複数枚必要な場合は全て揃っているか確認します。通常、原本は1枚のみ発行され、複数枚必要な場合はコピーで対応可能か会社や申請先に確認するのが一般的ですが、原本が複数枚必要な場合は、その旨を受付に伝えて発行してもらう必要があります(別途費用がかかることがあります)。
診断書を受け取る際は、多くの場合、発行手数料の支払いが必要です。費用については後述します。受け取った診断書は、会社への提出や手続きに必要となりますので、大切に保管しましょう。
休職のための診断書の即日発行は可能?発行までの期間

休職の必要性を感じてすぐにでも会社に提出したい、という場合、診断書を即日発行してもらえるのか気になる方も多いでしょう。
診断書が即日発行される可能性
結論と言うと、休職のための診断書が即日発行される可能性は低いです。
その理由は以下の通りです。
- 医師の判断に時間を要する: 特に初診の場合、医師は患者の症状、病歴、現在の状況などを詳しく聞き取り、必要に応じて検査を行い、総合的に判断して診断名を確定し、休職の必要性や期間を判断します。このプロセスには一定の時間がかかります。
- 診断書の作成作業: 診断書は重要な公的書類であり、医師が責任を持って正確に記載する必要があります。診察後、医師が診断書作成のための時間を確保し、内容を吟味して作成するため、すぐには手渡せないことが多いです。
- 医療機関の事務手続き: 診断書の作成は医師だけでなく、医療機関の事務スタッフも関わる手続きです。他の業務との兼ね合いもあり、即時対応が難しい場合があります。
ただし、以下のような場合は、ごく稀に即日発行が可能なケースもゼロではありません。
- 症状が非常に重く、誰が見ても一刻を争う状態である場合: 緊急性が高く、診断や休職の必要性が明確な場合。
- 以前から通院しており、症状が悪化して急遽休職が必要になった場合: 既に病状や経過を医師が把握している場合。
- 医療機関の方針や混雑状況による: たまたま医師や事務スタッフに余裕があり、緊急対応として例外的に即日対応してもらえる場合。
しかし、これらはあくまで例外であり、即日発行を前提にスケジュールを組むのは避けるべきです。基本的には、診断書の発行には数日かかるものと考えて準備を進めましょう。
診断書発行にかかる一般的な日数
休職のための診断書発行にかかる一般的な日数は、受診した日から数日〜1週間程度が多いです。
これは、医療機関の規模や混雑状況、医師の勤務状況などによって異なります。
- 個人クリニック: 比較的スムーズに発行されることが多く、数日程度で受け取れる場合があります。
- 総合病院: 多くの診療科があり、患者数も多いため、事務手続きに時間がかかり、1週間程度かかることも珍しくありません。
受診時に必ず発行までにかかる日数を確認し、会社への提出期限がある場合は、その旨を医師や受付に伝え、いつまでに必要か相談してみましょう。提出期限に間に合わない場合は、会社にその旨を連絡し、提出が遅れることの理解を得る必要があります。
診断書の療養期間・開始日の記載について
診断書に記載される「必要な療養期間」や「療養開始日」は、医師があなたの症状、病状の経過、仕事内容、職場環境などを総合的に判断して決定します。
- 必要な療養期間: 「○ヶ月間」「〇〇年〇月〇日まで」といった形で記載されます。医師は、あなたの回復に必要だと考える期間を医学的な観点から判断します。あなたが希望する期間を医師に伝えることは可能ですが、最終的な判断は医師に委ねられます。例えば、「まず1ヶ月休んで様子を見たい」「〇月末までには復帰したい」といった希望があれば、診察時に相談してみましょう。医師はあなたの希望も考慮しつつ、医学的な根拠に基づいて判断します。
- 療養開始日: これは診断書が発行された日、あるいは症状が出て仕事に支障をきたすようになった日、あるいは会社と相談して休職開始日とする予定の日などを記載することが考えられます。一般的には、受診日を療養開始日とすることが多いですが、医師との相談によって柔軟に対応してもらえる場合もあります。遡って過去の日付を療養開始日とすることも医学的に妥当と医師が判断すれば可能ですが、会社の規定によって認められないケースもあるため、会社側とも事前に調整が必要です。
これらの記載内容は、休職期間や傷病手当金の支給期間に影響するため、重要な項目です。医師とよく相談し、会社の規定も踏まえながら、適切な内容で記載してもらうように依頼しましょう。
休職のための診断書がもらえないケースとその対処法

心身の不調を感じて医療機関を受診し、休職のための診断書の発行を依頼しても、必ずしも診断書がもらえるとは限りません。診断書がもらえないケースにはいくつかの理由があります。
診断書をもらえない主な理由
診断書の発行は医師の医学的な判断に基づきます。以下のような場合、医師が診断書の発行は難しいと判断することがあります。
診断の根拠が不明確な場合
- 症状が客観的に確認できない、または軽微である: 患者さんの訴えはあるものの、医学的な検査や診察で異常が認められない、あるいは症状が非常に軽微で、医学的に「就労が困難な状態である」と判断する根拠に乏しい場合。
- 診断基準を満たさない: 医師は診断名を付ける際に、確立された診断基準(例: ICD-10, DSM-5など)に基づきます。症状がこれらの基準を満たさない場合、特定の診断名をつけることができず、診断書を作成できないことがあります。
- 情報不足: 患者さんが症状や困っている状況をうまく伝えられず、医師があなたの状態を十分に把握できない場合。特に精神的な不調の場合、客観的なデータがないため、患者さんからの情報が非常に重要になります。
診断書発行の条件を満たさない場合
- 医学的に休職の必要がないと医師が判断した場合: 医師があなたの状態は医学的に見て休職するほどではない、通院や業務内容の調整で対応可能であると判断した場合。
- 医療機関の方針: 一部の医療機関では、初診での診断書発行には慎重であったり、一定期間の通院を経て病状の経過を確認してからでないと診断書を発行しない方針をとっていたりします。
- 患者さんの訴えと医師の判断に乖離がある: 患者さんは休職を強く希望していても、医師が診察を通じて「休職が必要な状態ではない」「他の目的で診断書を求めている可能性がある」と判断した場合。
医師は、あくまで医学的な観点から診断書を発行します。患者さんの希望だけではなく、客観的な病状や就労困難性を判断の根拠とします。
診断書がもらえない場合の対処法
診断書の発行を依頼してももらえなかった場合、どのように対処すれば良いでしょうか。
セカンドオピニオンを求める
一つの医療機関で診断書がもらえなかった場合、別の医療機関を受診し、セカンドオピニオンを求めることが有効な手段です。
- 別の医師の診断を受ける: 医師によって診断や判断の基準、得意とする分野が異なる場合があります。別の医師に診察してもらうことで、異なる視点からの診断や、休職の必要性に関する別の判断が得られる可能性があります。
- 受診時のポイント:
- これまでの経緯(いつから症状が出ているか、どのような医療機関を受診したか、そこでどのような診断や判断があったか)を正直に伝えましょう。
- 前回の医療機関での診断書発行依頼の経緯(なぜもらえなかったのか、医師からどのような説明を受けたか)も伝えることで、新たな医師は状況を把握しやすくなります。
- 改めて、現在の症状や、それが仕事や日常生活に与える影響を具体的に、分かりやすく伝えましょう。
- 休職を検討している理由や、診断書が必要な状況を明確に伝えましょう。
- 医療機関の選び方: 最初の医療機関とは異なるタイプの医療機関(例: 個人クリニックとも異なり、総合病院など)や、心療内科/精神科の専門医がいる医療機関を選ぶことも検討しましょう。
セカンドオピニオンでも診断書の発行が難しい場合、もしかしたら医学的に見て休職が必要な状態ではないのかもしれません。その場合は、休職以外の方法(業務内容の調整、時短勤務、部署異動など)で、症状を軽減しながら働き続ける方法を会社と相談することも視野に入れる必要があります。
また、改めて自身の症状を正確に医師に伝える努力をすることも重要です。診察時間が限られている中で、辛さをうまく伝えられないこともあるかもしれません。症状が出始めた時期や、仕事や生活で具体的に困っていることをメモにして医師に見せるなどの工夫も有効です。
休職診断書の費用はいくら?

休職のための診断書は、医療行為ではなく書類作成であるため、健康保険の適用外となり、全額自己負担(自由診療)となります。そのため、医療機関によって費用が異なります。
診断書の発行にかかる一般的な費用相場は、3,000円から10,000円程度が多いです。
| 診断書の種類 | 一般的な費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 休職診断書 | 3,000円~10,000円 | 会社提出用など、一般的な書式の場合。医療機関により異なる。 |
| 傷病手当金申請書 | 3,000円~10,000円 | 健康保険組合指定の書式の場合。医療機関により異なる。 |
| 特定疾患の診断書 | 5,000円~10,000円以上 | 障害年金申請用など、より詳細な記載が必要な場合。複雑性により変動。 |
| 会社指定フォーマット | 3,000円~10,000円 | 医療機関の判断によるが、通常の診断書と同等か少し割高な場合も。 |
| 再発行・複数枚発行 | 1,000円~5,000円 | 医療機関による。コピーの場合は無料〜数百円の場合も。 |
費用の特徴:
- 医療機関による違い: 個人のクリニックよりも、総合病院の方がやや高額な傾向があります。
- 記載内容の複雑性: より詳細な病状の説明や、特別な検査結果の記載が必要な場合など、診断書の記載内容が複雑になるほど費用が高くなることがあります。
- 用途による違い: 会社提出用と傷病手当金申請用では、書式が異なることがあり、それぞれに費用がかかる場合があります。
- 健康保険適用外: 診察料とは別に費用がかかります。診察料は通常健康保険が適用されますが、診断書発行手数料は全額自己負担です。
受診予約時や診察時に、休職診断書の発行手数料がいくらになるか、事前に確認しておくことをお勧めします。また、会社や健康保険組合から特定の書式を指定されている場合は、その書式への記入が可能かどうかも含めて費用を確認しましょう。
診断書は、休職中も継続的な提出が必要になる場合があります(例: 〇ヶ月ごとに病状報告として)。その都度費用がかかる可能性があるため、長期の休職を検討している場合は、継続的な診断書提出の要否や頻度について会社と確認しておくと良いでしょう。
休職診断書を会社に提出する際の注意点

診断書を受け取ったら、次は会社に提出する手続きです。診断書の提出だけでなく、会社への報告・連絡も適切に行うことが、休職を円滑に進めるために重要です。
診断書を提出するタイミング
休職の必要性を感じ始めたら、診断書を取得する前に、まずは直属の上司や人事担当者に相談することをお勧めします。突然診断書だけを提出するのではなく、現在の体調や仕事への影響について相談し、休職を検討している旨を伝えましょう。
診断書が発行されたら、速やかに会社に提出するのが基本的なルールです。提出が遅れると、会社の休職手続きが進まず、場合によっては休職の開始時期に影響が出たり、無断欠勤扱いになったりする可能性があります。
- 理想的な流れ:
- 体調不良を感じ、上司や人事担当に相談する(休職の可能性があることを伝える)。
- 医療機関を受診し、医師に症状を伝え、休職の必要性について相談する。
- 医師から休職の診断を受け、診断書の発行を依頼する(発行までにかかる日数を確認)。
- 診断書を受け取り次第、速やかに会社に提出する。
診断書の発行に日数がかかる場合は、発行見込み日を会社に伝え、「発行され次第すぐに提出します」と連絡を入れておきましょう。
会社への報告・連絡
診断書の提出と合わせて、会社への報告・連絡は非常に重要です。
- 休職の意思を伝える: 上司や人事担当者に、診断書を取得したこと、診断書に基づいて休職したいという意思を明確に伝えましょう。
- 診断書の内容を説明する: 診断書に記載されている病名、必要な療養期間、医師からの指示(自宅療養など)について、会社の規定で求められる範囲で説明します。病名については、どこまで伝えるべきか事前に会社の規定を確認したり、人事担当者に相談したりしましょう。通常、病名が記載された診断書を提出すれば、詳細な病状を全て話す必要はありませんが、休職期間や復職の可能性について、医師の意見を伝えることは重要です。
- 今後の手続きについて確認する:
- 休職期間: 診断書に記載された療養期間を基に、会社の就業規則に則った休職期間が決定されます。期間の延長や短縮の可能性についても確認しておきましょう。
- 給与・社会保険料: 休職中の給与の扱い(有給か無給か)、社会保険料(健康保険、厚生年金保険など)の支払い方法について確認します。傷病手当金の申請方法も確認しましょう。
- 会社との連絡方法: 休職期間中に会社とどのように連絡を取り合うか(連絡頻度、連絡手段、連絡内容の範囲など)を決めておきましょう。療養に専念するためにも、必要最低限の連絡に留めることが望ましいです。復職に向けた面談などが必要になる場合もあります。
- 必要な手続き: 休職願の提出など、診断書以外に会社に提出する必要がある書類や手続きがないか確認します。
- 診断書の提出方法: 診断書はどのように会社に提出するか(手渡し、郵送、メールでのデータ送付など)を確認します。重要な書類ですので、郵送の場合は簡易書留にするなど、確実な方法を選びましょう。
会社によっては、休職に関する面談を実施する場合があります。その際は、あなたの現在の状況や休職の必要性について説明し、会社側の理解を得ることが大切です。休職中の過ごし方や、復職に向けたステップについても、会社と連携しながら進めていくことになります。
まとめ

休職のための診断書は、あなたが心身の不調により仕事から離れて療養する必要があることを客観的に証明する重要な書類です。法律上の義務ではない場合でも、多くの会社で休職申請に際して提出が求められます。
診断書を取得するためには、まず現在の症状に応じた医療機関(心療内科、精神科、その他専門科など)を受診し、医師に症状や休職の希望を正確に伝えることが第一歩です。診察の結果、医師が休職の必要性を認めれば、診断書の発行を依頼できます。
診断書の発行には、一般的に受診日から数日〜1週間程度の日数がかかり、即日発行は難しいケースが多いです。費用は健康保険適用外で、医療機関によって異なりますが、3,000円〜10,000円程度が相場となります。
もし診断書がもらえなかった場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることや、改めて症状を具体的に伝える努力をすることが考えられます。
診断書を受け取ったら、速やかに会社に提出し、休職の意思や診断書の内容を報告するとともに、休職期間中の手続きや会社との連絡方法について確認しましょう。
心身の不調は、早めに医療機関に相談し、適切な診断とサポートを受けることが回復への近道です。休職を検討されている方は、この記事を参考に、診断書取得と休職に向けた手続きをスムーズに進めていただければ幸いです。
【免責事項】
この記事で提供する情報は、一般的な知識に基づくものです。個々の症状、会社の規定、医療機関の方針などによって対応は異なります。実際の休職に関する判断や手続きについては、必ず会社の規定を確認し、医療機関で医師に相談してください。この記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。
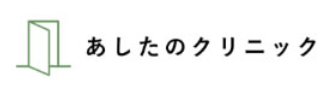

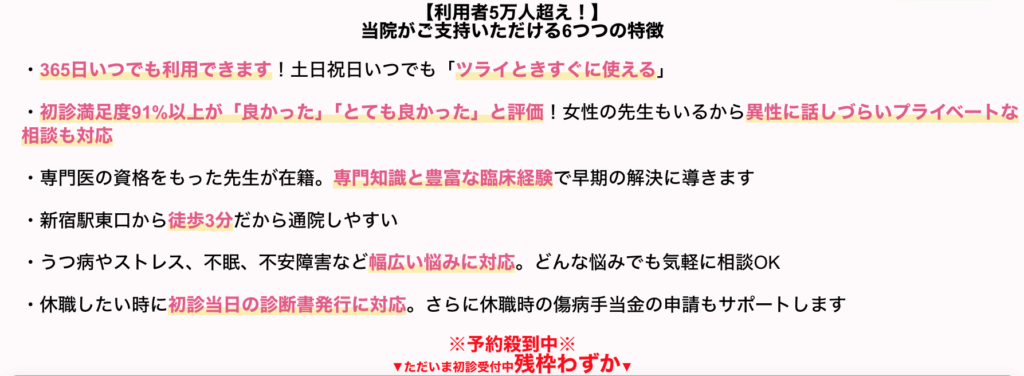



コメント