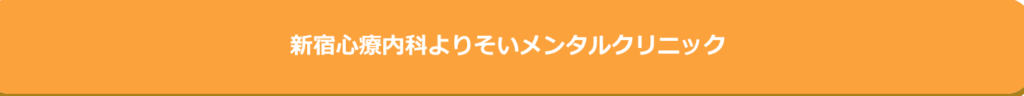
「最近、なんだか息苦しい…」「もしかして、これってパニック障害の症状?」そんな不安を抱えていませんか。
突然の息苦しさや、理由のわからない呼吸の困難感は、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
特に、それがパニック障害によるものだとしたら、適切な理解と対処が必要です。
この記事では、パニック障害によってなぜ息苦しさが生じるのか、そのメカニズムを詳しく解説します。
また、軽い息苦しさも含め、パニック障害による息苦しさの特徴や、いざという時の対処法、そして根本的な治療法についてもご紹介します。
息苦しさの原因が分からず不安な日々を送っている方が、少しでも安心して適切な一歩を踏み出せるよう、具体的な情報をお届けします。
パニック障害で息苦しさを感じる原因

パニック障害の方が息苦しさを感じるのは、決して気のせいではありません。
そこには、心と体の複雑なメカニズムが関係しています。
なぜ息がしづらくなるのか?
パニック障害における息苦しさは、主に自律神経の乱れによって引き起こされます。
強い不安や恐怖を感じると、交感神経が過剰に働き、心拍数の増加、血管の収縮、呼吸が浅く速くなるなどの身体反応が起こります。
これが「過呼吸」と呼ばれる状態につながることがあります。
過呼吸とは、「精神的不安や極度の緊張などにより過呼吸の状態となり、血液が正常よりもアルカリ性となることで様々な症状を出す状態です」と、日本呼吸器学会のウェブサイトでも説明されています。
この過呼吸になると、血液中の二酸化炭素濃度が低下し、結果として脳への酸素供給が十分に行き渡りにくくなることがあります。
皮肉なことに、酸素をたくさん取り込もうとすればするほど、息苦しさが増してしまうのです。
また、不安感から喉や胸の筋肉が緊張し、物理的に息がしづらく感じることもあります。
不安と息苦しさの関係性
不安と息苦しさは、非常に密接に関連しています。
まず、何らかのきっかけで不安を感じると、前述のような身体反応が起こり、息苦しさを覚えます。
すると、「このまま息ができなくなるのではないか」「何か重大な病気なのではないか」といった更なる不安(予期不安)が生じ、それがまた息苦しさを悪化させるという悪循環に陥りやすいのです。
この悪循環は、パニック発作を経験した人にとって特に顕著で、特定の場所や状況で「また発作が起きたらどうしよう」と考えるだけで、息苦しさを感じてしまうことも少なくありません。
パニック障害による息苦しさの特徴

パニック障害による息苦しさには、いくつかの特徴があります。
ご自身の症状と照らし合わせてみましょう。
軽い息苦しさも症状の一つか
「すごく苦しいわけではないけれど、なんとなく息が浅い感じがする」「常に胸が詰まったような感じがする」といった軽い息苦しさも、パニック障害の症状の一つである可能性があります。
特に、パニック発作とまではいかなくても、慢性的な不安感や緊張感を抱えている場合に見られることがあります。
このような状態は「全般性不安障害」など、他の不安障害と共通する部分もありますが、パニック障害の初期症状や、発作が起こっていない時期の持続的な症状として現れることもあります。
突然の息苦しさとは
パニック発作の際には、多くの場合、突然の強烈な息苦しさに襲われます。
厚生労働省のウェブサイトによると、パニック障害とは「突然激しい恐怖または強烈な不快感の高まりが数分以内でピークに達するもの」であり、その症状として「動悸、発汗、息苦しさ、どうにかなってしまいそうな感じなど複数の症状が同時に現れます。」と定義されています。
まるで溺れているかのような感覚や、空気を吸っても吸っても足りないような感覚、窒息するのではないかという恐怖感を伴うことが特徴です。
この息苦しさは、多くの場合、数分から数十分程度でピークに達し、その後徐々に落ち着いていきますが、本人にとっては非常に長く、耐え難い時間に感じられます。
息苦しさ以外の主な随伴症状
パニック発作では、息苦しさ以外にも様々な身体症状や精神症状が現れます。
これらが複合的に現れることで、さらに強い恐怖感や苦痛を感じることになります。
- 動悸、心拍数の増加
- めまい、ふらつき
- 吐き気、腹部の不快感
- 手足の震え、しびれ
- 発汗
- 悪寒または熱感
- 現実感の喪失、離人感
- コントロールを失うことへの恐怖
- 死への恐怖
これらの症状は個人差があり、全てが現れるわけではありません。
【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!
心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。
提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

息苦しさを伴う他の疾患との違い

息苦しさはパニック障害だけでなく、他の様々な身体疾患でも見られる症状です。
自己判断せずに、医療機関で正確な診断を受けることが非常に重要です。
呼吸困難の鑑別診断については、国立長寿医療研究センターのウェブサイトでも詳しく解説されており、心因性呼吸困難の評価項目なども示されています。
貧血や脳貧血との鑑別
貧血や脳貧血(起立性低血圧など)でも、息切れやめまい、ふらつきといった症状が現れるため、パニック障害の症状と混同されることがあります。
これらの違いを理解することは重要ですが、あくまで目安であり、正確な診断は医師が行います。
| 症状 | パニック障害 | 貧血・脳貧血 |
|---|---|---|
| 息苦しさ | 突然の強い息苦しさ、窒息感、過呼吸を伴うことが多い | 労作時の息切れ、酸素不足感 |
| 不安感 | 非常に強い不安、恐怖、予期不安を伴う | 不安感は主症状ではない場合がある |
| 発症状況 | 特定の状況や予期不安で誘発されることがある | 労作時、急な体位変換時などに起こりやすい |
| その他症状 | 動悸、めまい、吐き気、手足のしびれ、死の恐怖など | 顔面蒼白、立ちくらみ、倦怠感、頭痛、集中力低下など |
パニック障害の特徴は、強い不安感や恐怖感を伴うことです。
しかし、これらの症状だけで自己判断するのは危険です。
血液検査などで貧血の有無を確認したり、起立性低血圧の検査をしたりすることで、鑑別診断が行われます。
その他の可能性のある身体疾患
息苦しさを引き起こす可能性のある主な身体疾患には、以下のようなものがあります。
- 呼吸器疾患: 気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺炎、気胸など。
- 心疾患: 狭心症、心筋梗塞、心不全、不整脈など。
- 甲状腺機能亢進症: 甲状腺ホルモンの過剰分泌により、動悸や息切れ、発汗などが起こります。
- その他: 肺塞栓症、アレルギー反応(アナフィラキシー)など。
これらの疾患は、放置すると命に関わる可能性もあるため、息苦しさが続く場合は、まず内科や循環器科、呼吸器科などの身体科を受診し、身体的な問題がないかを確認することが重要です。
身体的な異常が見つからない場合に、精神科や心療内科の受診が勧められることが一般的です。
パニック障害による息苦しさの対処法

パニック障害による息苦しさは非常につらいものですが、発作時や日常生活で試せる対処法があります。
発作時に試せる具体的な対応
パニック発作が起きてしまった場合、以下の方法を試すことで、症状を和らげることができるかもしれません。
ただし、無理は禁物です。
- ゆっくりとした呼吸を意識する(腹式呼吸など):
息を吸うよりも、ゆっくりと時間をかけて息を吐き出すことを意識します。
「1、2、3、4」で鼻からゆっくり息を吸い、「1、2、3、4、5、6、7、8」で口からゆっくりと息を吐き出すなど、自分に合ったペースで行いましょう。
過呼吸になっている場合は、紙袋を口と鼻に軽く当てて呼吸する「ペーパーバッグ法」が知られていますが、酸素濃度が下がりすぎるリスクもあるため、医師の指導がない場合は安易に行わない方が良いという意見もあります。
まずはゆっくりとした呼吸を試みましょう。 - 安全な場所に移動する:
可能であれば、人混みや騒がしい場所を避け、静かで落ち着ける場所に移動しましょう。
壁際や隅など、安心できる場所に座るのも良いでしょう。 - 意識を別のことに向ける:
「息が苦しい」という感覚に集中しすぎると、余計に不安が増してしまいます。
周りの景色をじっくり観察する、心の中で数を数える、好きな歌を思い浮かべるなど、意識を別の対象に向けるようにしましょう。
手のひらをギュッと握って力を入れ、その後フッと力を抜く、といった簡単な動作を繰り返すのも効果的な場合があります。 - 頓服薬の使用(医師から処方されている場合):
医師から発作時のための頓服薬(抗不安薬など)を処方されている場合は、指示通りに服用しましょう。
日常生活で取り組むセルフケア
パニック発作を予防し、息苦しさを感じにくい状態を保つためには、日常生活でのセルフケアも重要です。
- 規則正しい生活:
十分な睡眠時間を確保し、毎日同じ時間に寝起きするなど、生活リズムを整えましょう。
バランスの取れた食事を心がけましょう。 - 適度な運動:
ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、ストレス解消や自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。
無理のない範囲で継続しましょう。 - ストレスマネジメント:
自分に合ったリラックス方法を見つけましょう(例:深呼吸、瞑想、音楽を聴く、アロマテラピー、入浴など)。
趣味の時間を楽しむことも大切です。 - カフェインやアルコールの摂取を控える:
カフェインやアルコールは、交感神経を刺激し、不安感を増強させたり、睡眠の質を低下させたりする可能性があるため、摂取を控えるか、量を減らすようにしましょう。 - 禁煙:
喫煙は呼吸器系に悪影響を与えるだけでなく、不安を悪化させる可能性も指摘されています。
息苦しさから解放されるための治療法

セルフケアだけでは症状の改善が難しい場合や、日常生活に支障が出ている場合は、専門家による治療が必要です。
医療機関での診断プロセス
精神科や心療内科では、まず詳細な問診が行われます。
いつから、どのような状況で、どの程度の頻度で息苦しさやその他の症状が現れるのか、日常生活への影響などを詳しく伝えます。
必要に応じて、心理検査(質問紙や面接形式など)が行われ、不安の程度や特性が評価されます。
また、前述の通り、息苦しさの原因が身体的な疾患でないことを確認するために、血液検査や心電図検査、呼吸機能検査などが他の診療科と連携して行われることもあります。
これらの情報を総合的に判断し、パニック障害の診断が下されます。
主な薬物療法について
パニック障害の治療には、主に以下の薬物が用いられます。
薬物療法は、医師の指示に従って適切に使用することが重要です。
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬):
脳内のセロトニンという神経伝達物質のバランスを整えることで、不安感やパニック発作を抑える効果が期待されます。
効果が現れるまでに数週間かかることが一般的です。
副作用として、吐き気や眠気、頭痛などが現れることがありますが、徐々に軽減していくことが多いです。 - 抗不安薬(ベンゾジアゼピン系など):
即効性があり、強い不安感やパニック発作を迅速に和らげる効果があります。
主に頓服薬として、あるいはSSRIの効果が出るまでの補助として用いられます。
眠気やふらつきなどの副作用や、長期使用による依存性のリスクがあるため、医師の指示通りに服用し、自己判断で増量したり中断したりしないことが大切です。 - その他: ベータ遮断薬(動悸を抑える)などが症状に応じて使われることもあります。
薬物療法は、症状をコントロールし、精神療法を受けやすくする土台を作る役割も担います。
精神療法(カウンセリング)の役割
薬物療法と並行して、あるいは薬物療法が合わない場合に、精神療法(カウンセリング)が行われます。
特に認知行動療法(CBT)は、パニック障害に対して有効性が高いとされています。
- 認知行動療法(CBT):
パニック発作や予期不安を引き起こす誤った認知(考え方の癖)を修正し、より現実的で柔軟な考え方ができるようにサポートします。
また、不安を感じる状況に段階的に直面する「曝露療法(エクスポージャー)」を通じて、不安への対処能力を高めていきます。
呼吸法やリラクセーション法などの具体的な対処スキルも学びます。
精神療法を通じて、自分の不安や恐怖と向き合い、それらをコントロールする方法を身につけることで、根本的な改善を目指します。
息苦しさが続く場合は専門家へ相談を

これまで述べてきたように、息苦しさの原因がパニック障害である場合、適切な対処と治療を行えば、症状は改善していきます。
しかし、自己判断で放置したり、誤った対処を続けたりすると、症状が悪化したり、慢性化したりする可能性があります。
「もしかしたら…」と感じたら、一人で抱え込まずに、まずは精神科や心療内科の医師に相談してみましょう。
専門家はあなたの状態を正確に把握し、あなたに合った治療法を提案してくれます。
息苦しさのない、穏やかな日常を取り戻すために、勇気を出して一歩を踏み出すことが大切です。
免責事項
本記事は、パニック障害による息苦しさに関する一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断や治療を推奨するものではありません。
息苦しさやその他の症状でお悩みの方は、必ず医療機関を受診し、医師の指導に従ってください。
本記事の情報に基づいて行った行動により生じた一切の損害について、責任を負いかねますのでご了承ください。
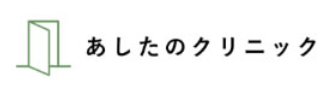

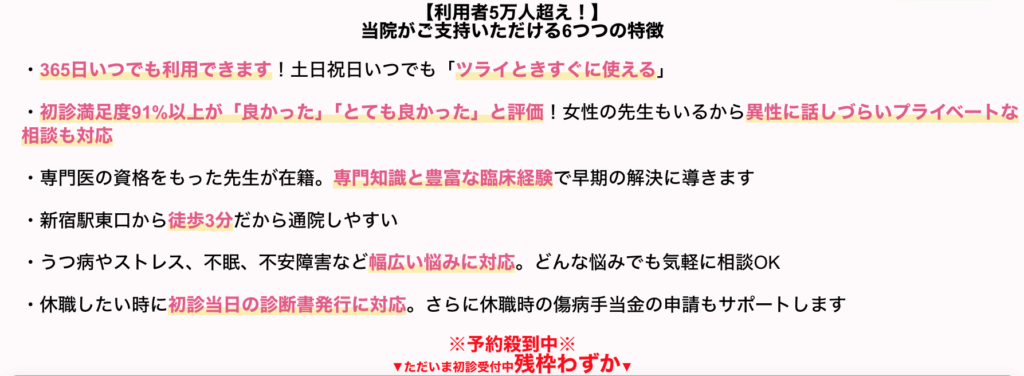



コメント